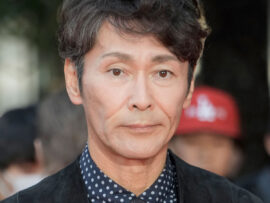予期せぬ時に生理が始まり、生理用品の持ち合わせがなくて困った経験は、多くの女性にとって身近なものだろう。「トイレットペーパーのように、生理用品がトイレに常備されていたら」――今、そんな切実な声に応え、公共施設や企業などのトイレに生理用品を無償で設置する画期的な取り組みが全国で広がっている。その中心にあるのが、スマートフォンアプリを活用した無料生理用品サービス「OiTr(オイテル)」だ。この記事では、OiTrの革新的な仕組み、その導入状況、そして利用者、企業、社会にもたらす多角的なメリットについて深掘りする。
「無料」を実現するOiTrのビジネスモデル
OiTr(オイテル)は、スマートフォンのアプリを使って生理用ナプキンを無料で受け取れるサービスである。トイレの個室に設置された専用ディスペンサーにスマートフォンをかざし、アプリの「取り出し」ボタンをタップするだけで、ナプキンを1個取り出すことが可能だ。
この「無料」の裏側には、ユニークで持続可能なビジネスモデルが存在する。ナプキン自体のコストは、ディスペンサーのディスプレイで配信される動画広告の収入によって賄われる仕組みだ。これは、ユーザー(ナプキンを必要とする人)、スポンサー企業(広告主)、そして設置側(施設や企業)のすべてが恩恵を受ける「三方よし」の設計となっている。このモデルにより、ユーザーは急な生理の際に無料で生理用品を入手でき、安心感を得られる。
全国に広がるOiTrの導入状況と多角的なメリット
OiTrは2021年8月にサービスを開始し、その設置場所は急速に拡大している。2025年7月現在、29都道府県の310施設に3471台が稼働しており、アプリのダウンロード数は140万を超えている。この普及は、生理にまつわる困りごとへの社会的な関心の高まりと、OiTrが提供する多角的なメリットが評価されている証と言えるだろう。
 江東区役所のトイレに設置されたOiTr(オイテル)のディスペンサーと、無料生理用品の提供を示すマーク。公共施設での生理用品無償提供の取り組みを示す写真。
江東区役所のトイレに設置されたOiTr(オイテル)のディスペンサーと、無料生理用品の提供を示すマーク。公共施設での生理用品無償提供の取り組みを示す写真。
具体的に、OiTrは以下の「三方よし」を実現している。
- ユーザー(生理用品を必要とする人)へのメリット:
急な生理の際に、生理用品の持ち合わせがなくても困ることがなくなる。これにより、予期せぬ事態への不安が軽減され、安心して社会生活を送れるようになる。 - スポンサー企業(広告主)へのメリット:
ディスペンサーに広告を配信することで、ターゲット層に最適化されたメッセージを届けることが可能になる。また、生理の貧困対策や女性支援といった社会貢献活動(SDGsへの貢献)を通じて、企業のブランドイメージや信頼性を向上させるブランディング効果も期待できる。 - 設置側(施設や企業)へのメリット:
利用者の満足度向上に直結し、施設や企業のホスピタリティを示すことができる。従業員向けの設置であれば、福利厚生の一環として女性従業員の働きやすい環境整備に繋がり、エンゲージメントを高める効果も期待できる。 - 社会全体へのメリット:
生理にまつわる不安、負担、不便さを軽減することは、女性の社会進出を強力に推進する基盤となる。「生理の貧困」や「生理による機会損失」といった社会課題の解決に寄与し、ジェンダー平等の実現に向けた一歩となる。
生理用品の無料提供にかける想い:男性発案者の視点
OiTrのディスペンサーとアプリを開発・製造し、サービス全体を運営しているのはオイテル株式会社だ。この画期的なサービスを発案し、実現に導いたのが同社の飯崎俊彦氏である。男性である飯崎氏がなぜ、生理という女性特有の社会課題に取り組むことになったのか、その背景には深い問題意識があった。
飯崎氏が5年前、63歳で自身のビジネス人生の集大成として社会課題の解決に取り組みたいと考えたことがきっかけだったという。その中で着目したのが「ジェンダーギャップ」だった。彼は、生理のある女性がライフステージにおいて生理による「機会損失」を多く経験している現実に目を向けた。さらに、男女間の賃金格差が依然として大きいにもかかわらず、生理用品、下着、診療費、それらにかかる消費税など、生理に伴う累計で約100万〜200万円もの出費が生じるという経済的負担にも注目した。
生理は避けて通れない現実であるにもかかわらず、その経済的・心理的な負担、さらには社会活動の足かせとなっている現状が、個人の責任として押し付けられていることに、飯崎氏は強い違和感を抱いたという。この問題意識こそが、OiTrサービス誕生の原動力となっている。
結論
OiTrは、単に生理用品を無料で提供するだけでなく、広告収入という持続可能なモデルを通じて、生理にまつわる様々な課題を解決し、女性がより安心して社会で活躍できる環境を創出している。この取り組みは、生理の貧困対策という差し迫ったニーズに応えるだけでなく、企業がSDGsに貢献し、ジェンダー平等を推進する具体的な手段としても機能している。飯崎氏のような男性がこの課題に取り組むことで、社会全体が生理に対する理解を深め、女性が直面する負担を軽減するための協力的なムーブメントがさらに加速することが期待される。OiTrの今後の展開は、よりインクルーシブで公平な社会の実現に向けた重要な一歩となるだろう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (2024年). 「江東区役所2階のトイレ。マークでオイテルが設置されていることがわかる」 [オンライン]. 入手先:
https://news.yahoo.co.jp/articles/c82b8e98b9ff6880727a54b30fd28209c3d65a02