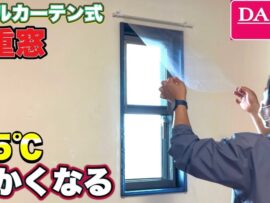前編では、日産の追浜工場(横須賀市)の閉鎖が横須賀市追浜エリアに及ぼす影響について、特に道路事情からショッピングモールやマンション街への転換が困難である点を考察しました。本稿では、引き続き工場跡地が工業用地として再活用される可能性に焦点を当て、特に日産専用埠頭の処遇が地域経済、ひいては海運事業に与える新たな課題を探ります。
追浜港・日産専用埠頭の重要性と課題
日産追浜工場の敷地内には、最大5000台の完成車を「日産専用船」(商船三井系列)で国内外に出荷できる専用埠頭が存在します。組立・製造から港からの航送までが一貫して行える「一体性」は、追浜工場の大きなメリットとされてきました。イヴァン・エスピノーサCEOも、今回の工場撤退に際し、埠頭および衝突試験場の存続を明言しています。これは、日産が追浜の立地をいまだ戦略的に捉えている証拠とも言えるでしょう。
しかし、この専用埠頭が、工場閉鎖後の追浜エリアにとって新たな、そして複雑な課題を提起しています。
追浜工場閉鎖後の専用埠頭の必要性
実際には、追浜工場の消滅後、専用埠頭が必ずしも日産にとって不可欠とは言い切れません。存続が決定している栃木工場(栃木県上三川町)からの完成車航送は、横浜市本牧の輸送基地や、茨城県の日立港などでも十分対応可能です。また、九州の苅田工場も自前の海外航送用専用埠頭を保有しており、完成車輸送の選択肢は豊富です。このような状況を鑑みると、わざわざ追浜に大規模な専用埠頭を残し続けるメリットが見えにくいのが現状です。これは、埠頭の維持管理コストを考慮すると、日産にとって合理的な選択肢とは言えない可能性を示唆しています。
売却交渉と追浜港の未来
さらに、仮に鴻海(ホンハイ)などが関心を示したと報じられたような「工場そのまま買い取り」のシナリオにおいても、新たな懸念が浮上します。もし買い手側が、高速道路網からのアクセス(横浜横須賀道路・朝比奈インターチェンジから市街地経由で7km)が不便なこの専用埠頭を「使わない」と判断した場合、日産が得られる売却評価額に大きく影響するだけでなく、追浜港そのものの必要性が一層薄れてしまう可能性があります。工業用地としての活用においても、埠頭が利用されなければ、その価値は半減することになるでしょう。
 日産村山工場跡地。追浜工場の売却と閉鎖が地域経済に与える影響を考察する上で、同様に売却された村山工場の事例は重要な比較対象となる。
日産村山工場跡地。追浜工場の売却と閉鎖が地域経済に与える影響を考察する上で、同様に売却された村山工場の事例は重要な比較対象となる。
海運事業への影響と追浜の「ダブルパンチ」
追浜港の必要性が薄れることは、追浜の街に「海運事業の衰退」という新たな難題をもたらす可能性があります。ただでさえ、かつて同港を発着していた「さんふらわあ」RORO船(貨物船)が発着地を東京有明に移すなど、「追浜離れ」が続いていました。このような状況下で、日産撤退の打撃に加えて、売却の行方次第で「海運衰退の打撃」というダブルパンチを食らいかねないのです。これは、地域経済における雇用の減少や、関連産業の衰退にも繋がりかねない深刻な問題と言えるでしょう。
結論
日産追浜工場の閉鎖は、単なる工場撤退に留まらず、その跡地利用、特に専用埠頭の処遇を巡って、横須賀市追浜エリアに複合的な課題を突きつけています。住宅・商業地への転換が困難な中、工業用地としての再活用も専用埠頭の戦略的価値が問われる状況です。もし埠頭が活用されなければ、地域経済は日産撤退による直接的な影響に加え、長年にわたり地域を支えてきた海運事業の衰退という、二重の困難に直面する可能性があり、今後の推移が注視されます。