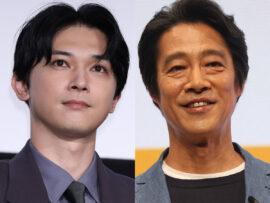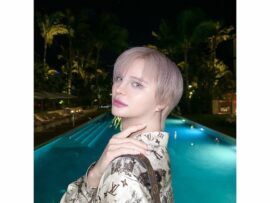「うなぎが最も美味しい季節は夏ではないのか?」そう思われている方も少なくないでしょう。しかし、その答えは一筋縄ではいきません。謎多きうなぎの生態と、現代の養殖技術の進化に焦点を当て、本当のうなぎの「旬」と、年間を通じて楽しめるその魅力について深く掘り下げていきます。
天然うなぎの本当の旬:産卵前の脂乗り
一般的に魚は産卵期に備えて多くの栄養を蓄えるため、その直前が最も美味しいとされています。うなぎも例外ではありません。天然うなぎの場合、秋から初冬にかけては脂の乗りが非常に良く、身質も柔らかくなり、まさに「旬」を迎えます。
川で成長し、背が深緑色で腹部が黄色を帯びた「黄うなぎ」が、産卵のために海へと下る準備を始めると、その体は黒ずんで光沢を放つ「銀うなぎ」へと変化します。この銀うなぎは、体側の模様が綸子織物(りんずおりもの)に似ていることから「綸子うなぎ」とも、また川を下ることから「下りうなぎ」とも呼ばれ、天然うなぎの中でも特に珍重される存在です。
養殖うなぎが変えた「夏のうなぎ」の常識

 焼き上がったうなぎの蒲焼のイメージ。美味しそうなうなぎ料理は年間を通して楽しめます。
焼き上がったうなぎの蒲焼のイメージ。美味しそうなうなぎ料理は年間を通して楽しめます。
平賀源内が広めた「本日丑の日」という習慣は、うなぎの美味しい季節についての認識を複雑化させました。現在市場に流通している活鰻の実に99%が養殖うなぎであることをご存知でしょうか。1970年代に普及したハウス式温水養殖池のおかげで、夏の土用の丑の日を前にした大量出荷が可能となりました。これにより、栄養価の高い餌を与えられて育った脂乗りが良く柔らかな養殖うなぎが年間を通じて提供されるようになり、多くの方が抱く「柔らかくて美味しいうなぎ」というイメージは、夏の養殖うなぎによって形成されたものです。
進化する養殖技術と「養鰻家」のこだわり:一年中楽しめるうなぎ
かつては、秋から冬にかけての国産養殖うなぎは旨味が増す一方で、皮が硬く調理が難しいとされ、職人を悩ませる存在でした。しかし近年、養殖技術の目覚ましい進歩と、こだわりを持ってうなぎを育てる「養鰻家(ようまんか)」たちの努力により、秋以降も美味しい養殖うなぎが出荷されるようになりました。
養鰻場を経営する「池主(いけぬし)さん」や管理する「池守(いけもり)さん」の中でも、その育成に並々ならぬ情熱を注ぐ人々を、私たちは敬意を込めて「養鰻家」と呼んでいます。うなぎファンの中には、お気に入りの養鰻家が育てたうなぎを、出荷順に「一番仔(いちばんこ)」「二番仔(にばんこ)」と呼び分けて、その時期ごとの味わいの違いを楽しむほどの深い愛好家もいるほどです。
結論として、現代においては、夏だけでなく冬も、つまり一年を通じてうなぎを美味しく食べることが可能です。「うなぎは夏限定」という概念にとらわれず、年間を通して四季折々のうなぎの味わいを深く楽しむことができるのです。そもそも「土用」は年に4回ありますから、うなぎをこよなく愛する者としては、年に4回、それぞれの季節の土用にうなぎを堪能することをお勧めします。
参考資料
- 高城 久『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)