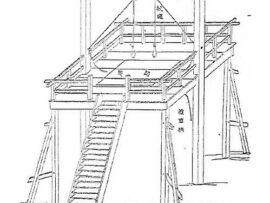7月29日に放送された日本テレビ系『DayDay.』で、国民的人気特番『はじめてのおつかい』の過去の感動名場面が特集されました。司会の森口博子さんをスタジオに迎え、長年子どもたちを見守ってきたベテランカメラマンが厳選した「忘れられないおつかい」が紹介され、視聴者からは「涙が止まらない」といった共感の声が多数寄せられました。しかしその一方で、現代社会の視点から企画そのものに対する疑問や懸念も浮上しており、長寿番組が直面する時代の変化と安全性の課題が浮き彫りになっています。
感動の裏に広がる安全性への懸念
番組で紹介されたのは、2歳8か月の男の子が兄の忘れ物を届けたり、4歳の女の子がお寺に僧侶を呼びに行くといった、幼い子どもたちの「人生初の大冒険」でした。多くの視聴者が彼らの健気な姿に心を打たれる一方で、「子どもが困って泣きそうになる状況をわざと作るのは幼児虐待ではないか」「猛暑の中、不審者、ながら運転の自転車、LUUPといった現代の危険が多い中で、幼児に一人で買い物に行かせるのは危ない」といった冷ややかな意見も少なくありません。

日本テレビ社屋の外観。人気長寿番組『はじめてのおつかい』の放送局であり、テレビ業界の社会貢献と安全対策の議論の場となっている建物の象徴的な姿。
これらの声は、放送が開始された1991年当時とは大きく異なる現代社会の安全意識を反映しています。民放キー局関係者は「おつかい中の子どもがいきなり走り出したり、転ぶハプニングを面白がる時代ではない。不用意に放送すれば、事故の危険性を指摘され責任が問われる」と語り、制作側もこうした社会の変化を痛感しているようです。かつてはハードルが高いおつかいほど感動を生むとされてきましたが、現代ではそれが「子どもに無理強いしている」と受け取られかねない状況です。不審者への警戒や、近年の酷暑の中での屋外活動は、幼い子どもを危険にさらすことにもなりかねず、番組の「安全性」に対する制作倫理が問われる局面を迎えています。
「やめどき」が難しい長寿番組の宿命
『はじめてのおつかい』は、その高い視聴率とスポンサーからの支持により、容易に終わらせることができない番組です。近年では、過去に出演した子どもたちの「その後の成長」を報告したり、タレントの子どもが「はじめてのおつかい」に挑戦する企画を増やすなど、番組側も試行錯誤を重ねて尺を持たせようとしています。
成長の見込みがない番組は即座に打ち切る傾向にある日本テレビですが、46年続く『欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞』や『24時間テレビ』のチャリティマラソンなど、局のパブリックイメージを担う長寿番組に関しては、その「やめどき」の判断が非常に慎重にならざるを得ません。社会貢献や国民的番組としての役割と、現代の安全基準や倫理観とのバランスをどう取るか、制作側は常に模索しています。
まとめ:時代の変化と共に進化する番組の意義
『はじめてのおつかい』は、確かに時代と共に変化する社会の課題に直面しています。しかし、制作スタッフは「子どもたちの安全」に細心の注意を払い、可能な限りの対策を講じているはずです。視聴者側も、番組の感動的な側面と、現代における安全への配慮という両面を理解し、幼い子どもたちのひたむきな「がんばり」を温かく見守る視点を持ち続けることが重要です。長寿番組として、社会の変化に対応しながら、その意義と価値をどう未来へ繋いでいくのか、『はじめてのおつかい』の今後の展開が注目されます。
Source: Yahoo! News Japan / Jprime