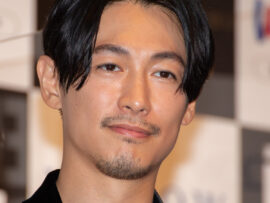2025年1月20日、ドナルド・トランプ氏が再びアメリカ大統領に就任した場合、彼の独特な考え方や言動が国際社会に与える影響は計り知れません。国際関係アナリスト北野幸伯氏の著書『新版 日本の地政学』(育鵬社)から、トランプ氏の外交政策の根幹をなす「アメリカファースト」と「お金ファースト」という二つの特徴を深く掘り下げ、その真意と潜在的な影響について解説します。彼のこれまでの大統領としての経験から、その行動パターンは予測可能です。
「アメリカファースト」の徹底追求
トランプ氏が掲げる「アメリカファースト」というスローガンは、彼が世界ではなく「アメリカのためだけ」に動くという明確な意思を表しています。これは単なる愛国主義に留まらず、すべての外交政策や国際関係において、アメリカの国益を最優先し、それ以外の要素を二の次にするという徹底した姿勢を意味します。国際的な合意や同盟関係も、最終的にはアメリカにとっての「利益」がなければ再考の対象となり得ます。
「損得勘定」に基づく「お金ファースト」外交の真意
トランプ氏のもう一つの際立った特徴は、「お金ファースト」とも表現できるほどの「儲かるか、儲からないか」という損得勘定への強いこだわりです。これは、彼のビジネスマンとしての背景が色濃く反映されており、外交や軍事同盟も例外ではありません。
世界最大の軍事同盟であるNATOを例に考えてみましょう。歴代のアメリカ大統領にとって、32カ国からなるNATOは、アメリカの国際的な影響力を示す最大の「資産」でした。アメリカはこの巨大な軍事同盟の盟主として、イギリス、フランス、ドイツといった大国を含む同盟国を率いてきました。しかし、トランプ氏の視点から見ると、NATOは「負債」として映ります。
 ドナルド・トランプ元米大統領が演説中に、自身の外交政策理念について語る様子。
ドナルド・トランプ元米大統領が演説中に、自身の外交政策理念について語る様子。
彼がそう考える理由は、「強いアメリカが自腹を切って、残りの弱い31カ国を守っている」という認識にあります。つまり、同盟国を守るためにアメリカから多大な費用が流出している状況を「損」と捉え、「負債」と見なしているのです。「金を支払って、なおかつ相手を守るのは理不尽だ。通常、守ってもらう側が、守ってくれる警備会社にお金を支払うのが道理だろう」という彼の論理は、ビジネスにおけるコストとリターンを重視する考え方に基づいています。
この「お金ファースト」の考えから、トランプ氏は他のNATO加盟国に対し、防衛費をGDP比で5%まで引き上げるよう要求しています。これは日本に置き換えると、現在の約8兆円の防衛費を約30兆円へと3.75倍にまで大幅に引き上げなければならないことを意味します。このような要求は「かなり無茶」に聞こえますが、トランプ氏にとっては「守って欲しければ、相応の費用を支払え」という至ってシンプルなメッセージなのです。
「お金ファースト」の理念を持つトランプ氏が、その経済観念を示す表情。
まとめ
ドナルド・トランプ氏の「アメリカファースト」と「お金ファースト」という二つの外交原則は、彼が再び大統領に就任した場合、国際関係に深刻な影響を及ぼす可能性があります。同盟国は、これまでの安全保障の枠組みが大きく変動する可能性に直面し、防衛費の増額や新たな役割分担を迫られることになるでしょう。彼の損得勘定に基づく外交は、既存の国際秩序や多国間協調のあり方を根本から問い直すものとなります。
出典:北野幸伯 著『新版 日本の地政学』(育鵬社)より一部抜粋・再編集