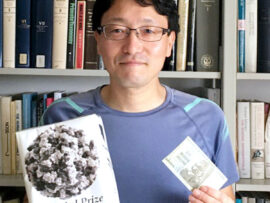岩手県盛岡市に位置する三ツ石神社は、境内に祀られた巨大な三つの岩と、そこに刻まれた「鬼の手形」と呼ばれる奇妙な痕跡で知られています。人間のものとは思えないほど大きな手形が残るこの巨石の謎を辿ると、地域に語り継がれる興味深い説話が浮かび上がってきます。この記事では、三ツ石神社の伝説を通して、日本文化における「鬼」の存在とその変遷に迫ります。

盛岡市名須川町にある三ツ石神社の境内。鬼が縛られたと伝わる三つの巨大な岩『三ツ石様』が鎮座し、その神秘的な雰囲気を伝えている。
日本書紀にも登場する「鬼」の概念とは?
「鬼」と聞いて、多くの日本人は角を生やし金棒を持つ大男の姿を思い浮かべるでしょう。節分の「鬼は外」や、子どもの遊び「鬼ごっこ」など、鬼は私たちの日常生活に深く根ざした存在です。「心を鬼にして」「鬼のいぬ間に」といった慣用句も当然のように使われています。しかし、そもそも鬼とは何なのでしょうか。
鬼は意外にも古くから存在が知られており、最古の記録としては『日本書紀』にその記述が見られます。斉明7年(661年)、斉明天皇が百済救援のために筑紫地方(現在の福岡県)に出陣し崩御した際、鬼が出現したと記されており、これが現存する史料において鬼が初めて登場するシーンとされています。太古の日本では、海外から渡来した異邦人や、地域を荒らす海賊、山賊の類いが「鬼」として伝承されたケースも散見されます。かつては得体の知れない存在や、恐怖の対象を示す言葉として「鬼」が用いられ、時代と共に怨霊や怪物、妖怪の一種として説話の中で扱われるようになったと考えられています。また、鬼の字が使われた人名や地名も多く、日本文化の形成において「鬼」が大きな存在感を発揮してきたことを示しています。
鎖で縛られた巨石「三ツ石様」と羅刹の伝説
鬼の考察を試みる上で興味深い場所が、岩手県盛岡市名須川町にある三ツ石神社です。この神社は決して大規模ではありませんが、境内にはその名の通り、巨大な岩が三つ祀られており、強烈なインパクトを放っています。苔むしたこれらの巨石は「三ツ石様」と呼ばれ、古くから信仰対象とされてきました。住宅地の中にあって、荘厳で神秘的な存在感を醸し出しています。
よく見ると、この巨石には太い鎖が巻き付けられています。これはかつて、鬼を縛り付けるために使われた鎖を再現したものと伝えられています。伝承によれば、この地域では遠い昔、「羅刹(らせつ)」という鬼が悪行の限りを尽くし、村人を苦しめていました。困り果てた村人たちが「三ツ石様、羅刹をこらしめてください」と藁にもすがる思いで願をかけたところ、羅刹はたちまちこの巨大な石に縛り付けられてしまったといいます。身動きが取れなくなった羅刹は観念し、二度と悪さをしないことを村人たちに誓い、許しを請いました。ちなみに、この地方には「不来方(こずかた)」という別称がありますが、これは羅刹が二度とこの地へは来ないと誓ったことに由来するという説があります。
三ツ石神社に伝わる鬼の手形と羅刹の物語は、単なる民話に留まらず、日本における鬼の概念がどのように人々の生活や信仰、さらには地名にまで影響を与えてきたかを雄弁に物語っています。三ツ石神社の伝説は、日本文化が育んできた鬼という存在の奥深さと、それが地域社会に与えた影響を今に伝える貴重な事例と言えるでしょう。
参考文献
- 友清哲「【驚きの写真】鬼が縛り付けられた岩?盛岡「三ツ石神社」に残る鬼の手形を追うと、「鬼」の起源がみえてきた」(Yahoo!ニュース / DIAMOND online 2024年8月3日掲載)