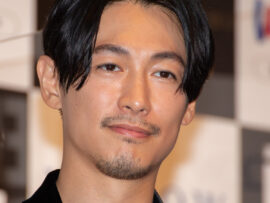太平洋戦争ではアメリカやイギリスとの戦いが主に語られますが、開戦当初、日本軍はオランダ領インドネシアのオランダ軍(蘭印軍)とも交戦し、制圧しました。日本軍は多数のオランダ人を抑留しましたが、日本の敗戦後、今度は日本兵がオランダ人により抑留されるという逆転の歴史が展開します。林英一氏著『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』に基づき、知られざるその過酷な実態に迫ります。
 日本軍がジャワ島に上陸。オランダ領東インド進攻の歴史的瞬間(1942年)。
日本軍がジャワ島に上陸。オランダ領東インド進攻の歴史的瞬間(1942年)。
ジャワ島に残された日本兵:抑留の歴史的背景
16世紀初頭に始まったヨーロッパ勢力による東南アジアへの進出は、交易独占を目的とした「点と線の支配」から、植民地を開発する「面の支配」へと変貌を遂げ、第一次世界大戦の頃までにはタイ以外の東南アジア全域が欧米列強の植民地となっていました。
このうちインドネシアでは、1830年にオランダ植民地政庁が住民の一部にコーヒー、サトウキビ、藍などの特定作物の栽培を義務づけ、その加工製品の独占的輸出で莫大な利益を上げました。その後、各地の小王国を次々と統治下に治め、オランダ領東インドが誕生しました。
その一方で、ジャワ島中部の農村で大規模な飢饉が起こるなど、農民たちは重い負担を強いられました。20世紀に入ると、オランダ世論の批判もあり、オランダ政庁は住民の福祉向上、キリスト教布教、権力分散を骨子とする「倫理政策」に転じます。この後、民族意識に目覚めた住民の間で民族主義運動が広がりますが、1934年に独立運動の指導者スカルノとモハマッド・ハッタが流刑に処されるなど、オランダ当局に抑圧されていました。
 南方抑留の地理的範囲を示す関連地図。『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』より。
南方抑留の地理的範囲を示す関連地図。『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』より。
日本軍の進出とインドネシアの地位変遷
そのような独立運動の停滞期に到来した日本軍は、1942年3月12日にスマトラ島北端のアチェに無血上陸を果たすなど、当初は解放者として住民に歓迎されました。しかし、1943年5月の「大東亜政略指導大綱」では「『マライ』『スマトラ』『ジヤワ』『ボルネオ』『セレベス』ハ帝国領土ト決定シ重要資源ノ供給源トシテ極力之ガ開発並ニ民心ノ把握ニ努ム」とされ、日本はインドネシアの独立を認めず、帝国領土に編入しました。
その後、戦局が悪化すると、翌年8月19日の最高戦争指導会議の「今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」で「将来東印度ヲ独立セシムルコトヲ成ル可ク速カニ宣明ス」として、将来の「独立」を許容する方針へと転換しました。
太平洋戦争下のインドネシアにおける、日本とオランダ間の複雑な抑留史。日本軍の支配から一転、敗戦後は日本兵がオランダ人によって抑留されるという運命の逆転がありました。林英一氏の著書が明らかにするこの「もう一つの悲劇」は、戦争の多面性と人間の運命の不確かさを現代に問いかける、重要な歴史的教訓と言えるでしょう。
参考文献
- 林英一 著, 『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』, 新潮選書, 新潮社
- Yahoo!ニュース (本記事の参照元記事)