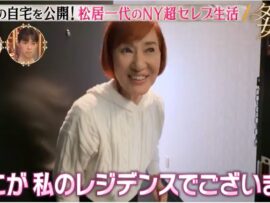都市部の道路や信号待ちで、バイクが自動車の列の間を縫うように前方へ進んでいく「すり抜け」を目にすることは少なくありません。その機動性の高さから、渋滞時に先頭へ出るための効率的な手段と捉えるライダーもいるでしょう。しかし、この「すり抜け」という行為は、日本の道路交通法においてどのように位置づけられているのでしょうか。果たして、法的な違反行為にあたるのか、多くのドライバーやライダーが疑問に感じているテーマです。
道路交通法は「すり抜け」行為自体を直接禁止していない
バイクはそのコンパクトな車体と優れた加速性能を活かし、都市部の移動や狭い道路での走行において大きな強みを発揮します。特に、交差点や片側複数車線の道路で停車中の自動車の隙間を縫うように進み、停止線付近まで出る光景は、日常的に見られるものです。このような走行スタイルは、バイクならではの機動性を象徴するものとも言えます。
一般的に「すり抜け」は危険な運転行為として批判的に見られがちですが、実は日本の道路交通法には「すり抜け」という行為そのものを直接的に禁止する明確な条文は存在しません。これが、「すり抜け」行為が厳密には違反ではないとされる主な理由です。
 交通量の多い市街地で、車列の間をすり抜けるバイク。事故のリスクを伴う運転行為の例。
交通量の多い市街地で、車列の間をすり抜けるバイク。事故のリスクを伴う運転行為の例。
「すり抜け」が法に触れる可能性のある具体的なケース
「すり抜け」行為自体は直接禁止されていませんが、その状況や方法によっては、道路交通法に定められた他の条項に抵触し、違反と判断される可能性があります。ライダーは以下の点を十分に認識しておく必要があります。
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条):車両の運転者は、安全運転に必要な注意を怠ってはなりません。すり抜けによって歩行者と接触したり、周囲の車両に危険を及ぼしたりした場合、この義務に違反したとみなされます。
- 車間距離保持義務違反(道路交通法第26条):前を走る車両が急ブレーキをかけた際でも追突を避けられる安全な車間距離を保つ義務があります。すり抜けの際に前車との距離が極端に近くなり、危険が生じた場合は違反となります。
- 通行区分違反:対向車線にはみ出してすり抜けを行った場合、「通行区分違反」となります。特に、センターラインが黄色の実線で描かれている区間は、「追い越しのための右側部分へのはみ出し禁止」を意味し、この場合は明確な違反です。
- 危険運転行為:無理な割り込みや、停車中の車両の間を蛇行するように走行し、他の交通の妨げになったり、著しく危険な状態を作り出したりした場合は、「危険運転」と判断され、より重い法的責任を問われる可能性があります。
 黄色の実線が引かれた道路のセンターライン。車線逸脱を伴うすり抜けは交通違反となる可能性を示す。
黄色の実線が引かれた道路のセンターライン。車線逸脱を伴うすり抜けは交通違反となる可能性を示す。
つまり、「すり抜け」という行為そのものに違反の定義はないものの、それが原因で周囲の安全を脅かしたり、他の交通ルールに違反したりした場合には、法的責任が問われることになるのです。
安全な交通社会のための「すり抜け」のあり方
「すり抜け」は、法的にはグレーゾーンに位置する行為であり、「違反ではないが、極めてリスクが高い」という認識を持つことが重要です。バイクの機動性を過信するあまり、他の交通参加者の安全を軽視した運転は許されません。
 都市部の幹線道路で、停車中の車列の間を走行するバイク。すり抜けの危険性とライダーの注意喚起。
都市部の幹線道路で、停車中の車列の間を走行するバイク。すり抜けの危険性とライダーの注意喚起。
交通の流れや周囲の状況を常に正確に読み取り、自動車や歩行者、自転車への十分な配慮を怠らないことが、安全運転の基本です。ライダーには、自らの行動が引き起こす可能性のある危険性を十分に理解し、常に慎重な判断が求められます。
「すり抜け」が日常的に行われる行為であるからこそ、その法的な解釈と潜在的な危険性を正しく理解し、安全な交通社会の実現に向けた一人ひとりの責任ある運転が不可欠です。