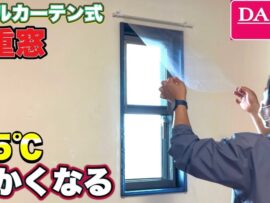豊臣秀吉の天下統一を語る上で、彼の才能ある弟、豊臣秀長の存在は欠かせません。秀長は単なる軍事の補佐役に留まらず、豊臣政権の安定と発展に不可欠な政治的・外交的役割を果たし、兄秀吉が最も信頼を置く肉親として、天下統一事業に絶大な貢献をしました。本稿では、秀長が果たした具体的な役割とその真価を深掘りします。
天下統一を支えた「調整役」としての秀長の役割
豊臣秀長が天下統一において果たした貢献は、合戦における軍事指揮や戦後処理に限定されるものではありませんでした。彼は服属した諸大名に対する接待役、そして秀吉と大名間の調整役を務めることで、豊臣政権の基盤を安定させ、ひいては天下統一を盤石なものにしました。弟としての立場を最大限に活かし、秀吉と諸大名との間に立ち、反旗を翻すことのないよう良好な関係の構築に尽力したのです。特に毛利氏や徳川家康に対するスタンスは顕著でした。
本能寺の変を境に、秀吉と毛利氏はそれまでの敵対関係から一転、協力関係へと移行します。秀吉が天下人への道を駆け上がれたのは、服属させた毛利氏との関係を円滑に維持できたことが大きく、紀州攻め以降、毛利氏は秀吉勢として積極的に軍事行動に参加し、その勝利に貢献しています。
天正13年(1585年)の紀州攻めで水軍を派遣したのに続き、四国攻めでは3万〜4万もの大軍を参戦させました。この時の毛利勢を率いたのは小早川隆景と吉川元長であり、両人は総大将を務める秀長と密接に連絡を取り合いながら、連携して軍を展開しました。この四国攻めを通じて、秀長と毛利氏の関係が深く強固になったことは想像に難くありません。
四国攻めの論功行賞で隆景は伊予を与えられましたが、その際には毛利氏が秀吉から拝領した上で、改めて主家である毛利氏から与えられるという形が取られました。これは隆景が毛利氏への恩賞という形式にこだわったためであり、秀長が秀吉との間に立ってその調整役を務めたと考えられています。
 豊臣秀長像:豊臣秀吉の天下統一を支えた補佐役の姿
豊臣秀長像:豊臣秀吉の天下統一を支えた補佐役の姿
毛利氏・長宗我部氏との「信頼関係構築」の要
同年12月には、毛利氏を代表する隆景とその兄である吉川元春が大坂へと赴きました。これは毛利氏が伊予を拝領したことに対する御礼を申し述べるための来訪でした。当主輝元を補佐する二人の叔父は、毛利氏との良好な関係を維持するためのキーパーソンであり、秀吉は彼らを盛大に歓待しました。その秀吉の意を受けて二人の接待に当たったのは秀長であり、四国攻めでの経緯を考慮すれば、彼が適任であったことは明らかです。
秀長は茶会にも隆景と元春を招き、秀吉の側近でもある千利休を引き合わせるなど、手厚くもてなしました。さらに、天正15年(1587年)の九州攻めに毛利勢が動員された際、彼らが秀長の指揮下に入ったのも、四国攻め以来築かれた信頼関係が考慮された結果でしょう。
同16年(1588年)7月には、今度は毛利輝元が上洛してきました。この輝元の接待にあたったのもやはり秀長であり、秀吉の関白としての邸宅である聚楽第で歓待しました。京都での接待に留まらず、自身の居城である大和郡山城にも輝元を招き、茶会などを催して手厚くもてなしています。これは毛利氏との関係をさらに強化したいという秀吉の強い意図が反映されたものでした。輝元もこれに返礼として、秀長に加えて当時在京中であった織田信雄や徳川家康をもてなしています。
秀長は四国攻めで降伏させた長宗我部氏との関係強化にも尽力しました。当主である長宗我部元親が秀吉に謁見するため上洛した際には、秀長がその仲介役を務め、両者の円滑な対面を実現させました。

服属交渉から伝令まで:島津氏との複雑な関係
このように、秀長は秀吉と服属した諸大名を繋ぐ要の役割を果たしました。諸大名が秀吉に拝謁するため上洛してくると、彼は単なる接待役としてだけでなく、秀吉との間に立って調整役も務めたのです。秀吉の代理、つまり名代として四国攻めの総大将を務めたことに象徴されるように、秀吉が最も信頼を置く肉親であったからこそ、その効果は計り知れないほど大きかったと言えるでしょう。
一方で毛利氏や長宗我部氏からすれば、秀長を通じて自家の安泰を図りたいという思惑がありました。両氏に限らず、秀吉に服属した諸大名は、秀吉との調整役を務める秀長を大いに頼りにし、彼との関係を重視しました。
このように、秀長は秀吉と諸大名の関係を取り持つ役割を担いましたが、これは服属後だけに限ったことではありません。秀吉に服属する前から、両者の間に立ち、交渉にあたっていました。
九州攻めは、島津氏が秀吉の停戦命令に背いて大友氏との戦いを再開したことが引き金となりましたが、その前から秀長は島津氏との交渉役を務めていました。四国攻め最中の天正13年(1585年)7月、秀吉は関白に就任します。その年の10月には、交戦中であった島津・大友両氏に対して、関白という権威を盾に停戦を命じました。しかし、その公式な命令が届く前に、秀長(あるいは秀長の家臣)は秀吉の関白就任を島津氏に伝えていたのです。それを知った当主義久が秀長に送った書状が現在も残されており、秀長がいかに早くから外交的な役割を担っていたかを示しています。
結論:天下統一に不可欠だった「政治家」秀長
豊臣秀長は、豊臣秀吉の単なる軍事の補佐役ではなく、政権の外交・調整を担う「政治家」としての才能を存分に発揮しました。彼は秀吉が最も信頼する肉親として、服属した大名との間に良好な関係を築き、紛争を未然に防ぎ、あるいは解決へと導きました。秀長の存在がなければ、豊臣政権の天下統一はこれほど円滑に進まず、あるいは成し遂げられなかったかもしれません。彼の多岐にわたる貢献は、豊臣政権の安定と日本の統一に不可欠なものであったと言えるでしょう。
参考資料
- 安藤優一郎『日本史のなかの兄弟たち』(中公新書ラクレ)
- Yahoo!ニュース: 豊臣秀吉の弟、秀長はどんな人物だったのか。歴史家の安藤優一郎さんは「軍事面だけでなく政治面でも兄を支え、天下統一に貢献した。間違いなく秀吉が最も信頼する肉親だった」という――。(第1回) (https://news.yahoo.co.jp/articles/aa0d6b0b49fe9aed7d0e2a1ab4d3508c43f8a734)