まんが甲子園、正式名称「全国高等学校漫画選手権大会」で、異例の事態が発生しました。第34回大会の最優秀賞作品が、発表後に類似作品の存在が確認され失格、「該当なし」という結果に。主催者はこの事態を重く受け止め、「誹謗中傷は絶対にしないで」と異例の呼びかけを行いました。知的財産権に詳しい舟橋和宏弁護士は、この問題に対し落ち着いた対応の必要性を訴えています。
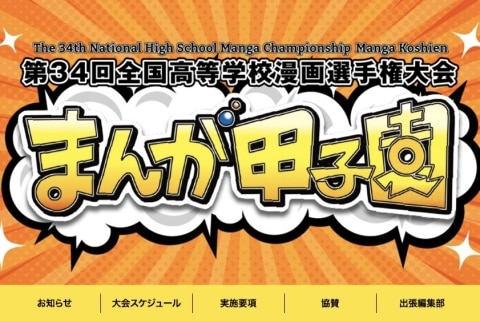 第34回まんが甲子園のロゴと開催概要を示す大会公式ポスター。若き漫画家たちの才能が集う全国高等学校漫画選手権大会の象徴。
第34回まんが甲子園のロゴと開催概要を示す大会公式ポスター。若き漫画家たちの才能が集う全国高等学校漫画選手権大会の象徴。
まんが甲子園 最優秀賞失格の衝撃と主催者の対応
今年の「まんが甲子園」で最優秀賞作品が失格となり、波紋を広げています。主催者は、類似作品の存在を確認し、大会の実施要綱の「第三者の著作権…等の権利を侵害しないよう注意すること」という規定に反すると判断。主催者は「規定に抵触する作品を審査対象から除外できなかったこと」を深く反省すると表明。SNS上での「パクリ」指摘に対し、「誹謗中傷を絶対しないで」と強く呼びかけました。
 まんが甲子園主催者によるSNS上の誹謗中傷に対する注意喚起のメッセージ。大会の信頼性を守り、健全な議論を促す重要性を示す。
まんが甲子園主催者によるSNS上の誹謗中傷に対する注意喚起のメッセージ。大会の信頼性を守り、健全な議論を促す重要性を示す。
著作権侵害の法的判断基準:弁護士が解説する「依拠性」と「類似性」
今回の失格問題で注目されるのが、著作権侵害の判断基準です。知的財産権に詳しい舟橋和宏弁護士は、著作権侵害の判断には「依拠性」と「類似性」の二要素が必要と指摘します。
「依拠性」は、既存の作品をもとに作成したか否かを指します。偶然似てしまっただけであれば成立しませんが、比較対象が非常に有名であったり、類似の程度が強い場合には、事実上、依拠性が推認されることもあります。
「類似性」は単に見た目が似ているかどうかで判断されるものではありません。アイデアやテーマ設定といった抽象的な部分が似ていても著作権侵害とはみなされず、著作物の本質的特徴が似ているかで判断されます。マンガの場合、具体的な構図、コマ割り、キャラクターのセリフ、ストーリーの展開など、表現の細部を比較して判断されることになります。SNSで指摘された失格作品については、起承転結の展開など具体的な表現に共通点が多いとされ、事務局は実施要綱に反すると判断したとみられます。
ネット上の指摘と事務局の最終判断
SNS上で指摘されている失格作品と類似作品の内容を総合的に考慮すると、具体的な表現における共通点が多数存在したことが伺えます。舟橋弁護士の解説に照らせば、事務局はこれらの共通点から「依拠性」を推認し、「オリジナル未発表作品」という実施要綱の条件に反すると判断したと考えられます。表現の一部に相違点があったとしても、全体としての類似性や創作過程における疑義が、最終的な失格決定につながったとみられます。この一件は、創作活動におけるオリジナリティの重要性を改めて浮き彫りにしました。
まんが甲子園での異例の失格は、創作における著作権の重要性と、オリジナル性の追求の不可欠さを浮き彫りにしました。同時に、SNSでの「パクリ」指摘に対する主催者の「誹謗中傷禁止」の呼びかけは、情報社会における責任ある言動の重要性を示唆します。本件は、創作活動の法的側面と社会倫理の両面から、私たちに大切な教訓を与えています。
参照元: Yahoo!ニュース






