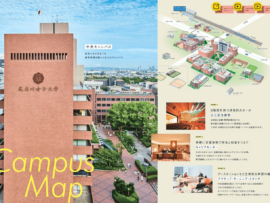人生の終焉を迎えるにあたり、「どのように死を迎えたいか」という問いは、多くの人にとって深く、時に避けたいテーマかもしれません。しかし、外科医であり在宅医療医として数々の人々の最期を見届けてきた久坂部羊氏によれば、延命治療や世に溢れるきれい事に惑わされると、「上手な死」を迎えることはかえって難しくなるといいます。本稿では、久坂部氏が提唱する「上手な死」の概念と、それを実現するための条件について深掘りします。
「幸福な死」とは何か?納得感と充足感のある最期
SBクリエイティブ社が実施した「死の恐怖の理由」に関するアンケートでは、「この世でやり残したことがなく、周囲ともきちんとお別れの挨拶ができていれば、納得感のある死になる」という回答がありました。「幸福な死」とは、まさにこの「納得感のある死」と言い換えられるでしょう。それは、痛みや苦しみがなく、思い残すことや後顧の憂いもなく、満ち足りた気持ちで迎える最期を意味します。
あるいは、何も知らないうちに突然訪れる「突然死」も、恐怖や嘆き、後悔を感じる間がないため、当人にとっては「幸福な死」と言えるかもしれません。夜、暖かい布団の中で体を伸ばし、安堵の息を吐きながらそのまま眠りに落ちて死ねたなら、これほど楽な死はないと久坂部氏は語ります。満ち足りた気持ちで眠りに向かう心地よさは何物にも代えがたいものですが、この満ち足りた気持ちは自分自身で作り出すものであり、どんなに偉い人や大金持ち、美人であっても、常に何かを得たいと願う人には手の届きにくい境地です。要は心の持ちようですが、現実にはこの「幸福な死」を迎えることは容易ではありません。
たった一度きりの「死」を上手に迎えるための条件と医療の役割
近年、久坂部氏には「上手な最期の迎え方」に関する講演依頼が増えているといいます。誰もが死ぬことは避けられないとしても、人生の最後に苦しんだり、辛い思いはしたくないという切実な願いがあるからです。
久坂部氏の結論は明確です。「上手な死」とは、余計な医療を受けず、比較的楽に迎える自然な死のことです。対して、「下手な死」とは、無駄な医療を施され、不必要な苦しみを味わいながら尊厳のない状態で死ぬことを指します。
現実には、多くの人が「下手な死に方」をしてしまいます。それは、「病院に行けば何か有効な治療があるのではないか」「苦しみを減らしてもらえるのではないか」「自宅で看取るのは不安だから専門家に任せたい」といった期待や不安から来るものです。しかし、人が死にゆく段階において、医療はしばしば無力であり、むしろ過剰な医療が有害となることさえあります。臨終間際に行われる医療のほとんどは、家族を納得させるためのパフォーマンスに過ぎないと久坂部氏は指摘します。
死ぬ時に苦しみたくないという気持ちは理解できますが、人間もまた生き物である以上、死ぬ際に多少の苦しみを伴うのは致し方ないことです。その苦しみをゼロにしようと病院に頼りすぎると、余計な医療を受け、場合によっては悲惨な延命治療に繋がってしまう可能性があります。人生で一度きりの「死」という経験を、そのような形で「下手」に迎えてしまうのは、実にもったいないことだと言えるでしょう。
 暖かい光の中で人生の最期を考える高齢者の手元
暖かい光の中で人生の最期を考える高齢者の手元
「死ぬ時はある程度苦しい、それは仕方がない」と心にしっかり準備ができていれば、実際にその時を迎えた際に「思ったほどではなかった」と安堵できるかもしれません。頑なに苦痛を拒絶するのではなく、腹を括っておくことこそが、「上手な死」を迎えるための鍵となるのです。読者の中には、実行が難しいと感じる方もいるかもしれませんが、世の中に溢れる「きれい事」の情報や幻想に惑わされず、しっかりと真実を知れば、自宅で自然な死を迎えることは決して難しいことではないと久坂部氏は強調します。
私たちは死をタブー視しがちですが、久坂部羊氏の提言は、死を人生の自然な一部として捉え、能動的にその迎え方を考えることの重要性を示唆しています。過剰な医療に頼るのではなく、真実を受け入れ、心の準備をすることで、後悔のない、納得感のある最期を迎えることができるのかもしれません。