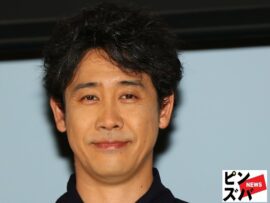近年、発達障害の診断を受ける子どもたちが増加しているという報告が多く聞かれます。この現象は、単に「発達障害を持つ人が増えた」ことを意味するのでしょうか?それとも、背後にはより複雑な要因が潜んでいるのでしょうか?本記事では、30年以上にわたり発達障害を専門としてきた児童精神科医であり、信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授の本田秀夫氏の見解を基に、この診断増加の背景にある社会的な変化と真の理由に迫ります。
発達障害とは何か?専門家による定義
発達障害とは、一体どのような特性を指すのでしょうか。本田秀夫氏によると、「生まれつき脳神経系に普通の人とは違う何らかの特徴があるために、人生のどこかで生活に支障が出ること」と定義されます。この定義の重要な点は、単に脳の特性があるだけでなく、その特性が日常生活、学業、または社会生活において困難や支障を引き起こしている場合に診断が下されるという点です。つまり、個々の脳の特性と、それが生活に及ぼす影響の両方が考慮されます。
多様性を持つ発達障害の種類と特性
発達障害と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。代表的なものには、対人関係やコミュニケーションの困難、特定の興味への強いこだわりなどが特徴的な自閉症スペクトラム症(ASD)、不注意、多動性、衝動性などが特徴的な注意欠如多動症(ADHD)、そして読み書きや計算など特定の学習能力に困難が見られる学習障害(LD)などがあります。
これらの障害は、それぞれ異なる特性を持つだけでなく、個人差も非常に大きいのが特徴です。本田氏が指摘するように、「どれか1つの障害の特性が見られることもあれば、複数の特性が重複して見られることもあり、その程度も人それぞれ」です。また、知的障害を伴う場合もあれば、知的な発達に遅れがない場合もあります。この多様性が、発達障害の理解を難しくする一方で、個々のニーズに応じたきめ細やかな支援の重要性を示しています。

統計データが示す診断数の増加傾向
実際のデータは、発達障害の診断数が増加していることを裏付けています。文部科学省の特別支援教育資料(2023年度)によると、公立小学校で通級指導(通常の学級に在籍しながら、必要に応じて特別教室で指導を受ける制度)を受ける注意欠如多動症(ADHD)の児童数は、2019年度の2万626人から2023年度には3万4654人へと顕著に増加しています。同様に、自閉症スペクトラム症や学習障害を持つ児童数も増加傾向にあると考えられています。この統計は、社会全体で発達障害への関心が高まり、診断と支援の機会が増えている現状を明確に示しています。
「本当に増えた」のか?専門家が語る背景
このような診断数の増加を見ると、「本当に発達障害を持つ子どもが増えたのではないか?」と考える人もいるかもしれません。しかし、本田氏はこの一般的な認識に対し、異なる見解を示しています。「昔ながらの遊びをしないから」「食品添加物や農薬が悪影響を与えている」「親の育て方が悪い」といったさまざまな説が流布していますが、これらはいずれも科学的な根拠に乏しいと本田氏は指摘します。
本田氏の結論は、「発達障害の人が本当に増えたというよりもむしろ、発達障害と診断される人が増えたと考えられる」というものです。この「診断される人が増えた」背景には、主に「診断概念が広くなったため」という要因があります。過去には見過ごされがちだった軽度な特性や、他の精神疾患と混同されていたケースが、現在のより詳細で広範な診断基準によって明確に認識されるようになったのです。また、社会全体の発達障害に対する認知度の向上や、早期発見・早期支援の重要性が認識され始めたことも、診断数増加の大きな要因として挙げられます。
変化する社会と発達障害への理解
発達障害の診断数増加は、単純な「増加」ではなく、社会の発達障害に対する理解度と診断技術の進歩を反映したものです。これは、私たちがこれまで見過ごしてきた多様な脳の特性を持つ人々への認識が深まり、適切な支援へと繋がる重要なステップと言えるでしょう。今後も、根拠のない情報に惑わされることなく、科学的知見に基づいた正確な理解を深め、発達障害を持つ人々が社会で生きやすい環境を築いていくことが求められます。
参考文献
- Yahoo!ニュース
- 東洋経済オンライン