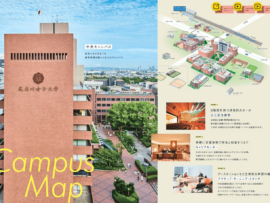日中戦争において、旧日本軍が現地の子ども、女性、高齢者といった非戦闘員に対し、残虐な行為を行ったとされています。一体なぜ、日本兵たちはそのような“蛮行”に走ってしまったのでしょうか。本稿では、禁固刑を受けた旧日本軍の軍人を取材したノンフィクション作家・保阪正康氏の著書『昭和陸軍の研究 上』(朝日文庫)より、元中尉である鵜野晋太郎氏の証言を基に、その背景に迫ります。
組織的放置が招いた蛮行の深化
戦後、自らの心境を記す「懺悔録」の作成を命じられた戦犯たちの中に、文字を書くことができない下級兵士がいました。彼は政治将校の問いかけに対し、突然土下座して泣き崩れ、西日本の貧しい山村で生まれ、小学校にも通えなかった自身の生い立ちを告白します。政治将校から「泣くな。おまえのせいではない。社会制度の犠牲者だ」と慰められると、その兵士は中国での自らの行為の一部始終を語り始めました。放火、略奪、そして強姦――数えきれないほどの蛮行が次々と告白され、傍らで聞いていた他の戦犯たちは、生気を失い、ただうつむくばかりでした。
「私は国を恨んでいたのです。私は家の働き手でしたが、私が徴兵されたために家族はどうすることもできませんでした。私が徴兵されてまもなく、妹は女郎に売られて家をでていったそうです」。この下級兵士の告白は、当時の日本の貧困と、兵士個人が抱えていた深い苦悩を浮き彫りにします。

 日中戦争の時代背景を示す日本兵のイメージ
日中戦争の時代背景を示す日本兵のイメージ
個人と組織:蛮行の背景にある社会構造
この告白を聞いた鵜野中尉は、日本軍の蛮行には、日本国内で厳しい下積み生活を強いられていた者が、その鬱憤晴らしとして、何の統制も受けずに好き勝手をしたという側面があることを痛感します。そして、将校たちがそうした行為を全く制止しなかったところに、旧日本軍の決定的な過ちがあったと認識しました。むしろ軍は、これらの残虐行為を放置しながら、「聖戦」という名目で戦争を推し進めていたのです。
この証言は、個人の苦しみと、それを許容し、時に助長した組織的な問題が複雑に絡み合って、非人道的な行為へと繋がったことを示唆しています。貧困や教育の欠如といった社会制度の犠牲者が、戦場でその鬱憤を晴らす場が与えられ、しかも軍上層部がそれを黙認するという構造が、蛮行を常態化させたと考えられます。
結論
日中戦争における旧日本軍の残虐行為は、単なる一部兵士の逸脱行為ではなく、当時の日本の社会背景、個人の絶望、そして軍組織全体の統制の欠如と黙認が複合的に作用して引き起こされたものでした。下級兵士が抱えた国への恨みや家族の悲劇は、彼らが戦場で何の歯止めもなく蛮行に走る一因となったことを、鵜野中尉の証言は明確に伝えています。この痛ましい歴史の真実に目を向け、その背景を深く理解することは、同様の過ちを繰り返さないために極めて重要です。なお、中国側は、合計1100人余りの日本人戦犯の大半を起訴猶予とし、昭和30年から31年にかけて日本へ帰国させました。
参考文献
- 保阪正康『昭和陸軍の研究 上』(朝日文庫)