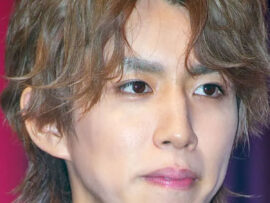江戸幕府十代将軍・家治の時代に絶大な権勢を誇った田沼意次。彼がなぜ突然その政治生命を断たれてしまったのか、その背景には、次期将軍の時代においても幕政の実権を握れるという意次の読み違いと、予期せぬ人物による裏切りがあったと歴史家は指摘します。特に、あまり知られていない弟・意誠の存在が、意次の権勢維持において重要な役割を果たしていたことが明らかになっています。
 江戸時代の政治家をイメージさせる風景
江戸時代の政治家をイメージさせる風景
権勢を誇った田沼意次、その失脚の引き金
田沼意次は、九代将軍家重の側近から幕府の要職に駆け上がり、その経済政策や幕政改革で「田沼時代」を築き上げました。しかし、家治の死後、次の将軍の時代に入っても自身の政治的影響力を維持できると過信していたと、歴史家の安藤優一郎氏は著書『日本史のなかの兄弟たち』の中で分析しています。意次の失脚は、単なる政策の失敗だけでなく、こうした未来への誤算と、意外な人物による「裏切り」が絡み合っていたとされています。
将軍側近としての兄・意次と弟・意誠の異なる道
将軍の側用人として幕府のトップに登り詰めた田沼意次に対し、2歳年下の弟・意誠(おきのぶ)は異なる道を歩んでいました。意次が次期将軍・家重の小姓として出仕した一方で、意誠は家重の弟である宗尹(むねただ)の小姓として召し抱えられました。元文元年(1736年)には蔵米三百俵を与えられています。
延享2年(1745年)に家重が九代将軍に就任すると、翌年には宗武(むねたけ)と宗尹がそれぞれ田安徳川家と一橋徳川家を創設し、十万石の大名に取り立てられました。意誠は一橋家初代当主となった宗尹にそのまま仕え、宝暦9年(1759年)には側用人から家老に昇進。禄高も五百石に加増され、明和7年(1770年)には八百石にまでなりました。意誠はその後も十数年にわたり一橋家の家老職を務め続けます。
意誠が一橋家家老に進んだ頃、兄の意次は既に御側御用取次として、幕府の影の実力者となっていました。各方面から意次の政治力への期待が高まり、その影響力を通じた働きかけが頻繁に行われるようになります。この裏では多額の金品が動くこともありましたが、意次やその家臣への直接的なアプローチだけでなく、意誠を介して意次への接触を試みるケースも少なくありませんでした。結果として、意誠もまた、隠然たる政治力を持つ存在となっていったのです。
薩摩藩・仙台藩に見る田沼意誠の「仲介役」としての力
田沼意誠が兄・意次の「窓口」としていかに重宝されたかを示す具体的な事例が、歴史の中に残されています。
宝暦12年(1762年)、江戸藩邸の焼失に見舞われた薩摩藩では、その再建費用に頭を悩ませていました。そこで藩主島津重豪(しげひで)と一橋宗尹の娘・保姫(やすひめ)との縁組に着目し、姻戚関係となる一橋家の家老を務める意誠を介して、幕府からの援助を意次に働きかけることに成功します。その結果、薩摩藩は3000両の下賜金と2万両の拝借金を幕府から引き出すことができました。薩摩藩にとって、この交渉の窓口となった意誠の存在は極めて大きかったと言えるでしょう。
また、明和2年(1765年)6月からは、仙台藩主伊達重村(しげむら)の側役・古田良智(よしとも)が、主君の近衛少将から中将への昇進を強く望み、幕府への裏工作を開始しました。当時、大名や旗本の朝廷からの官位は幕府が決定権を持っていたため、要人への働きかけは熾烈を極めていました。伊達家が目を付けたのは、老中首座の松平武元(たけちか)と御側御用取次の意次であり、両名を味方にすれば昇進は確実と考えていました。古田は松平武元の用人・宮川古仲太と意次の用人・井上寛司に対面し、主君の希望を伝えます。この時、井上との対面を仲介したのが意誠でした。伊達家の件においても、意誠が重要な窓口となっていたことが分かります。意次たちへの巧みな工作の結果、同4年12月、重村は念願の近衛中将に昇進を果たしました。
結論:政治的誤算と兄弟の絆が織りなす失脚劇
田沼意次の失脚は、単に彼の政治手腕の限界を示すものではありませんでした。次期将軍の時代における自身の権力基盤の誤読、そしてその後の「思わぬ人物の裏切り」が、彼の政治生命を完全に断ち切る決定打となったのです。同時に、弟・意誠が兄・意次の政治活動の裏で、いかに重要な仲介役として機能し、多くの大名家との関係構築に貢献していたかという事実は、田沼時代の政治構造の複雑さと、表舞台に立たない人物の隠れた影響力を浮き彫りにします。意次の失脚劇は、こうした政治的誤算と、知られざる兄弟の絆、そして権力闘争の深層が複雑に絡み合った結果と言えるでしょう。
参考文献
- 安藤優一郎『日本史のなかの兄弟たち』(中公新書ラクレ)