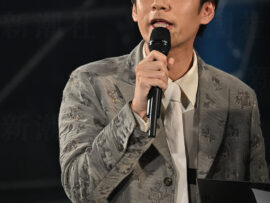今年、広島と長崎は原爆投下から80年という節目を迎えました。被爆地の切なる核兵器廃絶の願いとは裏腹に、国際社会は今、核を巡る深刻な緊張に直面しています。世界の安全保障環境が大きく変化する中、核抑止の概念や各国の防衛政策が改めて問われています。
 戦後80年を迎え、核廃絶への願いと世界の核情勢の複雑さを報じるニュースイメージ
戦後80年を迎え、核廃絶への願いと世界の核情勢の複雑さを報じるニュースイメージ
被爆者の声と広島県知事の警鐘
8月6日、80回目の原爆の日を迎えた広島では、14歳で被爆した94歳の男性が「80年経過したが、絶対にこの地球から、原子爆弾、核兵器はなしにしていただきたい」と、平和への強い訴えを発しました。また、8月9日の長崎では、胎内被爆を経験した94歳の男性が「平和には見えますけど、難しい時代ですね」と、現状の国際社会への複雑な思いをにじませました。
広島県の湯崎英彦知事は、平和記念式典で世界の現状に対する深い憂慮を表明しました。「広島の街は大きく変わり、平和と繁栄を謳歌しています。しかし同時に、むき出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあり、私たちは今、この繁栄が如何に脆弱なものであるかを痛感しています」と述べ、平和の尊さとその基盤の脆さを強調しました。
核兵器を巡る世界の現状と高まる緊張
実際、国際社会では核兵器を巡る動きが活発化し、緊張が高まっています。ロシアのプーチン大統領は2022年9月以来、ウクライナ侵攻に関連して核の「恫喝」とも取れる発言を繰り返し、「我々を核兵器で脅迫しようとする人々は、自分たちが同じ目に遭う可能性があると知るべきだ」と警告しています。
一方、アメリカでは、トランプ大統領が2025年8月1日に「『核』に対して、我々は備えなければならない」と発言するなど、核戦力の近代化に注力しています。特に「使える核」とも呼ばれる戦術核の開発が進められており、その動向が注目されています。
北朝鮮もまた、戦術核の開発を加速させていると報じられており、新型の駆逐艦に搭載される可能性も指摘されています。このような核開発競争の激化は、地域および世界の安全保障に新たなリスクをもたらしています。
国際社会に迫られる防衛費増額の波
核を巡る国際社会の緊張の高まりは、各国に防衛費の増額を迫っています。トランプ大統領は、NATO加盟国に対し、現在のGDP比2%という防衛費目標では不十分であり、「5%(の防衛費)が必要。2%では無理だ」と一層の増額を強く要求。これに対し、各国も合意する姿勢を見せています。
日本もこの流れとは無縁ではありません。「GDP比1%枠」が取り払われ、2027年度には「2%」とする防衛費増額目標を掲げ、急激な予算拡大が進んでいます。さらに、トランプ政権からは「3.5%」へのさらなる引き上げを要求されており、日本の防衛政策は大きな転換期を迎えています。
結論
戦後80年が経過し、核兵器廃絶への願いは依然として強いものの、現実の国際社会は核開発と防衛費増額という逆行する動きに翻弄されています。被爆者の声や各地の知事の警鐘が響く中、世界は核の脅威とどう向き合い、真の平和を構築していくのか。この歴史的な転換点において、国際社会の動向と日本の選択がますます重要となっています。