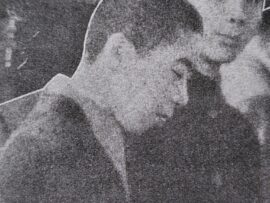元警視庁警視、成智英雄氏の著書『犯罪捜査記録 猟奇篇』(創人社)には、捜査の困難さが記されています。「犯罪の陰に性的問題が秘められていることは千古不滅の原理に違いないが、近年は想像もつかない殺人が突発し、証拠絶対主義の壁に阻まれ、捜査は難航し、迷宮入りが当然視される傾向さえ見られる」と。しかし、それを乗り越えるのは、捜査指揮官の的確な推理と、捜査員の汗と涙の集積に他なりません。昭和の時代、刑事たちは靴底をすり減らし、丹念な聞き込みと情報分析で被疑者にたどり着きました。今回ご紹介するのは、埼玉県で発生し、その犯人の「異常な人格」が社会に衝撃を与えた「一家四人殺し」事件。これは全2回にわたる第一部の記録です。
昭和の捜査:証拠の壁を越える刑事たちの足跡
現代の科学捜査とは異なり、昭和の刑事たちは「足で稼ぐ」捜査を重んじていました。緻密な聞き込み活動を通じて地域住民からのわずかな情報も逃さず、それらの断片的な情報を丹念に集約し、検討を重ねることで、事件の全体像を浮かび上がらせていきました。時に「証拠絶対主義」という法律の壁が立ちはだかり、捜査は困難を極め、迷宮入りが危惧される局面もありました。しかし、そうした状況下でも、現場の捜査員たちは決して諦めず、その熱意と努力が幾多の難事件を解決へと導いてきたのです。彼らの「執念」とも言える粘り強さが、この一家四人殺し事件の解決においても重要な鍵となりました。
 凄惨な事件現場の様子を示すイメージ写真。一家四人殺し事件の衝撃度を伝える。
凄惨な事件現場の様子を示すイメージ写真。一家四人殺し事件の衝撃度を伝える。
極秘作戦:蒲田の簡易旅館で容疑者Tを追い詰める
昭和45年8月26日午後7時50分、東京都大田区の国鉄(当時)蒲田駅西口にほど近い簡易旅館の2階。そこは、埼玉の「一家四人殺し」事件の容疑者T(当時34歳)を確保するための極秘の舞台となっていました。埼玉県警捜査第一課の警部補(当時43歳)は、コンビを組む埼玉県警蕨警察署の巡査(当時40歳)と共に、狭い二畳の部屋で息を潜めていました。別の場所では、もう一組の捜査第一課係長(当時43歳)と蕨署の巡査長(当時43歳)が待機。計画は、Tが旅館に戻ったところをこの四人で包囲し、事情聴取を開始するというものでした。刑事たちは、Tが戻るのを固唾を飲んで待ち構えていました。
昭和の時代に一家四人殺し事件を報じる当時の新聞記事。事件の記録と社会の反応を示す。
ステテコ姿の包囲網:緊迫の逮捕劇と取り調べの開始
トン、トン、トン――。床を踏む合図の音が3回響き渡ると、「来たぞ!」という緊張が走りました。白い半そでの開襟シャツに黒いズボンを履いた容疑者Tは、まさか刑事たちが待ち受けているとは知らず、廊下を歩いてきます。その瞬間、前後から二人ずつの刑事たちがTを取り囲みました。彼らは、捜査の一環として目立たないようランニングシャツにステテコ姿という異様な格好でした。以前Tを取り調べたことがあり、面識のある蕨署の巡査長が背後から「おいTちゃん、しばらくだな」と声をかけると、Tはまさかこんな場所で知人に会うとは思いもよらず、驚きの表情を見せました。別の一人の巡査が「Tちゃん、こっちへ来いよ」と促し、狭い二畳間に連れて行かれたTは、座らせられると捜査員たちに囲まれました。熱気と緊張で皆、汗びっしょりになる中、Tは正座したまま両手を膝に置き、額から首筋に汗が滴り落ちても拭おうとしません。捜査員がハンカチで汗を拭いてやると、Tはわずかに頭を下げました。こうして、事件の核心に迫る勝負をかけた取り調べが静かに始まったのです。
この「一家四人殺し」事件は、昭和の捜査史において、刑事たちの並々ならぬ執念と推理が結集された一例として記憶されています。科学捜査が現代ほど発展していなかった時代、彼らは地道な聞き込みと分析、そして容疑者との心理戦を通じて真実に迫りました。蒲田の簡易旅館で始まった容疑者Tへの事情聴取は、事件の全貌を解明し、社会に衝撃を与えた「異常な人格」を持つ犯人の闇を暴くための、決定的な一歩となったのです。この緊迫した状況から、一体どのような事実が明らかになるのでしょうか。
参考文献:
- 成智英雄『犯罪捜査記録 猟奇篇』(創人社)
- Yahoo!ニュース (Dailyshincho)「現場は血の海だった(写真はイメージ)」https://news.yahoo.co.jp/articles/5c602d3f803674dc5a2d793b87fb7d9705c82039