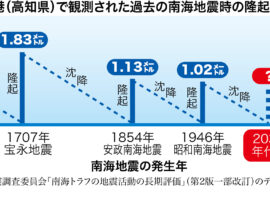高齢化が進む日本社会において、親の介護や死後の遺産相続を巡る兄弟姉妹間のトラブルは、もはや珍しいことではありません。「兄弟は他人の始まり」という言葉が示すように、かつて親しかったはずのきょうだい関係が、介護や相続の重圧によって亀裂を生み、深刻な対立へと発展するケースが多発しています。特に、介護の負担が一人のきょうだいに集中し、その苦労が適切に評価されないまま、金銭や財産の分配を巡って争いになる現状は、多くの家族が直面する課題となっています。この問題にどう向き合い、家族間の「争族」を防ぐには何が必要なのでしょうか。
介護負担が招く「きょうだい格差」と心の溝
親の介護は、時間、労力、そして精神的な負担を伴う重い責任です。大阪府に住む44歳の女性は、28歳の時に脳疾患で右半身に麻痺が残った母親の介護のため、高校教諭の職を辞めました。キャリアを諦め、結婚のタイミングも逃し、文字通り人生を捧げて母親を支えてきました。父親は既に他界しており、月12万円の遺族年金と学生時代からの貯蓄を切り崩しながらの生活でした。しかし、この献身的な介護に対し、二人の姉からの協力は一切ありませんでした。「私には家庭があるから」という一言で、彼女の“訴え”は常に退けられたのです。
 介護や相続を巡る問題で、兄弟姉妹の距離が次第に離れていく様子を表すイメージ画像。親の世話を巡る争いは家族関係に深い溝を生むことがあります。
介護や相続を巡る問題で、兄弟姉妹の距離が次第に離れていく様子を表すイメージ画像。親の世話を巡る争いは家族関係に深い溝を生むことがあります。
介護の現実とは、このように一人のきょうだいに負担が集中し、残りのきょうだいはその責任から逃れようとする「きょうだい格差」を生むことがあります。そして、その不均衡な負担は、介護を担った側の心に深い傷と不信感を残します。
相続問題に発展する介護の不均衡
介護中の負担の不公平は、親の死後、遺産相続という形でさらに大きな問題へと発展しがちです。大阪の女性のケースでは、母親の死後、実家で暮らそうと考えていた彼女に対し、二人の姉はねぎらいの言葉どころか、「遺族年金であなたも生活していたのだから、食べた分は返還しなさい」「結婚もせず、子どものいないあなたには家を引き継げない。相続放棄しなさい」と告げたといいます。
女性は、「私が結婚できなかったのは、母の介護を私に丸投げした、あなたたちのせいではないか」という強い怒りを感じながらも、何も言う気にはなれませんでした。介護から逃げようとするきょうだいを説得することは、時間とエネルギーの無駄だと悟り、「これが自分の運命だと覚悟を決めたらかえって楽になる」と語っています。無宗教ながらも「因果応報」を信じ、親への恩を忘れた者には「天罰がある」と彼女は確信しています。このような精神的な葛藤は、介護を担った人が抱えがちな普遍的な感情であり、遺産分割協議においてさらに複雑化することが少なくありません。
一方的な介護負担の現実:連絡が途絶えるきょうだい
埼玉県の57歳のパート女性もまた、近くの施設で暮らす両親の対応を一人で担っています。都内に住む3歳年下のフリーランスの妹は、どのような連絡をしても「忙しいから無理。よろしく!」とLINEで返事をするだけで、両親の介護やケアへの協力の気配は全くありません。
このように、介護の責任から逃れようとするきょうだいの存在は、介護を担う人にとって精神的、肉体的に非常に大きな負担となります。連絡が途絶えがちになったり、コミュニケーションがLINEなどの簡素なやり取りに終始したりすることは、家族としての絆が希薄になっている証拠でもあります。
家族の争いを防ぐための「事前の備え」
親の介護とそれに続く相続を巡るきょうだい間のトラブルを防ぐためには、「事前の備え」が不可欠です。これには、単に金銭的な準備だけでなく、家族間のコミュニケーション、役割分担の明確化、そして法的な準備も含まれます。
例えば、親が元気なうちに、介護に対する意向や希望を明確にし、家族全員で共有する「家族会議」の機会を設けることが重要です。また、親の財産状況を把握し、遺言書の作成や生前贈与、家族信託といった法的な手続きを検討することも、「争続」を回避するための有効な手段となります。介護の負担が特定のきょうだいに偏る場合には、その労力に対する「寄与分」を巡ってトラブルになることもあるため、事前に介護費用の分担や、介護者への何らかの対価を明確にしておくことも肝要です。
結論
親の介護と相続は、家族関係の真価が問われるデリケートな問題です。きょうだい間の絆が試される中で、不公平感や不信感が募り、修復不能な亀裂を生むことも少なくありません。しかし、それぞれの家族がこの問題から目を背けず、早期から具体的な対策を講じ、「事前の備え」を怠らないことで、多くの争いを未然に防ぎ、家族が穏やかに過ごせる未来を築くことができます。親への感謝と、きょうだい間の尊重を忘れず、困難な課題に家族一丸となって立ち向かうための対話と準備が、今こそ求められています。