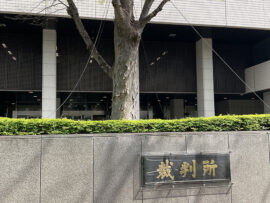日本列島に甚大な影響をもたらすとされる南海トラフ巨大地震について、政府の地震調査委員会は今年9月、その発生確率の計算方法を大幅に見直したと発表しました。これにより、30年以内に地震が発生する確率が従来の「80%程度」から、幅のある二つの異なる数値が併記される形となりました。情報の複雑化は避けられないものの、南海トラフにおける巨大地震の切迫度は依然として極めて高く、私たちは最新の科学的知見に基づいた防災対策の強化を求められています。
12年ぶりとなる計算方法の大幅見直し
地震調査委員会が南海トラフ巨大地震の発生確率計算方法を見直したのは、2013年以来、実に12年ぶりのことです。今回の見直しでは、これまでの「30年以内に80%程度」という単一の発生確率から、より詳細な評価が示されました。具体的には、主要な計算方法に基づく確率を「60~90%程度以上」へと変更。さらに、新たに別の計算方法による確率として「20~50%」も併記することになりました。しかし、このような数値の変更にもかかわらず、南海トラフでの巨大地震の切迫度は従来と変わらず「非常に高い」と評価されています。そのため、防災対策を進める上では、引き続き「60~90%程度以上」という高い確率値を強調することが望ましいと結論付けられています。
二つの異なる地震発生モデルによる評価
今回の発表で二つの確率が示された背景には、異なる地震発生モデルの採用があります。
時間予測モデルに基づく評価
南海トラフでは、地震発生に伴って地盤が隆起する「リバウンド隆起」という現象が観測されています。高知県の室津港では、江戸時代以来3回にわたってこの隆起量が測定されており、その記録からは「隆起量が大きいほど次の地震までの間隔が長くなる」という比例関係が示唆されています。地震調査委員会は、このデータを用いた「時間予測モデル」を長期評価に採用してきました。
今回の見直しでは、宝永地震(1707年)で1.83メートル、安政南海地震(1854年)で1.13メートル、昭和南海地震(1946年)で1.02メートルという過去の隆起量の根拠資料や潮位差を精査。その結果、不確実性を踏まえても上記の比例関係は否定できないと判断しました。さらに、誤差を反映できる新たな計算方法を導入した結果、発生確率が「60~90%程度以上」と算出されたのです。
単純平均モデルに基づく評価
一方、他の海溝型地震の発生確率推計には、地震の発生間隔から確率を割り出す「単純平均モデル」(「固有地震モデル」とも呼ばれる)が一般的に用いられています。南海トラフの過去6回の地震データにこのモデルを適用して計算すると、発生確率は「20~50%」となります。
地震調査委員会は、現時点ではどちらのモデルが優れているかを科学的に明確に判断できないとの見解を示しています。そのため、両モデルの確率値を併記し、不確実性を含めて情報を提供することで、科学的な観点から「より親切になった」と説明しています。
 南海トラフ巨大地震の発生確率と予測に関する図解
南海トラフ巨大地震の発生確率と予測に関する図解
情報の複雑化と防災への継続的な呼びかけ
今回の発生確率見直しと、複数の確率が併記されたことに対し、「分かりにくさが倍加した」という指摘があるのも事実です。しかし、これは科学的な不確実性を透明に示し、より正確な情報を提供しようとする地震調査委員会の姿勢の表れとも言えるでしょう。
重要なのは、これらの科学的評価の複雑さにもかかわらず、南海トラフ巨大地震が30年以内に発生する確率は依然として高く、その切迫度に変化はないという点です。私たちは、地震や津波から命を守るための準備を怠ってはなりません。地域のハザードマップを確認し、家族との避難計画を立て、非常用持ち出し品の備蓄を再確認するなど、具体的な防災対策を継続的に推進することが極めて重要です。最新の科学的知見を受け止め、冷静かつ積極的に防災意識を高めていきましょう。