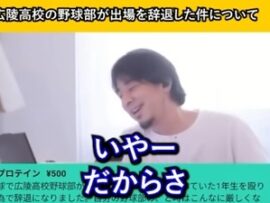2025年8月12日、日本航空123便墜落事故から40年の節目を迎えます。1985年に発生したこの未曾有の大惨事は、死者520名、生存者4名という甚大な被害をもたらし、日本の航空機事故史上最悪、単独機としては世界最悪の記録として、その記憶は今もなお深く刻まれています。524名という数字の背後には、それぞれの人生、そしてその家族や関係者たちの計り知れない物語が存在します。この節目に際し、改めて犠牲となられた方々の冥福を祈り、航空安全への意識を新たにする日としたいと考えます。
本記事では、事故から1年後の1986年に「週刊新潮」が掲載した特集「悲報はこうして来た」から、生存者の発見に尽力した上野村の村長の証言に焦点を当て、当時の緊迫した状況と人々の心を襲った衝撃を振り返ります。(本記事は「週刊新潮」1986年8月14・21日号の記事を再編集したものです。文中の年齢、役職等は1986年掲載当時のものです)
群馬県上野村:突然の悲劇に見舞われた過疎の村
日航機墜落事故により、全国にその名が知られることとなった群馬県多野郡上野村は、当時人口わずか2000人余りの典型的な過疎の村でした。事故当日、村長の黒沢丈夫氏は、東京へ日帰り出張に出かけていました。
「私は上野村を通る国道299号線の“整備促進期成同盟”の世話役をしており、その総会に出席するため、東京の都道府県会館へ出向いていました。朝6時頃に車で家を出発し、村に戻ってきたのは夕方6時58分頃だったでしょうか。一息つき、着替えて、孫が見ていたテレビのアニメ番組を横目でちらちら見ていたところ、午後7時20分頃に『日航機レーダーから消える』というテロップが流れ込んできたのです。そこで孫に頼んで、チャンネルをNHKに切り換えさせました。」
 日航機墜落事故40年、犠牲者を悼み空の安全を誓う人々
日航機墜落事故40年、犠牲者を悼み空の安全を誓う人々
村長は、この時、その日航機がまさか自身の村に墜落したとは夢にも思っていませんでした。しかし、NHKの臨時ニュースで伝えられたある証言が、彼の胸に不穏な予感を抱かせます。
「NHKの特集番組を中断して流された臨時ニュースの中で、たまたま長野県の川上村で高原野菜の収穫作業をしていた主婦が登場し、『大型の飛行機が危なっかしく三国山の方に飛んで行き、煙と火が見えた』と証言したのです。その言葉を聞いて、『これはひょっとするとわが村に落ちたかも知れないぞ』と、強く気になり始めました。」
普段は静寂に包まれる上野村に、日本中が注目する前代未聞の悲劇が襲いかかろうとしていることを、村長はまだ知る由もありませんでした。この後、黒沢村長は事故対応の最前線に立ち、生存者発見と被災者支援に奔走することになります。
1985年、日航機123便墜落現場・御巣鷹の尾根へ向かう捜索隊の様子
40年を経た今、語り継ぐべき教訓と未来への誓い
日航機123便墜落事故は、航空史に深く刻まれた悲劇として、今も多くの人々の心に残り続けています。上野村の黒沢村長が経験した「長い一日」は、この事故がいかに突然に、そして過酷に人々の生活を襲ったかを物語っています。事故から40年が経過した現在、私たちはこの歴史的教訓を風化させることなく、犠牲者への追悼とともに、航空安全の重要性を改めて認識し、技術の進化と安全対策の絶え間ない改善を通じて、未来へと繋いでいく責任があります。この悲惨な事故の記憶を語り継ぐことで、二度と同じ悲劇が繰り返されないよう、たゆまぬ努力を続けていくことが求められます。
参考文献
- 週刊新潮 1986年8月14・21日号 特集「悲報はこうして来た」より再編集