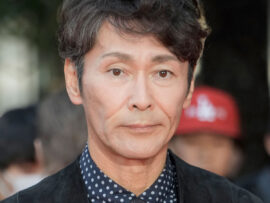第二次世界大戦という激動の時代を生き抜いた人々の証言は、現代に生きる私たちにとって貴重な歴史の記録です。特に、その時代ごとの生活様式や文化を映し出す「装い」は、当時の人々の日常や心境を雄弁に物語ります。今回、婦人画報デジタルに掲載された雑誌『美しいキモノ』(2015年夏号初出)でのインタビューより、人気作家・佐藤愛子さんの「着物」にまつわる言葉を紐解きます。戦中・戦後の極限的な窮乏を経験し、困難な時代を強く生き抜いた佐藤さんの証言は、単なるファッションの変遷を超え、歴史の重みを伝えます。
 佐藤愛子氏が語る戦時中の着物と生活の記憶
佐藤愛子氏が語る戦時中の着物と生活の記憶
女学生時代の着物と日常:戦況変化までの装い
佐藤愛子さんが女学校を卒業された年に戦争が始まりました。当初、日本軍の戦況は比較的安定しており、社会全体がそこまで切迫した雰囲気ではなかったと言います。学校では制服を着用していましたが、家に戻れば誰もが着物に着替えるのが日常であり、着物が生活の中心でした。普段着には銘仙が用いられ、外出時には縮緬や御召といった素材の着物が選ばれていました。親は娘のために一生懸命に着物を用意し、特に二尺という袖丈は当時の「お嬢さん」の装いの決まりだったと振り返ります。
 戦争を生き抜いた作家・佐藤愛子氏の視点から紐解く着物文化の変遷
戦争を生き抜いた作家・佐藤愛子氏の視点から紐解く着物文化の変遷
戦争の激化と「袖を切れ」キャンペーン
しかし、戦争が激しさを増すにつれて、日常の風景は一変します。いわゆる名士の夫人たちが愛国婦人会を結成し、戦争への協力を呼びかける「袖を切れ」キャンペーンを開始しました。これは、二尺袖のような長い袂で歩いていると「ぺらしゃらするな」(軽薄に振る舞うな)と批判され、新聞でも取り上げられるほど一般の風潮として広がっていったのです。もったいないと思いつつも、人々は袂を短く切り詰めざるを得ませんでした。この頃から、活動的なもんぺ姿が一般的になり、普段着としていた派手な銘仙を潰してもんぺに作り替えることも珍しくなくなりました。当時の銘仙は華やかでけばけばしい色柄が多かったため、労働着としては不向きなものでしたが、他に生地が手に入らない状況では選択肢がありませんでした。
 戦時中に広まった「袖を切れ」キャンペーンと婦人たちの愛国活動
戦時中に広まった「袖を切れ」キャンペーンと婦人たちの愛国活動
物資不足と着物の再利用:困難な時代の知恵
戦時下においては、どこにも生地が売っておらず、木綿のような素材は貴重品として入手困難でした。父親の背広を潰してスカートにしたり、古布を使って防空頭巾を作ったりと、あらゆるものが再利用されました。着物が惜しい、悲しいといった感情を抱く余裕は全くなく、そのようなことを考えることさえなかったと佐藤さんは語ります。現代の私たちには、当時の極限的な物資不足と、それに伴う人々の生活、そして心境の変化を想像することすら難しいでしょう。
結論
佐藤愛子さんの着物にまつわる記憶は、第二次世界大戦中の日本の生活がどれほど厳しく、そして人々がどれほど強く生きたかを伝えてくれます。華やかな着物が質素なもんぺへと姿を変え、その過程で人々の「装いへの意識」そのものが変容していった事実は、単なるファッションの流行ではなく、歴史の深い刻印です。物資が不足し、自由が制限された中でも、人々は知恵を絞り、互いに協力しながら困難を乗り越えました。佐藤さんの言葉は、この激動の時代を生きた人々の精神と、現代社会では失われつつある「物を大切にする心」の重要性を私たちに改めて問いかけています。
参考文献
- 『美しいキモノ』2015年夏号
- 婦人画報デジタル (オリジナル記事掲載元)