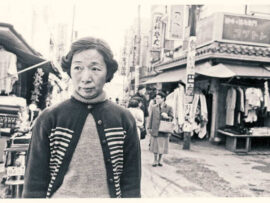警視庁の統計によれば、令和6年(2024年)の水難は過去10年間で最多の1535件に上り、水難者は1753人に達しました。特に死者・行方不明者の約80%が海(372人)と川(288人)で発生しており、中学生以下に限ると川での事故(18人)が海(5人)を大きく上回り、全体の約64%を占めています。今年も早期から水辺の安全対策が広く呼びかけられているものの、既に複数の事故が報じられています。こうした悲劇の背後には、常に懸命な救助活動を行った人々の存在があります。本記事では、1999年8月14日に神奈川県足柄上郡山北町の玄倉川で18人が濁流に押し流された水難事故に焦点を当て、当時の「週刊新潮」が報じた、川や地元関係者たちがどのように対応したのかを再検証し、現代における危機管理の教訓を探ります。(本稿は「週刊新潮」1999年9月2日号「『危機一髪』の命運 かくて18人は濁流にのみ込まれた」を再編集したものです。)
 玄倉川水難事故の現場:濁流にのみ込まれた河川敷の様子
玄倉川水難事故の現場:濁流にのみ込まれた河川敷の様子
迫り来る危機:ダム管理事務所の早期警戒
事故発生前日の8月13日午後3時頃、玄倉川のダムを管理する足柄発電管理事務所の職員は、コンピュータ画面に映し出された気象協会のデータから「これから大雨になりそうだな」とつぶやきました。そのデータは弱い熱帯低気圧の発生と、それに伴う相当な降雨を予測していたのです。
玄倉川の事故現場から約4キロ上流には、貯水量4万トンの玄倉ダムがあります。このダムは小規模ながらも、雨量が増えれば水位調整のための放流が必要となります。この気象情報を迅速に受け、足柄発電管理事務所は、山北町に位置する玄倉第1発電所の職員を現地巡視に派遣することを決定しました。同管理事務所の所長は当時を振り返り、「原則として、放流する場合には15分以上前に巡視し、警報することになっていますが、お盆休みを利用して玄倉川沿いでキャンプをしている人が多いだろうと考え、放流に備えて早めに警戒を呼びかけることにしたのです」と語っています。山北町には16のキャンプ場が存在しますが、近年では管理者のいない河川敷でキャンプをする人々が増加傾向にありました。
中州でのキャンプと迫る濁流の脅威
巡視に出た2名の職員が事故現場付近に到着したのは午後3時過ぎのことでした。この日も約100人もの人々が玄倉川でキャンプを楽しんでいました。上流に向かって右岸の河川敷には18個のテントが設営されており、さらに川を渡った中州には2個のテントが張られていました。翌日、この中州でキャンプをしていた人々が濁流にのみ込まれることになったのです。管理者のいない場所での無許可キャンプ、そして気象状況の急変という複合的な要因が、未曽有の悲劇へと繋がる伏線となりました。
玄倉川水難事故の事例は、ダム管理者の早期警戒と現場巡視の重要性を示唆すると同時に、予期せぬ自然の猛威に直面した際の脆弱性を浮き彫りにしました。2024年の水難事故増加という現状は、この過去の教訓が今なお重要であることを私たちに強く訴えかけています。適切な危機管理と、一人ひとりの防災意識の向上が、今後の水難事故防止には不可欠です。
参考文献
- 警視庁 令和6年(2024年)水難統計
- 週刊新潮 1999年9月2日号「『危機一髪』の命運 かくて18人は濁流にのみ込まれた」