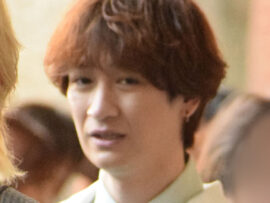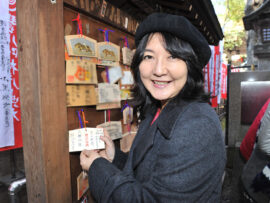大学受験は、多くの10代にとって人生における最大の転換点の一つです。現在の日本社会では、どの大学に進学するかが将来の職業選択肢やキャリアパスに大きな影響を与える現実があります。このような時代背景の中で、「自分らしい大学進学」を実現するための指南書として、『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売されました。本記事では、この発売を記念し、著者であるびーやま氏への特別インタビューをお届けします。近年議論が活発化している「Fラン大学」の存在意義について、びーやま氏が率直な見解を語ります。
 将来を考える受験生
将来を考える受験生
Fラン大学の現状と社会の視点
昨今、メディアでも取り上げられることの多い「Fラン大学」を巡る議論。「Fラン大学は廃止すべき」という厳しい意見も散見されますが、びーやま氏はその問いに対し、「非常に難しい問題であり、一概に答えを出すのは悩ましい」と前置きしつつも、「受験生には極力Fラン大学への進学を避けてほしい。しかし、もし進学したとしても逆転は可能だ」という複雑な胸の内を明かしました。
びーやま氏によれば、Fラン大学の教育レベルは一般的に高くなく、中学レベルの英語や分数計算から始める理系科目など、大学と呼ぶにふさわしいか疑問視されるケースも少なくないといいます。かつては優秀な学生のみが入学を許され、学術の中心であった「最高学府」としての大学の姿は薄れ、現代では選ばなければ誰でも大学生になれるのが現状です。少子化が進む中でも、この「何でもあり」な状況に対し、世間から厳しい目が向けられるのは当然であり、びーやま氏もその意見に同意すると述べています。
Fラン大学に「進学せざるを得ない学生」の可能性
一方で、びーやま氏はFラン大学の存在意義について、もう一つの側面を指摘します。それは、家庭の経済状況など、やむを得ない事情でFラン大学にしか進学できない学生が実際に存在するという事実です。もちろん、恵まれた環境にありながら単に勉強を怠った学生は論外としながらも、様々な背景を抱えつつも、Fラン大学に進学してもなお「頑張りたい」と意欲を持つ学生が一定数いることを強調します。
そのような学生たちの個人的な事情を無視して、ただ「Fラン大学をなくせ」と主張することは、彼らにとって選択肢を奪うことになりかねず、びーやま氏自身としてはそのような発言はできない、との見解を示しています。これは、Fラン大学が持つ教育機関としての課題と、そこに進学せざるを得ない学生の状況という、複雑な現実が絡み合っていることを示唆しています。
結論として、Fラン大学の問題は単なる教育レベルにとどまらず、社会経済的な背景や個々の学生の努力意欲までを含む多面的な課題であると言えます。びーやま氏の言葉は、安易な二元論では解決できない、高等教育の未来と学生の可能性について深く考えるきっかけを与えてくれます。