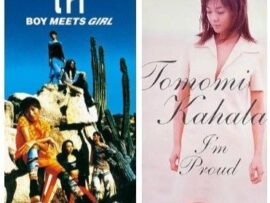現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』第98話では、柳井家を訪れたいせたくや(大森元貴)と六原永輔(藤堂日向)が、嵩(北村匠海)に舞台美術の協力を依頼するという重要な展開が描かれました。このシーンは、やなせたかし(嵩のモデル)といずみたく(いせたくやのモデル)、永六輔(六原永輔のモデル)が実際に手掛けた歴史的名作ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』の制作過程に深く関わるものです。本作を通じて描かれる、史実とドラマが交錯する創作の軌跡を紐解きます。
 NHK連続テレビ小説『あんぱん』に登場する今田美桜、河合優実、原菜乃華(写真提供:NHK)
NHK連続テレビ小説『あんぱん』に登場する今田美桜、河合優実、原菜乃華(写真提供:NHK)
『見上げてごらん夜の星を』ミュージカルの誕生とその革新性
1960年(昭和35年)に初演されたミュージカル『見上げてごらん夜の星を』は、小さな町の定時制高校を舞台に、昼間は働き、夜は星空の下で学ぶ7人の若者たちの青春群像を描いています。ある日、ひとつの手紙を巡って、彼らの友情や葛藤がユーモラスに展開。物語は、7人の夜学生と彼らの“共通のガールフレンド”となった女学生の交流を通して、「なぜ勉強するのか?」「なぜ働くのか?」といった普遍的なテーマを追求していきます。いずみたくが初めてミュージカルの楽曲を手がけ、当時日本では馴染みの薄かったミュージカルを広めたいと考えていた永六輔が台本・演出を担当しました。この作品は、日本のミュージカル史における画期的な試みとして評価されています。
坂本九との出会い:不朽の名曲が生まれるまで
『見上げてごらん夜の星を』の初演では、伊藤素道が主演を務め、当時のスターは一人も出演していなかったにもかかわらず、その革新的な内容と魅力的な楽曲で人気を博し、大阪での成功に続き翌年には東京でも上演されました。
このミュージカルが全国的な知名度を得たのは、1963年の再演時です。この時主演を務めたのが、若き日の坂本九でした。彼は同名の映画にも主演し、ミュージカルのテーマソング「見上げてごらん夜の星を」を歌い大ヒットさせました。この曲は今や国民的愛唱歌として広く親しまれています。いずみたくは、この作品をきっかけにミュージカルの魅力に深く傾倒し、1963年の再演版プログラムに「ミュージカルには必ずテーマ曲がある。(中略)それが流行歌やポピュラーソングを作曲する場合と大変に違う面白さである」と記しており、以降も劇団四季の作品など数々のミュージカル制作に携わることになります。本作はその後も1973年、1979年、2012年に再演されるなど、時代を超えて愛され続けています。

やなせたかしと盟友たちの絆:『あんぱん』が描く創造の源泉
『あんぱん』では、いせたくやと嵩が旧知の友人で、いせたくやが六原永輔を嵩に紹介する形で物語が進行しますが、史実では永六輔がいずみたくとやなせたかしを引き合わせたと言われています。意気投合したいずみたくとやなせたかしは、1973年からは「0歳から99歳までの童謡」シリーズの制作を開始し、毎月一曲ずつ、誰もが気軽に歌える歌を生み出しました。その中の代表曲が、今なお多くの人々に歌い継がれる「手のひらを太陽に」です。さらに、『アンパンマン』もアニメ化される前の1976年に『怪傑アンパンマン』としてミュージカル化され上演されており、その後もやなせといずみのタッグで複数の『アンパンマン』シリーズのミュージカル作品が制作されています。
ドラマの中で、これまで経験のない舞台美術の仕事に尻込みしている嵩は、のぶ(今田美桜)に説得されて稽古場に足を運びますが、永六輔をモデルとする六原永輔の個性的なキャラクターにさらに及び腰になっています。口を開けば「このままじゃダメだ」と言いながらも、なかなか一歩を踏み出せない嵩。しかし、史実においては、この頃から「困った時のやなせさん」として彼の才能が広く知られるようになっていく時期です。はたして嵩は、この新たな挑戦をどのように乗り越え、自身の新たな可能性を切り開いていくのでしょうか。今後の展開に注目が集まります。