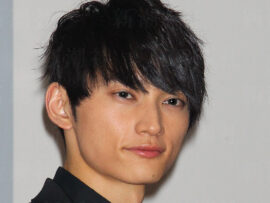中国の電気自動車(EV)大手、比亜迪(BYD)が日本の軽自動車市場への参入を正式に発表した。2026年にも軽EVの投入を目指し、日本市場に特化した専用車種の開発を進めている。特定の国・地域向けに専用モデルを開発するのはBYDにとって初の試みであり、日本市場に対するBYDの並々ならぬ重視姿勢が伺える。
軽自動車は、日本の新車販売全体の約4割を占める独自の規格であり、税制上の優遇措置が大きな魅力となっている。BYDの日本市場におけるEV乗用車販売台数は、2024年に前年比1.5倍の2,223台へと急増し、トヨタ自動車の2,038台を上回った。しかし、東南アジアや韓国を含むアジア太平洋地域全体で見ると、この伸びは必ずしも顕著とは言えない。BYDは、年内に発表を控えるプラグインハイブリッド車(PHEV)に加え、この軽EVを市場開拓の起爆剤としたい考えだ。そのため、軽自動車販売に関する深い知見を持つ人材の登用も積極的に進めている。
 BYDのロゴと電気自動車のイメージ、日本市場への参入戦略を示す
BYDのロゴと電気自動車のイメージ、日本市場への参入戦略を示す
軽自動車市場の特殊性と「非関税障壁」
軽自動車は、排気量660cc以下、全長3.4メートル以下、全幅1.48メートル以下、全高2メートル以下という厳格な日本独自の規格が定められている。この規格は、海外メーカーにとっては事実上の「非関税障壁」と見なされており、過去には欧米諸国から批判の対象となってきた経緯がある。その比較的安価な価格設定に加え、税金や保険料、高速道路の料金が低く抑えられていることから、鉄道などの公共交通機関が少ない地方における住民の重要な「足」として、長年にわたり定着している。
日本国内の乗用車EV販売においても、日産自動車の「サクラ」や三菱自動車の「eKクロスEV」といった軽EVが全体の約4割を占めており、日本市場でEVのシェアを拡大するためには、軽EV分野への参入が不可欠であるとされている。
BYDの日本向け軽EV戦略と課題
BYDは中国市場で小型車「海鴎(シーガル)」を販売しており、その価格は6万9,800元(約140万円)からと非常に競争力がある。シーガルが日本を含む海外市場に投入されれば、その低価格は既存メーカーにとって大きな脅威となると見られてきたため、これまでに徹底的な分解調査や研究が行われてきた車種としても知られている。
しかし、関係者によると、BYDはシーガルの右ハンドル仕様を製造しない方針であり、日本市場向けには専用モデルで対応することを選択した。専用の生産ラインを確保することはコスト増に繋がる可能性も想定される。「設計は完了しているものの、電池容量など未確定な部分も残されている」との説明があり、今後の航続距離などの詳細発表が待たれる。日本メーカーの軽EVの価格帯を踏まえ、BYDの軽EVも250万円程度が想定されているが、BYDは今年4月に既存モデルの「ドルフィン」を299万円まで値下げした経緯もあり、さらに安価な価格での販売となる可能性も指摘されている。
また、日本ではほとんどの急速充電器が日本独自の規格である「CHAdeMO(チャデモ)」を採用している。BYDは、日本専用の軽EVにおいてもこのCHAdeMO規格に対応させる方針を示しており、日本市場への適応に向けた抜かりない準備を進めている。
 BYDの販売店に設置されたCHAdeMO規格のEV充電設備、日本市場への適応を示す
BYDの販売店に設置されたCHAdeMO規格のEV充電設備、日本市場への適応を示す
結論:BYDの挑戦が市場に与える影響
BYDの日本軽EV市場への本格参入は、日本独自の規格が持つ「非関税障壁」という課題に正面から挑む戦略的な一歩と言える。日本市場への強いコミットメントを示す専用車種の開発、そしてCHAdeMO規格への対応といった取り組みは、BYDがこの特殊な市場で成功を収めるための重要な鍵となるだろう。日本のEV市場、特に軽EV分野における競争は、BYDの参入によってさらに激化することが予想され、今後の市場動向が注目される。