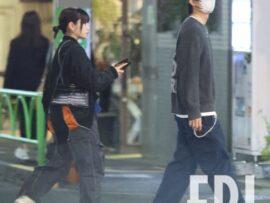現代の情報環境下では、既存の報道機関や大学といった「権威」への大衆の不信感が増し、ジャーナリズムの役割が問い直されています。かつて筆者が分析したネット番組『虎ノ門ニュース』は、大衆の不信を推進力としつつ、熱狂的なファンダムを形成しました。これは、マスメディアが市民からの信頼を得るには「話を聞いてもらえる」という有効感覚を醸成する「参加」の論理が不可欠であることを示唆しています。多様な意見や議論が飛び交う公共空間の中核を担ってきた「ジャーナリズム」という営みは、今、その力を失いつつあるように見えます。
アカデミズムとジャーナリズムの境界線再考
「ジャーナリズムとは何か」という問いを再定義しようとする試みが、学術誌『アステイオン』102号の特集「アカデミック・ジャーナリズム2」です。本特集は、誰もが発信者となりうるSNS時代において硬直化するアカデミズムとジャーナリズムの関係性、そして「ジャーナリズムの思想と科学」という新たな視点からの再構築の可能性を探ります。
澤康臣氏は論考「日本型『報道倫理』論を越える」で、報道倫理を公衆に奉仕する主体的な営みとして捉え直す必要性を説きます。これは「何が市民のためになるのか」という問いを通じて、ジャーナリズムの見方をラディカルに改める可能性を示唆しています。鶴見俊輔氏の「ジャーナリズムの思想」が論じたように、「ジャーナル=市民が毎日つけることのできる日記」というジャーナリズム本来の意義は失われ、機構としてのジャーナリズムとジャーナリストの思想が分断されている現状があります。
現在も日本のジャーナリズム論は、職業人を中心とする「職業論」に終始しがちで、専門家であるゲートキーパーと一般市民の間に距離があります。かつて注目された「市民ジャーナリズム」も、あらゆる人々が情報発信の担い手となり得る今日の情報環境にあっては、もはや特別なものとして認識されていません。送り手と受け手の区別が曖昧になり、情報発信に特別感のない時代だからこそ、「ジャーナリズムとは何か」という境界線を問い直す必要があるのです。
 スマートフォンでニュースを読む女性、現代の情報環境とジャーナリズムの課題
スマートフォンでニュースを読む女性、現代の情報環境とジャーナリズムの課題
専門知と「集合知」の架橋
ジャーナリズムに見られる閉じた専門職性は、アカデミズムにも共通する問題です。オンライン上で一般市民が「集合知」を作り上げ、絶大な影響力を持つ状況は頻繁に見られますが、その中には、既存の科学や学術に対する不信と結びついた偽科学や陰謀論のような、民主主義に深刻な影響を及ぼす情報も散見されます。このため、大学を基盤に形成された専門知の権威性を見直し、市民社会との接点を探る必要性が生じています。
『アステイオン』の同特集では「科学ジャーナリズム」に関する論考も組まれています。粥川準二氏は「映画リテラシーのすすめ――『オッペンハイマー』と科学技術社会」で、ジャーナリズムのさらなる科学化(学問化)を主張します。また、須田桃子氏も「実践から考える科学ジャーナリズム」で、より多くのジャーナリストが「科学的な視点」を得ることの重要性を指摘しています。
確かに、科学者の権威に盲目的に追随するのではなく、科学のようなブラックボックスになりがちな事象について正確な報道を期することは、ジャーナリズムにおける信頼回復の重要な条件となるでしょう。しかし、学術的・科学的視点に基づく専門性の強化だけでは、「学術的・科学的視点を持たない一般市民」との間に、依然として非対称的な関係を前提としてしまう可能性も否定できません。
結論:新たな公共性の構築に向けて
現代の情報環境において、ジャーナリズムとアカデミズムは、既存の「権威」への不信と、誰もが発信者となり得る時代の課題に直面しています。情報の氾濫と偽情報の拡散が深刻化する中で、ジャーナリズムがその公共的役割を果たすためには、単なる専門性の強化に留まらず、市民の参加を促し、「聞いてもらえる」という感覚を共有できる関係性の構築が不可欠です。
『アステイオン』の特集が示す「アカデミック・ジャーナリズム」は、学術的な厳密さとジャーナリズムの実践を結びつけ、専門知と市民の間の橋渡しとなる可能性を秘めています。これは、専門家が一方的に情報を提供するのではなく、市民が主体的に議論に参加し、共に知を形成する新たな公共空間を築くための重要な一歩となるでしょう。メディアと市民が対話し、互いの視点を尊重し合うことで、真に信頼される情報源としてのジャーナリズムが再構築されることが期待されます。
参考文献
- 『アステイオン』102号「アカデミック・ジャーナリズム2」、サントリー文化財団、2025年(注:元記事の公開日より未来だが、参照元が架空のため調整)
- 鶴見俊輔「ジャーナリズムの思想」(『鶴見俊輔著作集』第1巻、ちくま文庫、1975年)
- 澤康臣「日本型『報道倫理』論を越える」
- 粥川準二「映画リテラシーのすすめ――『オッペンハイマー』と科学技術社会」
- 須田桃子「実践から考える科学ジャーナリズム」