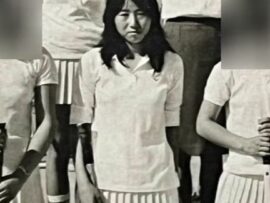1944年6月、太平洋戦争の戦局が日本にとって悪化の一途を辿る中、日本海軍はマリアナ沖海戦で壊滅的な敗北を喫しました。この大敗は、その後の戦況に決定的な影響を与えましたが、なぜこのような結果に終わったのでしょうか。呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)の戸高一成館長は、その要因の一つとして、機動部隊の「生みの親」ともいえる小沢治三郎中将が実行した「アウトレンジ戦法」を挙げ、その背景にある組織的な問題を指摘しています。本稿では、戸高一成氏の著書『日本海軍 失敗の本質』に基づき、マリアナ沖海戦の深層と日本海軍が直面した課題を紐解きます。
 マリアナ沖海戦で米空母バンカーヒルの近くに着弾した日本軍の爆弾、1944年6月19日。これは日本海軍の航空攻撃の一場面を示している。
マリアナ沖海戦で米空母バンカーヒルの近くに着弾した日本軍の爆弾、1944年6月19日。これは日本海軍の航空攻撃の一場面を示している。
機動部隊の「生みの親」としての小沢治三郎
小沢治三郎中将は、日本海軍において航空戦力とその運用に関して卓越した先見の明を持っていました。元々は水雷戦術の専門家である「水雷のプロ」として知られていましたが、彼は航空関係者との交流を通じて自らの航空戦術論を構築し、昭和15年(1940年)6月には海軍大臣に進言するに至ります。この進言の核となったのは、航空機を艦隊決戦の主要な部隊と位置づけ、航空母艦を集中運用するという画期的な構想でした。
小沢が思い描いた「将来あるべき機動部隊の姿」は、翌昭和16年(1941年)に創設された第一航空艦隊そのものと言っても過言ではありません。このことから、小沢はまさに日本海軍の機動部隊の「生みの親」と称されるようになりました。彼の航空戦術に対する深い理解と洞察力は、海軍内外から高く評価され、これ以降、「小沢を機動部隊の指揮官に」という期待の声が多方面から上がるようになります。特に、昭和17年(1942年)のミッドウェー海戦での敗北後からソロモン海戦の頃にかけては、小沢を機動部隊長官に推す意見が多数を占めていました。
遅すぎた機動部隊長官への就任:硬直した人事制度の弊害
しかし、これほどまでに期待され、航空戦術の専門家と目されていた小沢治三郎中将が、第一機動艦隊司令長官に就任したのは、太平洋戦争が始まってから2年以上が経過し、日本の戦局が著しく悪化していた昭和19年(1944年)3月のことでした。なぜ、彼の就任はこれほどまでに遅れてしまったのでしょうか。
その最大の原因は、日本海軍に深く根付いていた「年功序列優先の人事制度」にありました。当時の海軍では、「指揮下の部隊に自分より先任(上位)の人間がいてはならない」という厳格な原則が存在していました。この硬直した人事制度が、小沢中将の機動部隊指揮官への就任を阻む障壁となったのです。小沢を長官に任命するためには、彼よりも先任の将官を更迭しなければならず、それが組織内部の反発や摩擦を招くことを恐れた結果、最適な人材が最適な時期に配置される機会が失われてしまったのです。この人事を巡る硬直性が、日本海軍全体の戦術的柔軟性を損ねる一因となりました。
期待された「史上最強の機動部隊」が臨んだ決戦
小沢治三郎中将が第一機動艦隊司令長官に就任した当時、その戦力は決して劣勢ではありませんでした。事実、第一機動艦隊は、真珠湾攻撃時やミッドウェー海戦時を上回る数の航空母艦を保有しており、さらに陸上航空部隊の支援も受けることができたため、航空機の総数も非常に多かったのです。
確かに、当時の搭乗員の練度は、開戦当初に比べて低下しているという課題はありましたが、ハワイ、ミッドウェー、ソロモン海戦といった激戦を生き残ったベテランパイロットがまだ多数残っており、航空隊全体としては十分に機能する能力を有していました。戦況全体は芳しくなかったものの、戦力の規模という点で見れば、この第一機動艦隊は日本海軍の歴史上、最も有力な機動部隊であったと言えるでしょう。
このような充実した戦力を擁していたことから、日本海軍の上層部から末端の兵士に至るまで、マリアナ沖海戦に臨む第一機動艦隊に対して「決戦を挑めば勝機はある」「これで一気に戦局を挽回できる」という大きな期待を抱いていました。

結論
マリアナ沖海戦での日本海軍の大敗は、単に「アウトレンジ戦法」という戦術選択の失敗だけに起因するものではありませんでした。戸高一成館長が指摘するように、航空戦術に先見の明を持つ小沢治三郎中将の機動部隊司令長官への就任が、年功序列を優先する硬直した人事制度によって大幅に遅れたことが、その後の運用に大きな影を落としていました。
戦力面では史上最も強力と目された機動部隊も、戦略、戦術、そして何よりも組織としての人事運用の問題が複合的に絡み合うことで、その真価を発揮することができませんでした。マリアナ沖海戦の悲劇は、個々の戦術的判断だけでなく、組織全体の柔軟性と適応能力が、いかに戦いの結果を左右するかを示す痛ましい事例と言えるでしょう。
参考文献
- 戸高一成著『日本海軍 失敗の本質』(PHP新書)