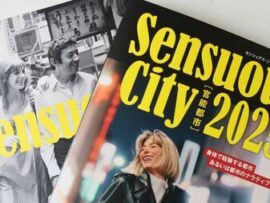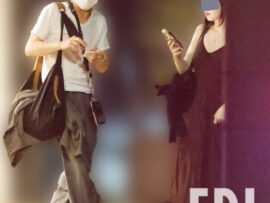空前の大ヒットを記録し、国内興行収入100億円到達が目前に迫る映画「国宝」。その成功の背景には、一度ならず繰り返し劇場に足を運ぶ「リピーター」たちの存在が大きく、「3宝目」「10宝目」といった熱狂的な声がSNSを賑わせ、「国宝沼」と呼ばれる現象を生み出しています。なぜ多くの観客がこれほどまでに魅了され、深く作品に没入するのでしょうか。この「国宝沼」の正体に迫るべく、AERAシネマカフェで実施された映画「国宝」ファン座談会の模様をお届けします。
 空前の大ヒットを記録している映画「国宝」の象徴的なビジュアル
空前の大ヒットを記録している映画「国宝」の象徴的なビジュアル
ファンとの出会い:歌舞伎経験者と吉沢亮ファンの視点
今回の座談会には、名古屋市在住の40代女性Aさんと、京都府在住の50代女性Bさんが参加しました。歌舞伎鑑賞歴10年のベテランで古典芸能にも造詣の深いAさんは、原作未読の状態で映画を鑑賞し、7月末時点で3回目の鑑賞を経験しています。一方、吉沢亮さんの熱心なファンであるBさんは、映画化が発表される数年前に原作を読んでおり、歌舞伎にはこれまであまり馴染みがありませんでしたが、すでに6回目の「リピート鑑賞」を果たすほどのめり込んでいます。二人の「国宝」との出会い方は対照的で、それぞれの視点から作品の魅力が語られました。
「原作 vs 映画」:異なる表現の衝撃
原作を事前に読み込み、吉沢亮さんのファンとして映画に大きな期待を寄せていたBさんは、実際の映画を見て「原作と映画は全く別もの」という衝撃を受けたと語ります。吉田修一氏の原作と李相日監督の手腕が、同じ題材から全く異なる物語を生み出したかのように感じられたといいます。歌舞伎に慣れていないBさんにとって、吉沢亮さんや横浜流星さんが1年半もの稽古を積んで挑んだ歌舞伎シーンが、歌舞伎を知る観客を納得させられるかという点は大きな懸念でした。しかし、Aさんの感想は、そうした懸念を払拭するものでした。
“国宝沼”にハマる:映画の圧倒的魅力
歌舞伎鑑賞歴が長いAさんは、映画鑑賞前は「歌舞伎役者ではない方がどう歌舞伎に向き合い、演じるのか」という先入観があったと明かします。しかし、1回目の鑑賞を終えた時、彼女の感想は「歌舞伎役者であるとかないとか、もうどうでもいい!」というものだったといいます。その圧倒的な完成度と感動に、自身の先入観が恥ずかしくなるほどだったと熱弁しました。Aさんは現在、職場の人や友人など周囲を巻き込み、次々と「国宝沼」に引きずり込んでいます。このエピソードは、「国宝」が専門知識の有無に関わらず、観る者全てを魅了する普遍的な力を持っていることを示しています。
まとめ:社会現象となった「国宝」の引力
映画「国宝」は単なるヒット作に留まらず、多くの観客を繰り返し劇場に呼び戻す「国宝沼」という社会現象を巻き起こしています。その魅力は、緻密なストーリーテリング、俳優陣の熱演、そして原作と異なる新たな解釈がもたらす深い感動にあります。歌舞伎の専門知識がある人もない人も、吉沢亮や横浜流星のファンもそうでない人も、一度この作品に触れれば、その引力から逃れることは難しいでしょう。あなたも「国宝沼」の扉を開いてみてはいかがでしょうか。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (2025年8月16日). 空前のヒットとなっている映画「国宝」.
https://news.yahoo.co.jp/articles/5ec34d7eb97d4ea8cf9f69e92129891f7355452c