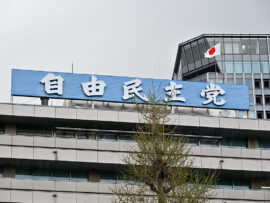三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生である筆者が教育と受験の「今」を読み解く本連載。今回は、受験期における学習効率を飛躍的に高める「習慣化」の重要性と、その具体的な実践方法について深く掘り下げていく。東大合格請負人・桜木建二の教えから、日々の学習に取り入れられる賢い習慣の作り方を探る。
勉強合宿から戻り、疲労からすぐに休んでしまった天野晃一郎と早瀬菜緒の姿は、多くの受験生が直面する現実かもしれない。しかし、東大合格請負人の桜木は「寝る前の勉強習慣」の重要性を説き、担任の水野は「歯を磨くように勉強しろ」と喝を入れる。これは単なる精神論ではなく、効率的な学習を実現するための実践的なアドバイスに他ならない。
迷いをなくし、時間を最大限に活用する「セット化」戦略
「この時間に何をやろうかな」と迷う時間は、受験期において非常に大きな損失となる。例えば、10分の移動時間のうち、毎回3分をその思考に費やしていたとすると、1年間で約18時間もの貴重な学習時間を失う計算になるのだ。これは模試を2回も受けられるほどの時間であり、合否を分ける可能性さえある。この無駄をなくすためには、特定の時間や場所で勉強する内容をあらかじめ「セット化」することが極めて有効だ。
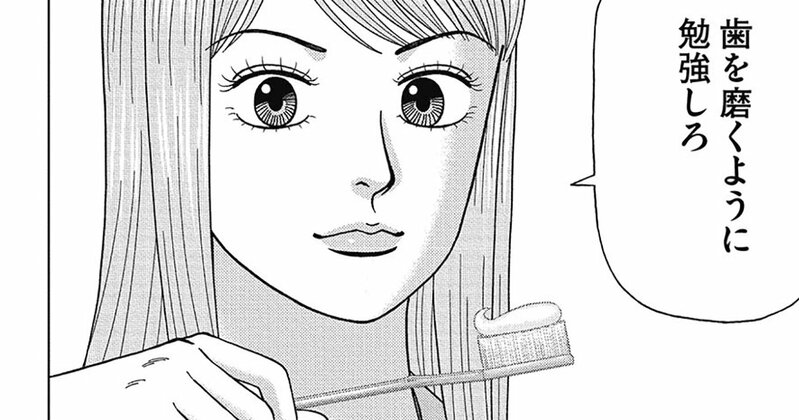 漫画『ドラゴン桜2』に登場する教師が、効率的な勉強習慣について語る様子。受験期の学習計画と集中力向上を示す。
漫画『ドラゴン桜2』に登場する教師が、効率的な勉強習慣について語る様子。受験期の学習計画と集中力向上を示す。
具体的には、「電車に乗ったら必ず英単語」「朝のホームルーム前に数学の問題を1問」といった具合に、行動と学習内容を結びつける。これにより、思考のプロセスを省き、即座に学習に取り掛かれるようになる。
特に寝る前は、英語の長文読解、現代文の論理的思考、数学の難問演習など、じっくりと思考を深められる分野が適している。布団に入った後も無意識にその問題を考え続けることで、理解がより一層深まることがあるからだ。一方で、自己採点のような単純作業は、朝の冴えた頭でテキパキとこなすのが賢明だ。採点前の「気になる状態」を一晩抱えることで、脳が無意識に問題を整理し、翌朝、新鮮なアイデアや新たな解法がひらめくこともある。
さらに、トイレやお風呂の待ち時間など、日常のあらゆる「スキマ時間」も侮れない。筆者は受験期、家中に英単語や歴史の苦手なポイントを記した付箋を貼り、嫌でも目に入る環境を作り上げた。その結果、今でもトイレに入ると、江戸幕府の鎖国政策の流れが自然と頭に浮かぶほど、知識が定着したという実体験がある。このような工夫で、無駄な時間をなくし、学習効率を最大限に高めることが可能となる。
「勉強モード」へ即座に切り替えるトリガー設定
多くの人が「やり始めるまで」が最も億劫で、そこで多くの時間を浪費している。この「腰の重さ」を解消し、「勉強モード」へ素早く切り替えるための「トリガー」を設定することも有効な戦略だ。
例えば、「机に座ったらまずタイマーを5分セットしてペンを持つ」「勉強用の特定の音楽をかける」「お気に入りのシャーペンに持ち替える」といった、ごく小さな動作をルーティン化する。これにより、意識的に「勉強しないモード」から「勉強するモード」へと移行する時間を最小限に抑え、学習への心理的な障壁を大きく下げることができる。
重要なのは、「勉強モード」と「非勉強モード」を完全に切り離しすぎないことだ。もちろん、休息の時間も必要だが、モード切り替えに時間がかかりすぎるのは非効率的だ。むしろ、日常生活のあちこちに勉強のきっかけを散りばめ、自然と学習に取り組める環境を構築する方が、トータルで見た学習効果は高まる。筆者自身も、自分をあまり信用していないからこそ、無理やりにでも勉強させるきっかけを日常生活に忍ばせていたという。
真の「勉強習慣」を築くための目的意識
ここまで「習慣化」の重要性を述べてきたが、忘れてはならないのは「なぜその勉強をやるのか」という明確な目的意識である。単に時間を埋めるためだけの「自己満足の勉強」では、いくら続けても意味は薄い。すでに完璧に覚えている単語を何周も繰り返すことに、大きな効果は期待できないだろう。
合格や実力向上といった明確なゴールに向けて、その時々で最も効果的な学習内容を選ぶことが重要だ。限られた時間を、意味のある、そして目的意識に裏打ちされた「学習」へと変えること。これこそが、真の「勉強習慣」なのである。漫然と机に向かうのではなく、常に目標を意識し、それに繋がる学習を継続する姿勢が、受験成功への道を切り開く。
勉強の習慣化は、単に時間を効率的に使う技術ではない。それは、迷いをなくし、スムーズに学習に入れる環境を作り、そして何よりも「何のために学ぶのか」という強い目的意識を持って取り組むことで完成する。日々の小さな工夫と明確な目標設定が、受験期の大きな成果へと繋がるだろう。
参考文献