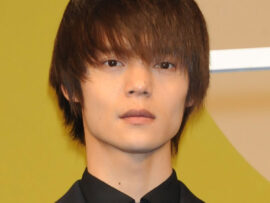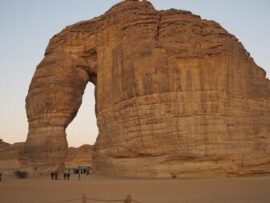読売新聞オンラインは本年8月14日、自衛隊が中国の空母を想定した攻撃訓練を実施したとする記事を配信しました。記事によれば、今年6月には中国海軍の空母「遼寧」が南鳥島沖に、また「山東」が沖ノ鳥島沖に展開し、日本の排他的経済水域(EEZ)内で軍事演習を行っていたとのことです。日本政府は、これらの中国空母が米国の空母を仮想敵として演習を実施していたと分析しています。このような中国海軍の活動の活発化は、日本の安全保障環境の厳しさを改めて浮き彫りにしています。そして今、防衛省が発表した「ある文書」が、静かではあるものの、日本の防衛態勢の現状に対する大きな波紋を広げています。それは、自衛隊の主要な式典である「観閲式」の実施を当面中止するという決定でした。
中国空母の展開と自衛隊の対抗訓練
今年6月、中国の航空母艦「遼寧」は南鳥島沖に、そして「山東」は沖ノ鳥島沖にそれぞれ展開し、日本のEEZ内で大規模な軍事演習を実施しました。日本政府はこの演習について、中国海軍が自らの空母を「米国空母」に見立てて、実践的な訓練を行っていたものと分析しています。これは、中国海軍が遠洋での作戦遂行能力を向上させ、特定の状況下での戦闘能力を磨いていることを示唆しています。
こうした中国海軍の動きに対し、航空自衛隊はF-2戦闘機を用いた空母攻撃訓練を尖閣諸島周辺海域で実施しました。これは空対艦ミサイルによる空母攻撃手順を確認するもので、ステルス性能が限定的なF-2戦闘機をあえて使用したことには、中国に対する明確な牽制と、日本の防衛能力を示す意図があったと見られます。これらの動きは、日本と中国間の緊張がかつてないほど高まっていることを改めて認識させます。
防衛省が発表した「観閲式中止」の背景
このような緊迫した情勢の中、防衛省は7月30日に「今後の観閲式等について」という文書を発表し、大きな注目を集めました。観閲式とは、内閣総理大臣が自衛隊員を閲兵する式典であり、具体的には陸上自衛隊の中央観閲式、海上自衛隊の観艦式、航空自衛隊の航空観閲式がそれぞれ実施されてきました。しかし、防衛省はこの文書において、これらの観閲式を「当分の間、中止する」と決定したことを明らかにしました。
初めて観閲式が行われたのは1951年であり、その歴史は自衛隊の歩みと重なります。今回の決定により、式典開催のノウハウが失われることへの懸念も一部で表明されています。しかし、軍事関係者の間で最も驚きをもって受け止められたのは、その中止理由でした。防衛省の文書には、その理由が次のように記されています。
《我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する現在、隙のない我が国の防衛態勢を維持する上で、そのような観閲式等を実施することは困難な状況に至っております。このため、今後、観閲式等は、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化しない限り、実施いたしません》
観閲式中止が示唆する「尖閣防衛」の緊迫度
軍事ジャーナリストは、防衛省が「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境」という言葉を用いたことに強い驚きを表明しています。この表現は、現在の日本の安全保障環境が極めて深刻な局面にあることを明確に示しており、特に中国との緊張関係、とりわけ尖閣諸島を巡る情勢がその根底にあると考えられています。
より平易な言葉に「翻訳」すると、この説明は「中国の人民解放軍による台湾や尖閣諸島への侵略可能性が高まっており、自衛隊はこれに対応するために多忙を極めている。そのため、観閲式を実施する時間的・人員的な余裕がない」という実情を浮き彫りにします。事実、海上保安庁は自衛隊よりも早く、2013年度から観閲式の「延期」、実質的な中止を継続してきました。これは、尖閣諸島への中国公船による領海侵犯が常態化し、海上保安庁がその対応に追われているためです。2018年には海上保安庁創設70周年を記念して6年ぶりに観閲式が実施されましたが、その後は再び延期、つまり中止が続いています。
観閲式の準備には多大な労力が必要とされます。かつて、陸海空の自衛隊は毎年、陸上自衛隊を主体とした3軍合同の中央観閲式を実施していました。しかし、1996年以降、部隊への負担軽減のため、中央観閲式、観艦式、航空観閲式と分けて実施されるようになり、各自衛隊にとって観閲式は3年に1回の負担に軽減されていました。しかし、現在の自衛隊は、各部隊が激務が常態化しており、文字通り「手一杯」の状況にあると報じられています。今回の観閲式中止は、自衛隊が置かれている現実と、日本が直面する安全保障上の喫緊の課題を浮き彫りにするものです。
 自衛隊の観閲式に参加する石破総理。日本の安全保障環境は近年大きく変化している。
自衛隊の観閲式に参加する石破総理。日本の安全保障環境は近年大きく変化している。
結論
自衛隊の観閲式が当面中止されるという防衛省の決定は、単なる式典の取りやめ以上の意味を持ちます。それは、日本が「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境」に直面しているという認識に基づいた、切迫した判断です。中国の空母活動の活発化、尖閣諸島を巡る緊迫した情勢、そして自衛隊全体の常態化した激務が、この決定の背景には横たわっています。今回の決定は、日本が国家としての防衛態勢を維持するために、あらゆるリソースを集中せざるを得ない状況にあることを示唆しています。国際社会が不安定さを増す中で、日本の安全保障政策は、かつてないほどの厳しさと複雑さに直面していると言えるでしょう。
参考資料
- 読売新聞オンライン (2024年8月14日) 「中国空母を想定、自衛隊が攻撃訓練…『遼寧』『山東』太平洋展開の6月に」
- 防衛省 (2024年7月30日) 「今後の観閲式等について」
- 週刊新潮 (公開日不明) 「中国空母を想定、自衛隊が攻撃訓練…『遼寧』『山東』太平洋展開の6月に」 (Yahoo!ニュース 配信)
- 軍事ジャーナリストへの取材に基づいた情報