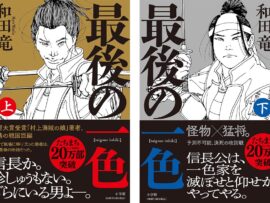人間誰もが、時には愚痴を聞いてほしい、喜びを分かち合いたいと感じるものです。それは学校の教員も例外ではありません。本連載「教員のリアル」では、そんな学校現場の知られざる現実を共有し、つらい経験への共感、心温まるエピソード、そして成功体験をお届けしています。今回、お話を伺ったのは、公立中学校で支援員として授業補助に携わる川嶋祥さん(仮名)。以前掲載された「一人一台端末」に関する記事に共感し、メッセージを寄せてくださいました。川嶋さんが語るのは、中学校で深刻化する「授業崩壊」の現実です。タブレットでゲームに興じるなど、ICT端末を不適切に使用する生徒が増え、まともに授業に参加できない現状と、その改善に向けた道のりの厳しさ、そして教育現場の支援員が感じるもどかしさが浮き彫りになります。
 中学校の教室でICT学習用タブレットを操作し学ぶ生徒たちの様子
中学校の教室でICT学習用タブレットを操作し学ぶ生徒たちの様子
教育への志と「支援員」としての新たな役割
学生時代から教育に深い関心を抱き、一時は教員を志していたという川嶋さん。同時に子どもたちへの自然体験教育にも魅力を感じ、「体力と気力のあるうちに」と、まずは民間団体で子どもと自然体験を繋ぐキャリアをスタートさせました。「教育は、自分が生涯をかけて突き詰めたいテーマです」と語る川嶋さんは、その後、やはり学校教育も経験したいとの思いから、都心部の中学校に社会科の教員として着任しました。
約4年間教員として勤務した後、家族と共に地方へ移住。一時的に教育の場を離れましたが、現場感覚を失うことへの危機感を覚え、再び教育現場への復帰を決意します。今回は教員ではなく、授業の補助を行う「支援員」として、公立中学校に戻ることになりました。「『支援員』は、授業の補助的な役割を担い、担当教員の手が回らない部分をフォローするものです。具体的には、教室内を巡回してつまずいている生徒を個別に支援したり、集中できていない生徒に声をかけたりといった役割を担います」と川嶋さんは自身の職務を説明します。
教室の後ろから見た「タブレット乱用」と授業妨害の実情
支援員として教室の後ろから日々の授業を見守る中で、川嶋さんが直面したのは、教育現場が抱える深刻な課題、特にICT端末の導入によって引き起こされている「授業崩壊」の実態でした。生徒たちが「一人一台端末」として配布されたタブレットを授業中にゲームやSNSに使用し、学習から逸脱してしまうケースが後を絶たないと言います。これにより、多くの生徒が授業に集中できず、まともに授業参加ができなくなる状況が生まれています。
さらに川嶋さんは続けます。「授業中におしゃべりしたり、居眠りしたり、あるいは授業妨害と見なされるような行為をする生徒もいるため、そうした行動を注意することも私たちの業務です。中には、席に座っていられずに教室を出て行ってしまう生徒もおり、その生徒を追いかけたり、校内を探したりすることもあります」。以前勤務していた中学校では、こうした生徒に対しては厳しく指導する方針が採られていましたが、今の勤務校では、より「ゆるやか」な方針が採用されており、厳しく叱責することはほとんどないとのことです。この指導方針の違いが、現場で働く支援員にとって大きな「もどかしさ」となっていることが伺えます。ICT教育の推進とともに、生徒の学習意欲の維持や生徒指導のあり方が、新たな教育課題として浮上している現実がここにあります。
結論
公立中学校の現場で支援員として働く川嶋祥さんの証言は、現代の教育現場における「授業崩壊」の深刻な現実、特に「一人一台端末」としてのICT端末がもたらす新たな課題を浮き彫りにしました。タブレットの不適切な使用、生徒の授業妨害、そして学校の指導方針の違いが、教育の質と教員、そして支援員の教員の負担に大きな影響を与えていることが分かります。このような生の声を共有することは、学校教育が直面する複雑な教育課題への理解を深め、より効果的な解決策を模索する上で不可欠です。教育現場の「リアル」に目を向け、多角的な視点から議論を進めることが、日本の未来を担う子どもたちの学びの環境を改善する第一歩となるでしょう。
参考資料
- 写真:東洋経済education × ICT
- Source: Yahoo!ニュース – 公立中学校「支援員」が明かす授業崩壊とタブレット問題のリアル