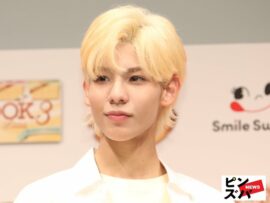日本人は「秩序を重んじる国民」として知られ、信号遵守や行列での割り込み回避といった行動規範が強く根付いています。しかし、企業におけるコンプライアンス違反が後を絶たないという矛盾もまた、日本の社会が抱える現実です。脳科学者の茂木健一郎氏と独立研究者の山口周氏は、この根本的な原因が、日本人にとっての「世間」と「社会」という概念の相違にあると指摘します。
「世間原理主義」が現代にもたらす影響
茂木氏は、日本人にとって最も大切なのが「社会」ではなく「世間」であるという考えは、江戸時代からほとんど変わっていない「世間原理主義」であると提言します。芸能人のスキャンダルや失言に対して、世間からのバッシングが起こる現象は、まさに「世間様に顔向けできない」という感覚が根強いことの表れです。この「世間」という同調圧力を重んじる風潮が、個人の行動様式だけでなく、より広範な社会問題にも影響を与えていると茂木氏は分析しています。
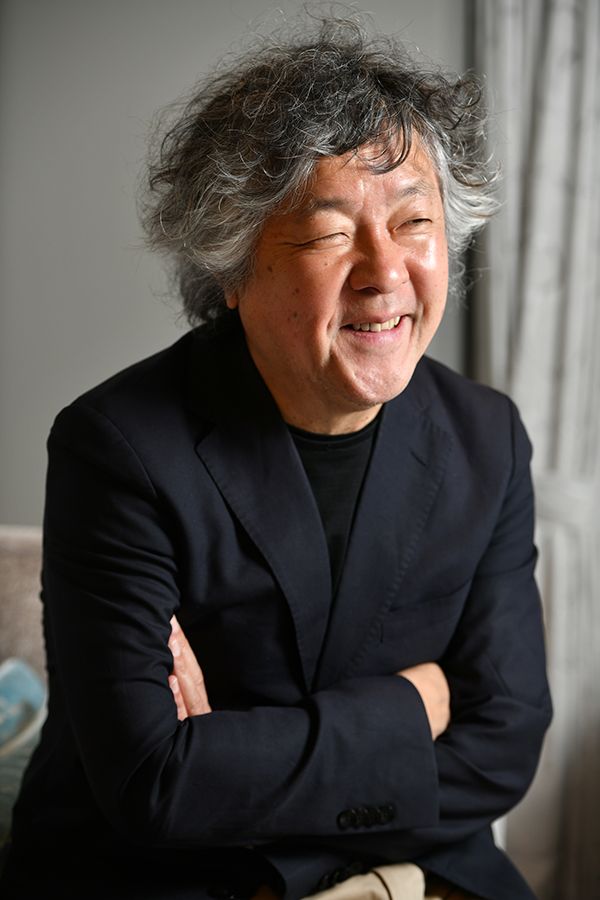 脳科学者の茂木健一郎氏と独立研究者の山口周氏
脳科学者の茂木健一郎氏と独立研究者の山口周氏
「社会」概念の誕生と「世間」との対立
「社会(society)」という言葉は、幕末から明治初期にかけて蘭学を学んだ西周(にしあまね)によって造られたとされています。西や福沢諭吉らが参加した明六社では、「society」の翻訳に苦心しました。彼らは、「society」が「独立した個人(individual)」が集まって形成されるものであり、それぞれ異なる思想や独自の意見を持つ人々が基盤であると理解しました。これは、同調圧力を前提とする「世間」とは根本的に異なる、対立する概念であると認識されたのです。福沢諭吉もまた、『学問のすすめ』の中で「世間」と「社会」を対立するものとして説明しており、この両概念間の課題は100年以上も前から存在していたことが伺えます。
プラットフォームビジネスと「パブリック」な視点の欠如
哲学者ハンナ・アーレントは、「プライベート」と「パブリック」の概念を明確に分けました。個人的な労働や余暇活動は「プライベート」な行為であるのに対し、個人を超え社会全体のために行われる活動が「パブリック」な行為であるとされます。山口氏は、日本においてこのアーレント的な「パブリック」な活動を行う人が非常に限られていると指摘します。
茂木氏は、日本でプラットフォームビジネスが育ちにくい理由もここに隠されていると語ります。プラットフォームビジネスには、「みなで世の中を変えよう」といった「社会」の視点が不可欠です。「個人的な課題」や「消費者の目線」だけでは不十分であり、「社会を変える課題解決」という大きな目標が必要です。たとえ優秀な「プライベート(個人)」が多数集まっても、彼らの視線の先に「世間」しかない場合、「社会」は生まれず、真のプラットフォームビジネスは育たないという結論に至ります。これは、単なる市場での売上や株価の上昇といった「成功」とは異なる本質的な課題を示唆しています。
結論
日本の社会に根深く残る「世間」を重んじる文化は、コンプライアンス違反が後を絶たない現状や、革新的なプラットフォームビジネスの発展を阻害する要因となっていることが示唆されます。独立した個人が集い、より大きな「社会」的目標に向かって協働する視点を持つことが、日本が直面する課題を克服し、持続的な発展を遂げる上で不可欠であると言えるでしょう。