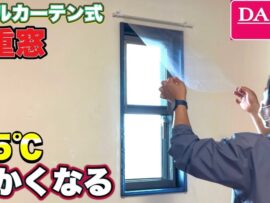日本の宝とも言える「釧路湿原国立公園」の周辺で、大規模太陽光発電施設、いわゆるメガソーラーの建設が相次ぎ、その環境影響が大きな議論を呼んでいます。特に、モデルの冨永愛氏が7月2日に自身のX(旧Twitter)で疑問を呈したことで、この問題はSNSを通じて瞬く間に注目を集めました。「週刊文春」の記者は、この深刻な事態の実態を追うべく、現地釧路へと向かいました。総面積2.6万ヘクタールを誇る釧路湿原は、国指定特別天然記念物であるタンチョウの主要な繁殖地であり、釧路市指定天然記念物キタサンショウウオの貴重な生息地でもあります。この希少生物の宝庫で進むメガソーラー建設ラッシュは、果たして適切なものなのでしょうか。
釧路湿原の生態系と相次ぐメガソーラー建設
釧路湿原はその広大な自然が育む多様な生態系で知られ、日本を代表する湿原として国際的にも高い価値が認められています。特にタンチョウは、その美しい姿から「湿原のシンボル」として親しまれ、その保護は日本の自然環境保全における重要な課題の一つです。しかし、近年、このかけがえのない自然環境のすぐそばで、経済活動の一環としてメガソーラーの建設が急速に進められています。再生可能エネルギーの導入は地球温暖化対策として推進される一方で、その設置場所が地域の生態系に与える影響は看過できない問題として浮上しています。
 釧路湿原周辺で進行中のメガソーラー建設現場、貴重な自然環境への影響が懸念される
釧路湿原周辺で進行中のメガソーラー建設現場、貴重な自然環境への影響が懸念される
日本エコロジー社による建設:専門家が指摘する環境調査の不備
建設反対の声が高まる中、特に批判の的となっているのが、釧路市北斗地区で日本エコロジー社(大阪市)が進めているメガソーラー建設です。釧路市に拠点を置く猛禽類医学研究所の齊藤慶輔代表は、この建設中の施設について、環境調査の重大な不備を指摘しています。齊藤代表によれば、建設予定地ではタンチョウの現地調査が実施されず、専門家1名へのヒアリングのみで済まされていました。さらに、国指定天然記念物であるオジロワシの調査も繁殖期を外れた数日間しか行われておらず、希少な夏鳥であるチュウヒに至っては、一切の調査が行われていない状況でした。付近ではこれらの動物全ての生息が確認されており、齊藤代表は「事前の環境調査が不十分なまま着工されたことは極めて問題」と強い懸念を示しています。
この日本エコロジー社の建設計画に対し、文化庁も8月26日に「環境調査が不十分な場合には原状回復を求める可能性もある」という見解を表明しました。これは、調査の不備が明らかになった場合、建設の中止や現状への復元を求める可能性を示唆するものであり、問題の深刻さを裏付けています。
日本エコロジー社の反論:適法性とガイドライン遵守を主張
こうした専門家や行政からの指摘に対し、日本エコロジー社の代表取締役は「週刊文春」の取材に応じ、反論を展開しました。同社は、事業地が「釧路湿原国立公園」の区域内ではなく、開発が許可されているエリアに位置していることを強調し、SNS等で広がる「湿原内」での建設という誤解は事実ではないと主張しています。
同社は、釧路市ガイドラインに基づき専門業者による調査を実施し、専門家の評価を得た上で行政から受理され、事業を開始したとしています。そのため、適法に受理された事業が不当に非難されるべきではないとの立場です。また、調査基準が行政において必ずしも明確ではなかったため、同社は自主的に追加調査を繰り返し実施したと説明しています。今後は、調査基準の明文化を行政に要望しつつ、誠実に対応していく方針を示しました。文化庁の見解についても、同社は自社の調査は適切に実施され、行政受理を得ていることから、「(調査が)不十分であれば受理されることはない」と認識しており、文化財保護法や国立公園法は主に国立公園内を対象とする規制であり、本事業は適法に進められていると改めて主張しています。
まとめ
釧路湿原周辺で進行するメガソーラー建設は、貴重な生態系への影響、事前環境調査の妥当性、そして再生可能エネルギー開発と自然保護のバランスという、複数の重要な論点を提起しています。専門家からは調査の不備が指摘され、文化庁も原状回復の可能性に言及する一方で、事業者は法的な適格性とガイドライン遵守を主張しており、見解の相違が浮き彫りになっています。
この問題のさらなる詳細については、8月27日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および8月28日(木)発売の「週刊文春」にて、小泉進次郎元環境相の動きや、釧路湿原の乱開発に関して地元で「戦犯」とされている蝦名大也前釧路市長への60分にわたる直撃取材の内容などが詳報されています。
参考資料
- 週刊文春編集部. 週刊文春 2025年9月4日号.