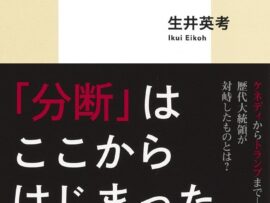東京の男子御三家と称されながらも、その校風は他とは一線を画す麻布中学校・高等学校。城南地区や横浜方面から多くの生徒が集まるこの学園は、「自由闊達・自主自立」の精神を旨とし、2025年には創立130周年を迎えます。かつて財務的な危機に直面した学園の再建に尽力し、現在は理事長として次なる一手を見据える吉原毅氏が、麻布生に託す使命と学園経営の舞台裏について語りました。
吉原毅氏は、1955年東京・蒲田生まれ。麻布中学校・高等学校、慶應義塾大学経済学部を卒業後、1977年に城南信用金庫に入職。企画部時代に小原鉄五郎・第3代理事長から薫陶を受け、2006年には副理事長、2010年には理事長に就任し、2017年からは名誉顧問を務めました。麻布学園の理事を経て、2017年より学校法人麻布学園理事長を務めています。さらに、2024年には千葉商科大学副学長、2025年には横浜商科大学理事長に就任予定であり、その経営手腕は多岐にわたる分野で高く評価されています。公益財団法人小原白梅育英基金理事長、原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長、労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団監事、一般社団法人かながわ農福連携推進協会会長、立正大学評議員など、多くの公職も兼任。著書に『信用金庫の力』『原発ゼロで日本経済は再生する』、共著に『この国の「公共」はどこへゆく』『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』など多数あり、その専門知識と経験は麻布学園の経営改善に大きく貢献しています。
麻布学園、財務危機からの再生:吉原理事長のリーダーシップ
麻布学園の理事長に就任して以来、吉原氏は学園の持続可能な未来を築くために尽力してきました。その道のりは決して平坦ではありませんでしたが、的確な分析と粘り強い交渉により、学園は大きな転換期を迎えました。
理事長就任と学園経営への関与の始まり
吉原氏は2017年にPTA会長出身として初めて麻布学園の理事長に就任しました。しかし、彼の学園経営への関与は、それよりも遡ること10年以上前、2005年のことでした。氷上信廣・第9代校長と清水慶三郎先輩が理事長に就任したタイミングで、吉原氏は理事として学園運営に携わることになります。当時、三井住友銀行の岡田明重会長(監事)らからは、「経営改善は得意だろう?言いにくいことを言ってくれ」と依頼され、教職員組合との交渉の前面に立つという重責を担うことになりました。スタンフォード大学のように、麻布学園の理事は無報酬のボランティアであり、その献身的な姿勢が求められました。
経営破綻寸前の危機と組合交渉の舞台裏
吉原氏が理事に就任した当時、麻布学園は財務的に破綻寸前の状態にありました。通常9割から10割が当たり前の自己資本比率が3割台にまで落ち込み、どの金融機関からも融資を受けられない状況だったのです。この厳しい現実を教職員組合との団体交渉の場で説明しなければなりませんでした。
 麻布学園の白い校舎と麻の葉文様の校章、背景には六本木ヒルズ
麻布学園の白い校舎と麻の葉文様の校章、背景には六本木ヒルズ
交渉の過程では、恩師から「お前は在学中そんな生意気なことを言ったことはない」と厳しい言葉を浴びせられたり、「理事会の経営責任だ」と追及されたりすることもありました。しかし吉原氏は、「原因は先生方の言い分をすべて飲んでしまったことにあります」と毅然と答え、一番若い理事として深夜まで交渉を重ねました。
状況を打開するため、吉原氏はバランスシートや損益計算書、資金繰り表に基づいた50年間のシミュレーションを作成し、このままでは何年後に経営破綻するという具体的な結果を示しました。これに対し、ある先生から「俺が計算したのと同じだ。なかなかよくできているじゃないか」と言われたというエピソードも明かされました。
学園の資金がどこに費やされていたのかを分析した結果、そのほとんどが人件費であったことが判明します。他校では非常勤教員が半数を占めることが多い中、麻布の教員は基本的に全員が正規雇用であり、正副担任制を敷くことでクラスあたりの手厚い教育を実現していました。良い教員を集めるために給与水準もトップクラスであったことが、財務状況を圧迫する要因となっていたのです。
財政健全化への道のりと教員の協力
財務状況を改善するため、吉原氏はいくつかの改革を断行しました。まず、学費をわずかに引き上げましたが、地元の子弟が通えなくなるほどに高騰させることは避けました。さらに、賞与を含む給与体系を、一定の年齢からフラットにするなど変更しました。これらの改革には教員側の協力が不可欠であり、中には退職金から300万円を学校に寄付した先生もいたといいます。
こうした努力の結果、制度改革からわずか3年で学園は黒字化を達成しました。吉原氏は「ここは我慢のしどころ」と、地道にお金を貯め続け、財務基盤の強化に努めました。
時代に合わせた教育体制の進化と教員の多様化
財務が健全化したことで、麻布学園は教員への配慮や教育体制の進化にも目を向けることができるようになりました。
コロナ禍での教員への配慮と働きやすい環境
新型コロナウイルス感染症が蔓延し、物価が高騰した時期には、健全化した財務状況を背景に、他校に先駆けて思い切ったベースアップ(ベア)を実施しました。これにより、「出すときは出すんだな」と教員から喜びの声が上がり、何よりも先生方が安心して働ける環境を整えることに成功しました。これは、学園の長期的な安定と、質の高い教育を提供し続ける上で非常に重要な施策でした。
変化する教員構成:女性教員とOBの現状
近年、麻布学園の教員構成にも変化が見られます。かつてはゼロだった女性教員も増加し、各分野で活躍しています。講師が何人かいる程度で、現在も正規雇用が中心であり、2人担任制という手厚い教育体制を維持しています。一方で、OBの先生は5〜6人と少なく、学園が多様な人材を積極的に受け入れている現状がうかがえます。
麻布学園が直面した財務危機とその克服は、吉原理事長の卓越した経営手腕と、学園全体の協力体制によって成し遂げられました。創立130周年を迎えるにあたり、麻布学園は「自由闊達・自主自立」の精神を次世代へと繋ぎながら、社会に貢献する人材を育てるという使命をこれからも果たし続けるでしょう。その歴史と伝統の上に、新たな時代に合わせた進化を続ける麻布学園の未来に注目が集まります。