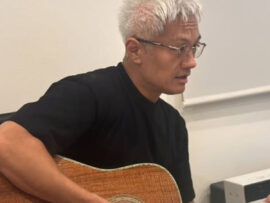自民党は2日、先の参院選における歴史的な大敗を受け、その詳細な総括結果を公表しました。石破茂首相は両院議員総会で自らの責任を認め、謝罪の意を表明したものの、政権のトップとして続投する意欲を示しています。今後の石破政権がどのような道を辿るのか、ジャーナリストの城本勝氏は、「石破政権というよりも、結党70年を迎えた自民党自体がゾンビと化しており、後継総裁が誰になろうともこの状況は変わらない」と指摘し、その先行きに懸念を表明しています。
「終わりの始まり」が迫る自民党の政局
石破首相は、2日の自民党両院議員総会において、参院選の敗北責任を認めつつ、「地位に恋々とするものではない。しかるべき時に決断する」と発言しました。これは首相が将来的に辞任する可能性を示唆する曖昧な表現でありながら、今後の政局の焦点が、いつ、どのような形で自民党総裁が交代するのかという点に移ったことを意味します。党内では、野党との協調路線を継続するのか、あるいは保守色の強い自民党本来の路線を取り戻すのか、といった路線対立が複雑に絡み合い、党内の駆け引きは一層混沌としています。明確なのは、次期自民党総裁が誰になろうとも、現在の自公政権がこのまま存続していくことは極めて困難になったという現実です。
衆参両院で与党が少数派となったことで、予算案や法案の単独可決はこれまで以上に厳しくなりました。仮に野党が内閣不信任案を提出すれば、可決される可能性が高く、政権運営が行き詰まるのは時間の問題と見られています。こうした状況を打開するためには、従来の枠組みを超えた大胆な連立拡大か、あるいは解散・総選挙による多数派の回復が不可欠です。選挙総括に明記された「解党的出直し」がもし失敗に終われば、「本当の自民党の終わりの始まりになるのではないか……」という深刻な不安が、多くの自民党議員の間で広がっています。結党70年を迎えた自民党は、党内の分断が進む中で、まさに歴史的な岐路に立たされています。
 参院選大敗を総括する自民党両院議員総会で挨拶する石破茂首相と森山裕幹事長
参院選大敗を総括する自民党両院議員総会で挨拶する石破茂首相と森山裕幹事長
逆説的上昇:世論調査に見る石破内閣支持率の謎
「解党的出直しが必要だ」とまで選挙総括に明記せざるを得なかったこと自体、石破首相にとって政権存続の厳しさを物語っています。しかしながら、マスコミ各社の世論調査では、石破内閣の支持率が軒並み上昇するという不可解な現象が見られます。例えば、8月中旬に読売新聞が実施した調査では、選挙直後の22%から39%へと17ポイントも跳ね上がりました。また、1日に公表された日経新聞の調査でも、前月比10ポイント増の42%となり、日経の調査で支持率が4割台に回復したのは半年ぶりです。
この支持率上昇の理由は、石破首相の辞任を求める中心メンバーに、旧安倍派の裏金問題を抱える議員が多かったことに起因するとされています。昨年の衆院選に続き、参院選でも自民党の裏金問題に対する国民の不信感が根強い中で、旧安倍派と対立してきた石破氏を引きずり下ろそうとする動きが、かえって石破氏への支持につながっていると分析されています。日本人特有の「判官びいき」の感情も影響しているのかもしれません。実際、各種の世論調査では、石破首相の辞任を求める意見よりも、続投を容認する意見が半数を超え多数を占めています。参院選で国民から厳しい審判を下された石破内閣が、世論調査では支持率を回復するというこの複雑な展開は、自民党のみならず政界全体に困惑と迷いをもたらしています。石破首相が「地位に恋々とするものではない」「しがみつくつもりはない」と表明せざるを得なかった背景には、責任問題を曖昧にしたままでは、自民党内の混乱がさらに長引くことへの強い懸念があったと考えられます。
結論
参院選の大敗を受けて自民党は「解党的出直し」を迫られ、石破政権もその存続が危ぶまれる深刻な局面を迎えています。党内では後継総裁を巡る駆け引きと路線対立が激化し、現行の連立政権の政権運営は一層困難になる見通しです。一方で、世論調査では石破内閣の支持率が逆説的に上昇しており、これは旧安倍派の裏金問題に対する国民の批判が、石破首相への判官びいきを促している可能性を示唆しています。自民党は結党70年の歴史の中で最も困難な岐路に立たされており、今後の選択が日本の政治情勢に大きな影響を与えることは確実です。