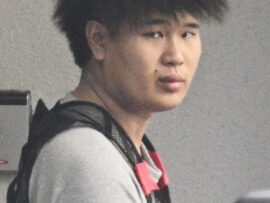「大学受験」は、日本の10代にとって人生最大の節目の一つです。良い大学に進学できれば、希望する職業に就ける可能性が高まり、将来の選択肢が広がるのが現状です。それほどまでに大学受験が持つ影響力は計り知れません。このような厳しい時代にあっても「自分らしい大学進学」を実現するために、書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が刊行されました。本書は、きれいごとを排し、「大学受験とは何か」「人生とは何か」を深く考察できる受験の決定版として注目を集めています。今回、日本ニュース24時間では、発刊を記念して著者であるびーやま氏への特別インタビューをお届けします。
 大学受験と進路選択に悩む学生のイメージ。未来の選択肢を考える受験生を象徴
大学受験と進路選択に悩む学生のイメージ。未来の選択肢を考える受験生を象徴
Fラン大学への強い風当たりとその背景
近年、メディアや社会の論調において、いわゆる「Fラン大学」に対する風当たりが強まっています。一部では「Fラン大学に進学しても意味がない」といった過激な意見も聞かれ、受験生や保護者の間で不安や戸惑いが広がっています。この状況について、びーやま氏は次のように語ります。
「確かに、おっしゃる通りFラン大学への批判は強くなっています。しかし、個人的にはやや過剰な印象を受けていますし、Fラン大学に進学したからといって人生が終わりになるということは決してありません。」
びーやま氏は、社会全体の認識が、Fラン大学の存在意義を一面的なものに限定している現状に対し、警鐘を鳴らしています。高等教育機関としての大学の多様な役割や、学生一人ひとりが持つ異なる背景を考慮に入れる必要性を強調しています。
「人生終わりではない」専門家が語るFラン大学の真の役割
びーやま氏は、自身も積極的にFラン大学への進学を推奨しているわけではないと前置きします。大学に進学するのであれば、十分な勉強をして、それなりのレベルの大学を選ぶべきだという考えを示しています。また、大学は本来、高等教育機関であるため、高い学力を持って入学し、さらに高レベルな学習を続けるのが理想的であると語ります。
しかし、その一方で、社会には多様な学生が存在することも見過ごしてはならないと指摘します。例えば、家庭の経済的事情や、家族の介護といった個人的な事情によって大学進学の選択肢が極端に狭まってしまう学生がいます。また、他人より学習のスタートが遅れたものの、大学で学びたいという強い意欲を持つ学生も少なくありません。びーやま氏は、このような学生たちにとって、現状のFラン大学が重要な「受け皿」となっている側面があることを強調します。社会においてこれ以上Fラン大学が増加することは望ましくないとしつつも、現在存在するFラン大学が果たしている現実的な役割にも目を向けるべきだというのが、彼の見解です。
地方と都市の格差:大学選択における現実
びーやま氏は、Fラン大学に対する「意味がない」という批判が、特定の環境下で形成された論理である可能性を示唆しています。具体例として、家族の介護をしながら大学に通う学生のケースを挙げます。このような状況では、学生は自宅から通学可能な範囲にある大学しか選べないことがほとんどです。
「都会であれば国公立大学から私立大学まで、あらゆるレベルの大学が豊富に存在するため、多様な選択肢の中から自分に合った大学を見つけることができます。しかし、地方に目を向けると、大学の選択肢は極端に絞られてしまいます。」
もし、その学生が通える範囲にある唯一の大学がFラン大学だった場合、その進学を「意味がない」と一蹴することは、びーやま氏にはできないと言います。この指摘は、大学選択における「地方と都市の格差」という、日本の教育システムが抱える構造的な問題を浮き彫りにします。
したがって、「Fラン大学は意味ない」と言い切ってしまう意見は、大学の選択肢が地理的、経済的に豊かな都会に住む人々の「理屈」に過ぎないのではないか、とびーやま氏は結論付けています。彼の言葉は、大学進学の機会均等や、学生一人ひとりの状況に寄り添う教育のあり方について、改めて考えさせるものとなっています。
結論
びーやま氏のインタビューは、「Fラン大学」というレッテルによって一元的に評価されがちな高等教育機関の多様な側面と、受験生が直面する現実的な課題を浮き彫りにしました。大学受験が人生の大きな岐路であることに変わりはありませんが、その選択は決して単純な学力レベルだけで決まるものではないことを強く示唆しています。家庭の事情、経済的制約、地域的な選択肢の少なさ、そして何よりも学びたいという個人の強い意欲といった多角的な要素が、学生の進路選択に影響を与えます。
「Fラン大学は無意味」という短絡的な意見は、都市部の限られた視点から生まれたものであり、全国の多様な受験生の状況を反映しているとは言えません。びーやま氏の言葉は、大学の役割を単なる学歴の場としてだけでなく、人生の多様な局面で学びの機会を提供する「受け皿」として捉え直す必要性を私たちに訴えかけます。
社会全体として、全ての学生がそれぞれの状況に合った高等教育を受けられるよう、より多角的で柔軟な視点を持つこと、そして大学が多様な背景を持つ学生たちにとって真に価値ある学びの場であり続けるための議論が求められています。
参考文献
- びーやま. (2025). 『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』 (出版社名記載なし).
- Yahoo!ニュース. (2025年9月5日). 「Fラン大は意味ない」は都会の理屈?専門家が語る大学受験の現実. 記事URL (元記事のURLに合わせる)