コロナ禍が明けた現代においても、日本の大学生が抱えるメンタルヘルス問題は深刻化の一途を辿っています。学業や人間関係の悩みから生じる不調に加え、発達障害や精神疾患が背景にあるケースも少なくありません。各大学では学生支援の体制強化が進められているものの、自殺予防対策や個々の状況に応じたきめ細やかなサポートの提供には、依然として多くの課題が山積しています。早稲田大学教授であり、同大学保健センターで精神科医として学生の診療に当たる石井映美氏が、大学生のメンタル不調の実態と支援の現状について詳しく解説します。
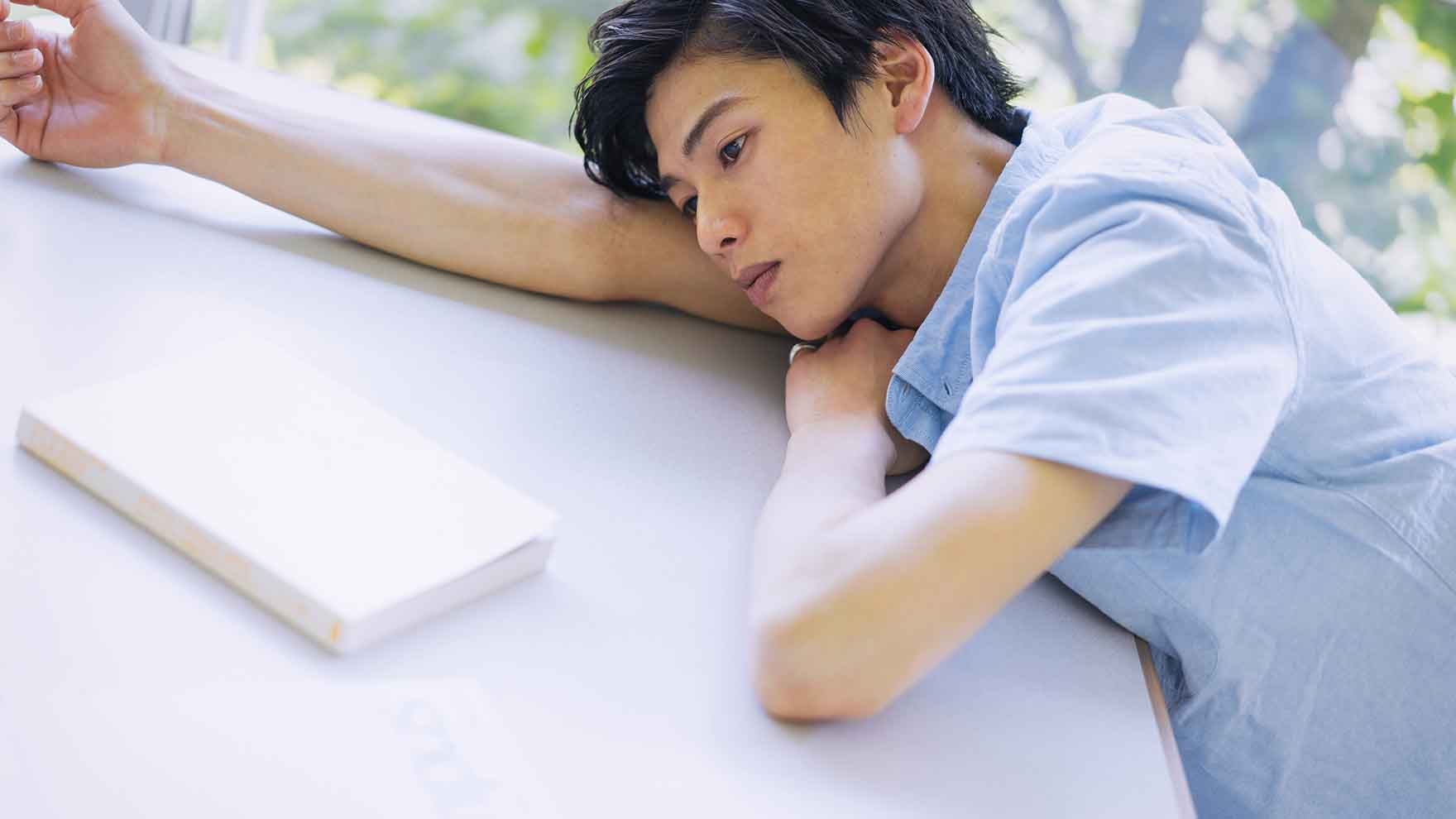 大学構内で考える学生のシルエット。メンタルヘルス問題に直面する若者を示唆。
大学構内で考える学生のシルエット。メンタルヘルス問題に直面する若者を示唆。
85%の大学が「メンタル不調学生の増加」を認識
河合塾グループのKEIアドバンスが2023年12月から2024年1月にかけて全国の国公私立大学の学長を対象に実施したアンケート調査によると、回答した大学の実に85%が「メンタルヘルスに問題を抱える学生が増加している」と回答しました。石井氏は、大学生のメンタル不調の訴えが増えている背景には複数の要因があると指摘します。
大学時代は、その後の人生を左右する進学や就職といった重要な岐路にあたる時期であり、学生は大きなストレスを抱えやすくなります。さらに、20歳前後はうつ病や統合失調症といった精神疾患が発症しやすい好発年齢でもあります。近年では、発達障害が背景にあるメンタル不調も多く見受けられるようになりました。また、コロナ禍を経て「メンタル不調は誰にでも起こり得るものだ」という認識が社会に広まったことで、学生自身が不調を表明しやすくなり、専門機関への受診や相談のハードルが下がった側面もあると石井氏は分析しています。
学業ストレスと季節変動が自殺リスクに影響
文部科学省は、コロナ禍で大学生のメンタルヘルスの悪化が懸念された2020年度以降、「大学における死亡学生実態調査」の結果を公表しています。石井氏もこの調査に、全国大学保健管理協会および全国大学メンタルヘルス学会の一員として携わっています。
この調査では、月別の学生自殺死亡数を詳細に分析しており、毎年学期が始まる4月、5月、そして9月、10月、さらに年度末の3月に自殺数が多くなる傾向が明らかになっています。一方で、夏休み期間にあたる8月は、例年自殺数が少ない傾向が共通して見られます。この結果は、学業不安といったアカデミックストレスが大学生のメンタル不調と密接に連動していることを強く示唆しています。
石井氏の臨床経験からも、季節の変わり目には自律神経のバランスの乱れから不調を訴える学生が一定数存在するといいます。特に、8月後半から11月頃にかけての冬に向かう時期は、調子を崩す学生が多い印象があるとのことです。この時期は、論文提出の期限が迫ったり、就職活動において友人たちの中で自分だけ内定が出なかったりといった状況に直面し、不安が募りやすい時期でもあります。また、中学、高校、大学と環境が変わるたびに心が揺らぎやすい学生もいるため、春学期が始まる時期に新入生が不安や不調を訴えるケースも目立っています。
まとめ
日本の大学における学生のメンタルヘルス問題は、多岐にわたる要因が絡み合い、深刻化の一途を辿っています。学業や就職活動、対人関係のストレスに加え、精神疾患や発達障害といった個別の背景も考慮した、包括的かつ個別化された支援体制の構築が喫緊の課題です。大学は、学期開始時や季節の変わり目、特にストレスが高まる時期に合わせた予防策と早期介入を強化し、学生が安心して学べる環境を提供するために、継続的な努力と連携が求められています。
参考文献
- KEIアドバンス. (2024). 全国国公私立大学学長アンケート調査.
- 文部科学省. (2020年度以降). 大学における死亡学生実態調査.
- Yahoo!ニュース. (2025年9月7日). 「85%の大学が「メンタル不調の学生が増えている」と回答」. 東洋経済education × ICT.






