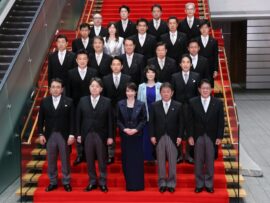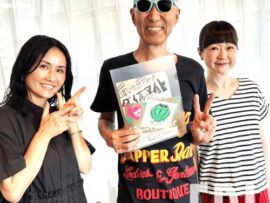作家である堀香織氏は、自身の母が難病「多系統萎縮症」と診断されてからの介護と看取りの日々を深く見つめ直しました。この記事では、病や老いに直面する家族の役割、小さな気遣いや共に過ごす時間がどれほど心を支えるか、そして介護の現場で感じた「本人の意思を尊重すること」の重みについて、堀氏の著書からの抜粋を通じて探ります。高齢化が進む日本社会において、家族の介護問題は切実なテーマであり、本稿は多くの読者に共感を呼び、示唆を与えるでしょう。
多系統萎縮症と診断された母の幸福な日々への終止符
堀氏の母は2010年6月、故郷である下田へ引っ越し、悠々自適な生活を送っていました。著者や弟、アメリカ在住の妹も頻繁に母を訪れ、家族間の交流も盛んでした。母には新たな恋人S氏ができ、2014年の夏には交際がスタート。S氏は真面目で誠実な印象ながら、ユーモアに富んだ愉快な人物で、寡黙な母と楽天的なS氏はまさに好対照でした。母が心から楽しそうに笑う姿を見て、著者は心から安堵し、母の幸福な日々を喜んでいました。
 難病の母を支える家族の絆と、心の通い合いを示すイメージ写真
難病の母を支える家族の絆と、心の通い合いを示すイメージ写真
しかし、その幸福な日常は突然終わりを告げます。2015年10月、母はわずか67歳で「多系統萎縮症」と診断されました。これは体を動かす機能が徐々に失われる神経の難病です。母は病名を知った後、自らパソコンで病状を検索し、「平均5年で車椅子、8年で寝たきり、9年で死亡」という過酷な現実を知ってしまいます。その時の母の衝撃と絶望はいかばかりだったでしょうか。当時、著者や妹、弟はそれぞれ遠方に暮らしており、頻繁に下田の母の元へ通うことは困難でした。そんな中、献身的に母の世話を焼いてくれたS氏の存在は、まさに神様のようだったと著者は振り返ります。
進行する難病と家族の心の葛藤
病が進行していく中で、家族はさまざまな心の葛藤と向き合うことになります。多系統萎縮症と診断された年の大晦日、著者と弟は下田へ母を訪ね、三人で新年を迎えました。その際、母がちらし寿司にのせる薄焼き卵をうまくかき混ぜられない姿を目にし、著者は病の進行を実感し、内心大きなショックを受けました。また、母が近所を歩いていた際にパトカーが声をかけてきたという話を聞き、まっすぐ歩けなくなっていることを知り、病が日常生活に与える影響の大きさを痛感します。著者は努めて明るく振る舞い、「格好いい杖を買おう」と、その場でインターネットで注文しました。これは、母の尊厳を守りつつ、少しでも前向きに病と向き合ってほしいという家族の願いが込められた行動でした。
遠距離介護から在宅介護へ:弟の決断と家族の協力
東京へ帰る車中、運転をしていた弟は「お母さんをあの家にひとりで住まわせておけない。僕が引き取ってもいい?」と、母の在宅介護を決意します。下田の母の家は築80年で老朽化が進み、特に寝室のある2階への階段は梯子のように急で、多系統萎縮症の母には危険でした。弟のこの決断に対し、著者は深い感謝の念を抱きました。
翌2月、弟は母を自宅へ迎え入れ、2017年6月末までの1年4ヵ月にわたり、食事の世話や病院への送り迎えなど、献身的な介護を続けました。弟は料理が得意で、食いしん坊だった母にとって、弟の作る食事は日々の大きな楽しみとなったようです。実際、母の顔色は下田にいた頃よりもはるかに良くなりました。信頼できる誰かが作る温かい食事、そして誰かと囲む食卓の存在が、難病を抱える母の心と体にどれほど良い影響を与えたか、著者は深く感じ入っています。著者はせめてもの意味で、弟に毎月3万円を渡すことで、介護にかかる負担を少しでも分かち合おうとしました。これは、家族が協力し、互いに支え合うことの重要性を示しています。
まとめ
堀香織氏の母の介護と看取りの経験は、難病という厳しい現実に直面しながらも、家族がどのように支え合い、故人の意思を尊重していくべきかを深く問いかけます。小さな気遣い、共に過ごす時間、そして介護の役割分担と経済的支援は、介護者の負担を軽減し、被介護者の生活の質を高める上で不可欠です。高齢化が進む現代社会において、このような家族の物語は、私たちに「看取り」とは何か、家族の「支え」とは何かを改めて考えさせる貴重な視点を提供してくれるでしょう。
参考文献
堀 香織『父の恋人、母の喉仏 40年前に別れたふたりを見送って』(光文社)