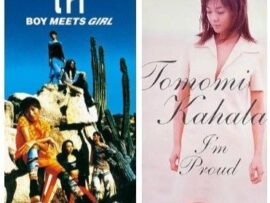皇室に関する国家事務を一手に担う宮内庁。その最高責任者である宮内庁長官は、どのような職務を遂行しているのでしょうか。ジャーナリスト井上亮氏による著作『宮内庁長官 象徴天皇の盾として』(講談社現代新書)では、初代宮内庁長官を務めた田島道治氏が、昭和天皇から直接聞き取った「生の言葉」、すなわち本音が克明に記録されています。これまでベールに包まれてきた天皇の肉声が、いかにして後世に伝えられてきたのか、その知られざる舞台裏を紐解きます。
 1969年、皇居新宮殿の長和殿ベランダで一般参賀に応える昭和天皇ご一家
1969年、皇居新宮殿の長和殿ベランダで一般参賀に応える昭和天皇ご一家
天皇の「生の言葉」が歴史に残るまで:側近たちの役割
天皇が普段どのような会話を交わし、どのような考えをお持ちなのかを知ることは、極めて困難です。天皇に接した人々の証言は貴重な手がかりとなりますが、情報が限られ、天皇との対話をありのままに外部に語るケースはほとんどありません。天皇という特殊な立場への配慮から、「公式答弁」に終始せざるを得ないのが実情です。
しかし、天皇の「生の言葉」は、聞いた本人が公表する意図なく正直に書き留めた日記、備忘録、メモといった非公式な記録の中にこそ、その真髄が表れています。昭和天皇に関しては、戦前は侍従武官長の本庄繁、内大臣の木戸幸一、侍従の小倉庫次ら、そして戦後は侍従次長の木下道雄、侍従長の入江相政、侍従の卜部亮吾など、数多くの側近による日記が刊行物として世に出ており、私たちは非公式に語られた天皇の言葉を知ることができます。そこには、包み隠さない天皇の「ホンネ」(本音)が綴られており、その人柄や人間性とともに、多様な事象に対する考え方を深く理解する上で欠かせません。日本の近現代史において天皇は不可欠なキーパーソンであり、その心の内が垣間見えるこれら側近の日記類は、まさに第一級の歴史資料と言えるでしょう。
オモテの長官が残した異例の記録:田島道治の『昭和天皇拝謁記』
上述の記録は、主に「オクの人たち」(天皇の身近に仕える内廷の人間)によるものです。これに対し、「オモテの長」(宮内庁のトップである宮内庁長官)による日記やメモ類で世に出ているものは、初代の田島道治と昭和末期の富田朝彦の二例しかありませんでした。この事実は、天皇に日常的に接するオクの人だからこそ聞けることがある、という先入観を抱かせがちでした。
しかし、その先入観を大きく覆したのが、2021年12月から『昭和天皇拝謁記』(岩波書店)として全7巻が刊行された田島道治氏の備忘録、日記、資料群です。この画期的な資料は、初代宮内庁長官という「オモテ」の立場にありながら、昭和天皇との詳細なやり取りを忠実に記録したもので、従来の認識を刷新するものです。この記録を通じて、私たちは「象徴天皇」としての昭和天皇が、いかに国の行く末を案じ、どのような心情で日々を過ごされていたのかを、より具体的に、そして生々しく知ることができるようになりました。
結論:宮内庁長官が遺した「真の声」の価値
初代宮内庁長官である田島道治氏が遺した『昭和天皇拝謁記』は、日本の歴史研究において極めて重要な意味を持つ資料です。この記録は、宮内庁長官が単なる行政のトップに留まらず、象徴天皇とその時代を後世に伝える「語り部」としての役割を担っていたことを示しています。天皇の「生の言葉」を、その真意とともに克明に記録した田島氏の功績は、日本の近現代史、特に昭和期の政治・社会状況、そして象徴天皇制の確立過程を深く理解するための不可欠な手掛かりを提供してくれます。『昭和天皇拝謁記』は、天皇の人間性や思索に迫る上で、後世に伝えられるべき貴重な歴史遺産と言えるでしょう。