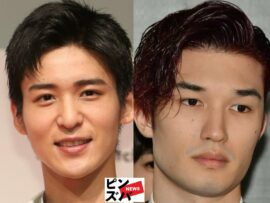江戸時代後期、第11代将軍徳川家斉の時代に絶大な権勢を振るった老中松平定信。彼の「寛政の改革」は厳格な倹約と風紀引き締めを旨とし、妥協を許さない姿勢は歴史に名を刻みました。しかし、その強硬なイメージとは裏腹に、定信は辞職願を巧みに利用し、政治を思い通りに操るという意外な一面も持っていました。本記事では、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の描写も交えながら、松平定信がどのようにして辞職願を自身の権力強化の道具としたのか、その政治手腕の真実に迫ります。
妥協なき改革路線、そして異例の辞職願い
NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の劇中では、松平定信(井上祐貴)が冒頭から一貫して妥協のない改革路線を推し進める姿が描かれています。老中格の本多忠籌(矢島健一)や老中の松平信明(福山翔大)といった同志からの「人は正しく生きたいとは思わない、楽しく生きたいのだ」「倹約令や風紀の取り締まりを緩めてほしい」といった進言にも、定信は耳を傾けません。
「世が乱れ、悪党がはびこるのは、武士の義気が衰えておるからじゃ。武士が義気に満ち満ちれば、民はそれに倣い、正しい行いをしようとする。欲に流されず、分を全うしようとするはずである。率先垂範!これよりはますます倹約に努め、義気を高めるべく、文武に励むべし!」と、自説を曲げずに独裁への道を突き進んでいきました。そんな定信が、次なる回では将軍補佐役の辞職を申し出るという、まさに意外な行動に出るのです。
 江戸時代の政治家、松平定信の姿を想起させるイメージ
江戸時代の政治家、松平定信の姿を想起させるイメージ
将軍補佐役辞任の裏に隠された策略
将軍徳川家斉(城桧吏)に嫡男の竹千代が生まれ、大名たちが祝いに駆けつける中、定信は家斉とその実父である一橋治済(生田斗真)に対し、将軍補佐役のほか、財政を司る勝手掛、大奥を管理する奥勤めの辞職願を提出します。
表向きの理由は、家斉が20歳となり、世継ぎも誕生したため、もはや自分が将軍補佐を務める必要はないというものでした。本音では定信を煙たがる家斉と治済はこれを受け入れようとしますが、ここで尾張藩主の徳川宗睦(榎木孝明)が異議を申し立てます。風紀の是正から度重なる異国船の到来まで、難題が山積する中で定信以外に局面を乗り切れる者はいないと説得し、結果として定信は将軍補佐役にとどまることになりました。
じつは、定信はこの状況を予測していました。本多忠籌や松平信明らが治済に接近していることを知り、彼らに先手を打たれる前に、徳川宗睦と結託してあえて辞職願を提出するという、巧妙な政治劇を仕掛けたのでした。「べらぼう」で描かれたこの行動は、フィクションのように見えますが、その背景には史実が色濃く反映されています。

辞職願を常套手段とした定信の政治手腕
この辞職願の提出は、松平定信にとってまさに「常套手段」でした。天明7年(1787年)6月に老中に就任して以来、彼はことあるごとに辞職願を提出し、慰留されることで将軍家斉らの信頼を再確認したり、慰留されることをテコに自らの思い通りの人事を断行したりと、政治的に巧みに利用してきたのです。
「べらぼう」で描かれたのと同様に、定信は家斉に嫡男の竹千代が生まれた直後の寛政4年(1792年)8月9日、将軍に世継ぎができたことを理由に、将軍補佐役のほか勝手掛と奥勤めの辞職を願い出ています。その結果、ひとまずは将軍補佐役と勝手掛は慰留されることに成功しました。
また、奥勤めに関しては、老中は奥勤めを兼務しないという新しい規定の導入を提案し、これが受け入れられました。しかし、これにより他の誰も奥勤めができなくなり、定信が将軍補佐役という立場を根拠に大奥を統制することになったのです。表面上は一部の役職を辞職する形を取りながら、その実、定信は自身の権限をさらに強固なものにしていったのです。
権力強化の陰で深まる確執と転落の兆し
松平定信のこの巧妙な辞任劇と権力強化の裏側では、御三家である尾張の徳川宗睦らとの関係を深めていました。これは、彼と一橋治済、そして本多忠籌、松平信明らとの確執が日ごとに深まっていたことの表れでもあります。
辞職願という一見すると弱気な行動が、実は政治的な計算に基づいた戦略であり、定信の権力掌握への執念と手腕を示しています。しかし、この権力強化の過程で生まれた亀裂や深まる対立が、やがて彼の転落のきっかけとなることを、当時の誰もが知る由もありませんでした。松平定信の政治人生は、まさに巧みな策略と、それに伴う避けられない確執の連続だったと言えるでしょう。
参考文献
- 歴史評論家 香原斗志. 「11代将軍徳川家斉の時代に権勢をふるった松平定信は、どんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「辞職届を使うなど巧妙に政治を操ることで、思い通りの改革を進めていった。しかし、転落のきっかけは思わぬところから始まった」という――。」PRESIDENT Online, Yahoo!ニュース.
https://news.yahoo.co.jp/articles/3af3951f3a461ec5751ff81e823bc608bc44928d