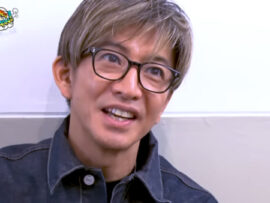アメリカ社会では、経済的な二極化が深刻化し、それに伴い社会的な課題が浮上しています。特に注目すべきは、自殺率の継続的な上昇と、その背後にある経済格差の拡大です。早稲田大学教授で政治学者の中林美恵子氏は、経済的に困窮する非大卒の白人男性の自殺率の高さ、薬物やアルコール依存による死亡率の増加を指摘し、経済格差がそのまま寿命の格差に直結している現状を警鐘を鳴らしています。本稿では、日本と比較しながらアメリカの「不平等」の実態、富の偏在、そして社会全体に及ぼす影響を深く掘り下げます。
日本と比較するアメリカの「不平等」の実態
アメリカは「豊かすぎる人と貧しい人が混在する社会」という特異な状況にあります。経済格差を示す主要な指標である「相対的貧困率」と「ジニ係数」を用いて、その現状を日本と比較してみましょう。OECD(経済協力開発機構)のデータによれば、アメリカの相対的貧困率は18%であり、日本の15.7%を上回っています。相対的貧困率とは、所得が中央値の半分未満である人々の割合を示す指標です。
また、「ジニ係数」は所得や資産の分布における不平等さを示す指標で、0に近いほど平等、1に近いほど不平等であることを意味します。同じくOECDのデータでは、アメリカのジニ係数は0.396で、日本の0.338よりも高く、アメリカの所得格差が日本よりも大きいことが明確に示されています。
急拡大するアメリカの富の偏在:上位層への集中
アメリカにおける富の配分は、著しく偏っています。特に1990年頃から経済格差は急速に拡大し、その傾向は現在も続いています。アメリカ議会予算局のデータに基づくと、2021年にはトップ0.01%の収入が1979年と比較して約9倍に増加し、トップ1%の収入も約6倍になりました。これに対し、下位20%の人々の収入はほとんど変わっておらず、格差の拡大が顕著に表れています。
 アメリカの所得格差拡大の推移を示すグラフ:1979年からの上位層と下位層の収入変化
アメリカの所得格差拡大の推移を示すグラフ:1979年からの上位層と下位層の収入変化
資産の7割を上位20%が保有する構造
所得格差の拡大は、資産の偏りにも直結しています。2024年第2四半期の純資産保有状況を所得階層別に見ると、トップ1%の層が全資産の23%を占めるに至っています。さらに上位20%の所得階層に目を向けると、その資産保有率は1990年末の60%から、2000年末に65%、2010年末に68%へと上昇し、2024年には全資産の約70%を握る結果となっています。これは、「全体の約2割の要素から全体の約8割の成果が生み出される」という「パレートの法則(80:20の法則)」をまさに体現する、富の偏在を示しています。
「富める者がさらに富む」アメリカのメカニズム
アメリカには、桁違いの大金持ちが多く存在します。例えば、イーロン・マスク氏の世界トップクラスの総資産額は、日本円に換算すると49兆円を超える規模です。世界の大金持ちランキングでは、上位20位のうち15人がアメリカ人であり、富の集中が浮き彫りになります。
アメリカの超富裕層は多額の税金を支払っていますが、その所得税率は日本ほど高くありません。日本の最高税率が所得税と住民税を合わせて約55%であるのに対し、アメリカの連邦所得税の最高税率は37%です(地方税は州によって異なり、最大で50%に達することもあります)。単純な比較はできませんが、アメリカでは、所得が増えるほど税率の低いキャピタルゲインや、税額控除制度、寄付控除制度などの利用率が高くなる傾向があります。これにより、所得が高い層ほど実質的な税負担が減少するように見える仕組みが確立されており、富裕層がさらに富を蓄積しやすいサイクルが生まれていると言えるでしょう。
政府の役割とフィランソロピーの台頭
日本では政府が貧富の差を是正するための役割を担う傾向が強いですが、アメリカでは政府のその力が弱いという特徴があります。このため、富裕層はNPO(非営利団体)や財団を設立し、国内外の貧しい人々への公共サービス的な支援を行う「フィランソロピー」(慈善活動)を積極的に行っています。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が設立した「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」によるアフリカ諸国へのワクチン支援やコンピュータ提供などがその典型的な例です。教会や慈善団体も伝統的に同様の活動を続けています。
しかし、政府の是正機能が弱い結果として、所得格差や貧富の差は大きく拡大し、中間層は薄くなっています。そのしわ寄せとして、多くの貧しい人々が日々の食費にも困るような厳しい生活を強いられているのが、現在のアメリカ社会の現実です。
結論
アメリカにおける経済格差の拡大は、単なる所得や資産の偏りの問題に留まらず、社会の分断、中間層の減少、そして白人男性の自殺率上昇といった深刻な社会的影響を及ぼしています。日本と比較することで、アメリカ社会の「不平等」が際立ち、富める者がさらに富むメカニズムが確立されていることが明らかになりました。政府の役割が限定的である中で、慈善活動が重要な意味を持つ一方で、根本的な解決には至っていません。この深い亀裂は、アメリカ社会が直面する最も喫緊かつ複雑な課題の一つであり、その動向は世界にとっても重要な意味を持ちます。
参考文献
- 中林美恵子. 『日本人が知っておくべきアメリカのこと』 辰巳出版, 2023年.
- OECD Data (経済協力開発機構). 相対的貧困率およびジニ係数に関する最新データ.
- アメリカ議会予算局 (Congressional Budget Office) データ. 所得および資産格差に関する統計.
- President Online. 「アメリカでは自殺率が上昇し続けている…」2023年10月31日掲載記事を再編集.
- Yahoo!ニュース. 上記President Online記事の配信元.