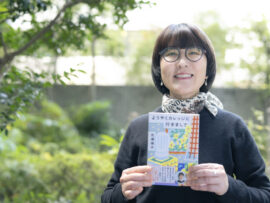近年、日本の食卓から、かつて身近だった大ぶりで脂の乗ったサンマの姿が遠ざかっています。消費者からは「小さくて高い」という嘆きの声が聞かれ、秋の味覚として親しまれてきたサンマは今や高級魚の様相を呈しています。資源の悪化が深刻化する中、なぜ細く小さなサンマが食用として市場に流通し続けるのか。その背景には、単なる不漁だけではない、日本の食文化と漁業が抱える複雑な現状が横たわっています。
資源悪化と小型化:それでもサンマが市場に出回る理由
現在、サンマの資源は急激に悪化し、漁獲されるのは小型魚ばかりとなっています。2024年には東京都内のスーパーで、マイワシほどの小さなサンマが1尾200円以上で販売されるケースも多く見られ、その味気なさは否めません。不漁により身は細く小さく、脂の乗りも悪い。それにもかかわらず、サンマがマイワシやサバといった他の大衆魚とは異なり、漁港から豊洲などの魚市場を通じて食用として取引され、小売店で販売されるのには特別な理由があります。
大手スーパー・イトーヨーカドーで長年水産物のチーフバイヤーを務めてきた小谷一彦氏(現・魚食普及アドバイザー、小谷フードビジネス代表)は、サンマが持つ「特別な存在感」を指摘しています。その季節感は他の魚にはないものであり、これが産地から小売りへと流通する大きな要因となっているようです。年間数万トンという過去にないレベルの不漁が続く現状でも、サンマは多くの消費者が「旬」を知る魚として、季節を味わうために手に取る期待が持てる大衆魚なのです。
 高値で並ぶサンマ、かつての食卓の風景とは一変
高値で並ぶサンマ、かつての食卓の風景とは一変
過去の「庶民の味方」と現代のギャップ
小谷氏が魚の仕入れを担当していた2000年代半ばまで、サンマは年間数十万トンという好調な水揚げが続き、1尾あたりの重さは約150グラムが中心でした。時には200グラムの大物が獲れることもあり、現在の状況からは想像できないほど大きな魚だったと振り返ります。当時、現在の主流である100グラム前後のサンマは価値が低く、生鮮流通に乗ることはほとんどなく、餌用や缶詰向け、あるいは輸出用として引き取られていました。
大きくふっくらとしたサンマの小売価格は1尾100円ほどで、特売時にはさらに安価で大量に販売され、秋の味覚として「庶民の味方」でした。小谷氏はこの「100円で脂の乗った旬の味覚」という過去の印象が40歳以上の消費者に深く根付いており、当時のサンマを懐かしんでは現状を嘆く要因になっていると説明します。このため、店頭で多くの消費者が「ずいぶん小さいサンマなのに高い」と口を揃えるのです。
「秋刀魚」が背負う文化的価値と限界サイズ
他の魚種であれば、品質やサイズが劣ればスーパーの店頭に並ぶことは少ないかもしれません。しかし、サンマは「秋刀魚」と書かれるように、その名に秋を冠し、ほとんどの消費者が旬を知っているという点で他の大衆魚とは一線を画します。頭が付いた丸ごとの1尾で生鮮流通し、多くの消費が期待できる大衆魚は他にほとんどなく、サンマの存在感は極めて大きいと言えます。

不漁の現在、豊漁だった頃よりも小さく、1尾100グラムのサンマであっても「1尾」として扱われます。小谷氏によれば、100グラムは塩焼きなどで味わう際の「限界のサイズ」であり、これ以下になるとさすがに小さすぎて、食べても味気なく感じられ、消費者から敬遠されてしまう可能性が高いと指摘しています。
結論:文化と市場のはざまで苦境にあえぐサンマ
サンマの不漁と小型化は、日本の食文化に深く根付いた「秋の味覚」の象徴を大きく揺るがしています。かつては手の届く価格で旬を彩った大衆魚が、資源の激減とサイズの小型化によって「小さくて高い」高級魚へと変貌を遂げました。それでもなお、サンマが市場に流通し続けるのは、その強い季節感と文化的価値が消費者の購買意欲を支えているためです。しかし、この現状が続けば、消費者の期待と現実とのギャップは広がるばかりであり、サンマが日本の食卓から真の意味で遠ざかる日も近いかもしれません。漁業者、流通業者、そして消費者が一丸となって、この「秋刀魚」が未来も日本の食文化の一部であり続けるための新たな道筋を模索する時期に来ていると言えるでしょう。