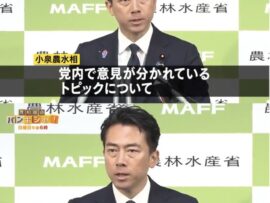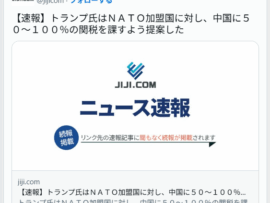日本の象徴である天皇。その歴史は世界最古の王朝とも言われ、126代目の天皇陛下が2019年に即位されました。 悠久の歴史を誇る皇室ですが、その起源はどこにあるのでしょうか? 本記事では、考古学者・森浩一氏の著書『日本神話の考古学』を参考に、神武天皇以前の皇室のルーツ、特に南九州・日向神話に焦点を当て、謎に包まれた歴史の扉を開いていきます。
神話の世界から歴史の検証へ:南九州と皇室の繋がり
日向とは?鹿児島との関係性
神武天皇以前の時代、いわゆる“神代”の舞台として描かれている「日向」とは、現在の宮崎県のみならず、鹿児島県を含む広大な地域を指します。神話の中では、特に鹿児島県南西部の薩摩半島が重要な舞台として登場します。 隼人と呼ばれる人々が活躍したこの地は、神話の展開において天皇家の遠い先祖と密接な関係を持っているとされています。
 薩摩半島の海岸線
薩摩半島の海岸線
しかし、神話と歴史の境界線はどこにあるのでしょうか? 『古事記』や『日本書紀』の記述は、史実を反映しているのでしょうか、それとも編纂者の創作なのでしょうか? この疑問を解き明かすためには、考古学や民俗学の資料、そして南九州の土地柄や奈良時代以後の歴史的背景を考慮する必要があります。
考古学的資料が語るもの
“完全な創作”と断じるには、無視できない考古学的資料が存在します。もちろん、『古事記』や『日本書紀』の物語がそのまま史実であったとは考えにくいですが、南九州、特に隼人の地域に存在する資料は、私たちに新たな視点を与えてくれます。
鵜戸の岩屋と神武天皇:17世紀の記録が伝える真実
ジョアン・ロドリーゲスの証言
17世紀初頭、日本で活躍したイエズス会の通事、ジョアン・ロドリーゲスは、『日本教会史』の中で、興味深い記述を残しています。彼は、「日本人が最初に住んだのは九州の日向であり、最初の国王である神武天皇も日向に住んでいた。日向には鵜戸の岩屋という洞窟があり、そこが国王の宮殿であった」と記しています。
日本語に通暁していたロドリーゲス、通称「伴天連」。彼が日本の人々から直接話を聞き、記録に残した情報は、歴史の謎を解き明かす上で貴重な手がかりとなります。 著名な歴史学者、例えば(仮称)山田教授は、「ロドリーゲスの記録は、当時の民衆の間で語り継がれていた伝承を反映している可能性が高く、歴史研究において重要な資料と言えるでしょう」と述べています。
伝承と歴史の融合
ロドリーゲスの知識は、『古事記』や『日本書紀』だけでなく、九州の人々から聞いた伝説も含まれていると考えられます。 神武天皇以前の皇室のルーツ、そして南九州との繋がり。 これらの謎を解き明かすためには、神話と歴史、そして伝承を融合させた多角的な視点が不可欠です。
まとめ:古代日本のロマンに思いを馳せて
神武天皇以前の皇室のルーツを探る旅は、古代日本のロマンに触れる刺激的な体験です。 南九州・日向の地には、今もなお多くの謎が眠っています。 この記事が、古代史への興味を深めるきっかけになれば幸いです。