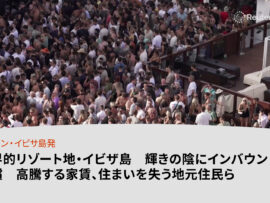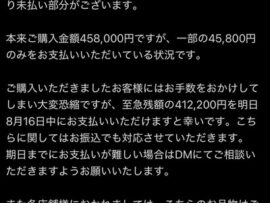やなせたかしが念願の東京高等工芸学校工芸図案科(現在の千葉大学工学部)に入学したのは1937年。同年7月に日本が中国と全面戦争に突入するという不穏な時代にあって、自由な校風が根付くこの学舎は、やなせ氏の将来のクリエイター業の礎となり、後世に語り継がれる国民的ヒーロー「アンパンマン」の誕生へと繋がる深遠な学びを彼にもたらしました。本稿では、やなせたかし氏の生い立ち、特に文学との出会いがどのように彼の創作哲学、ひいてはアンパンマンの世界観を形成していったのかを深く掘り下げていきます。
 「アンパンマン」の原作者である漫画家・詩人のやなせたかし氏の肖像。
「アンパンマン」の原作者である漫画家・詩人のやなせたかし氏の肖像。
絵画の挫折から開花した文才:やなせたかしを育んだ読書体験
学校生活は自由を謳歌する場であるだけでなく、やなせたかし氏にとって「ぼくの生き方、人生の考え方の基本はすべてこの学校で学んだ」と語るほど、アンパンマンが生まれる土壌が耕されていった重要な時期でした。その大きなきっかけの一つが、学芸部での活動です。自らよりも絵の上手い同級生を目の当たりにし、絵以外の技術を身につける必要性を痛感したやなせ氏は、学内の学芸部に入部します。
ここで彼の大きな強みとなったのが、それまでに培ってきた膨大な読書量でした。やなせ氏は「でも僕は絵を描いたり、本を読んだりするのは好きだったんで、それでなんとか、寂しさから救われたんじゃないのかなと思います。とにかく本は、よく読んでいました」(やなせたかし『何のために生まれてきたの?希望のありか』PHP研究所、2013年)と述べています。精神的に不安定だった少年時代、早くに父を亡くし、母の再婚で伯父夫婦に引き取られた経験を持つやなせ氏は、まさに「本の虫」だったのです。
読書家であった伯父の家には、『中央公論』『改造』『文藝春秋』『オール讀物』『婦人倶楽部』『主婦之友』『婦人公論』といった雑誌から、実の父が残した『世界美術全集』、トルストイなどのロシア文学、島崎藤村や三木露風の詩集、石川啄木の歌集、そして聖書まで、多岐にわたる書物が揃っていました。これらの書物を次から次へと読み漁った経験は、学生向けの執筆活動に十分な素養を与えました。クラスで回覧する雑誌の編集も手掛け、旺盛に小説を執筆する姿は、伯父に反対され叶わなかったものの、早稲田大学に入学して大作家になるという彼の夢と文才への自信を裏付けていました。この時期には既に、後年様々な分野で活躍するやなせたかし氏の原型が形成されていたと言えるでしょう。
創作の核を形成:井伏鱒二と太宰治がやなせたかしの文体を変えた瞬間
やなせたかし氏の創作の原型を語る上で、井伏鱒二と太宰治に深く心酔した経験は決して欠かせません。当時、やなせ氏の文体は父と伯父が所有していた古典的な本を読み過ぎた結果、古めかしい美文調でした。しかし、なぜかこの文体が原因で筆が進まなくなってしまう時期が訪れます。
そんな時に、やなせ氏の文体を解き放ったのが井伏鱒二と太宰治の作品でした。やなせ氏は、二人の文体から「詩のリズム」を感じ取り、「文章の書き方」を理解したと語っています。井伏鱒二の代表作『山椒魚』や『屋根の上のサワン』、そして太宰治の短編集『晩年』などに深い感銘を受けたと話しています。
アンパンマンに息づく「哀愁とメルヘン」:文学的影響が育んだ独自の作風
井伏鱒二と太宰治の短編小説を読むと、やなせたかし氏が彼らからいかに大きな影響を受けていたかが明確に理解できます。それは、塩をかけることでスイカの甘さが際立つように、小説に漂う「哀愁」が「メルヘンの美しさ」を引き立て、同時にその美しいメルヘンの世界が「哀しみ」をより深くするという、相反する二つの要素が組み合わさった作風としてやなせ作品にも頻繁に見られます。
太宰治の『晩年』に収録された短編小説「魚服記」もまた、やなせ氏が影響を受けた「哀愁とメルヘン」の組み合わせが色濃く見て取れる作品です。この物語の主人公は、滝壺近くの山小屋で炭焼きをする父と共に小さな茶店を営む娘のスワ。彼女はかいがいしく家計を助けるためキノコを採りますが、父は炭やキノコが売れると決まって酒に溺れて帰ってくるという、貧しくもどこか牧歌的な生活を送っています。しかしある日、スワは父からむごたらしい仕打ちを受け、外へ飛び出し、やがて滝壺へと身を投じてしまいます。この物語が内包する純粋な悲しみと、抗えない運命の哀愁は、やなせたかし氏の心に深く響き、彼の創作に大きな影響を与えたのです。
やなせたかし氏の創作の核には、この井伏鱒二や太宰治から受け継いだ「哀愁」と、彼自身の「メルヘン」が絶妙に融合した独自の哲学が息づいています。
やなせたかしの創作活動は、その困難な生い立ちの中で培われた豊富な読書体験と、特に井伏鱒二や太宰治との文学的な出会いによって深く形成されました。絵画の道で一度挫折を経験しながらも、文学の世界で独自の文体と哲学を確立し、やがて「哀愁とメルヘン」という相反する要素を融合させた独自の作風を生み出したのです。アンパンマンが単なる明るいキャラクターではなく、時に深い悲しみや自己犠牲の精神を描くのは、まさにこの文学的背景、特に彼の魂に刻まれた哀愁の美学が根底にあるからに他なりません。彼の作品が時代を超えて多くの人々に愛され続ける普遍的な魅力は、この深淵な創作哲学に支えられていると言えるでしょう。
参考文献
- 物江 潤『現代人を救うアンパンマンの哲学』(朝日新聞出版)
- やなせたかし『何のために生まれてきたの?希望のありか』(PHP研究所、2013年)
- Yahoo!ニュース(ダイヤモンド・オンライン転載)