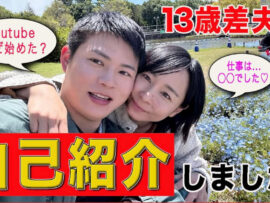AIの進化は目覚ましく、人間の知能を超える日が来るかもしれないという予測もある一方、2024年のノーベル物理学賞受賞者であるジェフリー・ヒントン博士はAIの危険性を警告しています。しかし、物理学者である田口善弘氏は、AIが人類を脅かす可能性を否定しています。なぜなら、AIと人間の知能は根本的に異なるからです。では、そもそも「知能」とは一体何なのでしょうか? 本記事では、田口氏の著書『知能とはなにか』を参考に、知能の定義を再考し、人間とAIの知能の決定的な違いを分かりやすく解説します。
脳の機能解明への挑戦:非侵襲的手法の限界
 脳のMRI画像
脳のMRI画像
fMRIやEEGといった非侵襲的な手法により、脳の活動を観察する技術は飛躍的に進歩しました。近年では、機械学習を活用することで、これらのデータから人間の思考内容を予測する技術も開発されています。まるでSFの世界のような「読心術」の実現も夢ではなくなってきているのです。
これらの非侵襲的な計測データは、脳活動を理解するための貴重な情報を提供してくれます。しかし、脳がどのように知能を実現しているのかという核心部分の解明には、まだ至っていないのが現状です。
ある高名な非線形物理学の権威は、脳研究の現状について、次のような鋭い指摘をしています。「コンピュータにMRIをかけても、その動作原理は理解できないだろう。同様に、非侵襲的な脳活動計測だけで知能の謎が解けると考えるのは早計ではないか。」
つまり、脳の各部位が活動しているかどうかを把握するだけでは、それぞれの部位がどのような機能を担っているのかを理解することはできない、というわけです。
 脳の活動イメージ
脳の活動イメージ
知能の定義:情報処理能力から「予測」と「制御」へ
知能とは、一般的に情報処理能力と考えられています。しかし、田口氏は、知能の本質は「予測」と「制御」にあると提唱しています。
人間は、過去の経験に基づいて未来を予測し、その予測に基づいて行動を制御することで、環境に適応し、生存確率を高めてきました。例えば、熱いフライパンに触ると火傷すると予測し、触らないように手を制御するといった具合です。
一方、現在のAIは、大量のデータからパターンを学習し、特定のタスクを高い精度で実行することができます。しかし、AIには、人間のように未来を予測し、行動を制御する能力は備わっていません。
AIは、与えられたデータに基づいて最適な解を導き出すことはできますが、データにない状況に直面した場合、適切な対応をとることが難しいのが現状です。
人間とAIの知能:創造性と意識の有無
人間とAIの知能のもう一つの大きな違いは、創造性と意識の有無です。人間は、新しいアイデアを生み出し、芸術作品や科学技術を生み出すことができます。また、自分自身を認識し、感情や思考を持つことができます。
一方、AIは、既存のデータに基づいて新たなパターンを生成することはできますが、真の意味での創造性を持っているとは言えません。また、AIには意識がなく、自分自身を認識することも、感情や思考を持つこともできません。
料理研究家の山田花子さん(仮名)は、「料理は創造的な活動であり、人間の知能の賜物と言えるでしょう。AIはレシピを生成することはできますが、人間の料理人と同じように、食材の微妙な変化に対応したり、新しい料理を生み出すことは難しいでしょう。」と述べています。
まとめ:AIと人間の知能は異なるもの
AIは、特定のタスクにおいて人間を凌駕する能力を持つようになってきていますが、人間のように未来を予測し、行動を制御する能力や、創造性、意識は持ち合わせていません。AIと人間の知能は、本質的に異なるものなのです。
AIの進化は、人間の生活を豊かにする可能性を秘めていますが、同時に、AIの利用に伴うリスクについても慎重に検討していく必要があります。