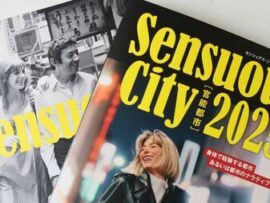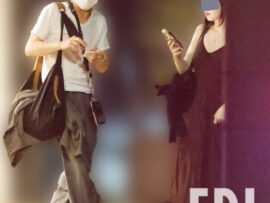小学校や中学校といえば、上履きへの履き替えが当たり前だった時代を覚えている方も多いでしょう。しかし、東京都内の公立小中学校では、外履きのまま過ごす「一足制」を導入する学校が増加しています。今回は、この「一足制」の現状、メリット・デメリット、そして子どもたちの反応について詳しく見ていきましょう。
一足制が広がる背景:人口増加と清潔な環境
東京・港区では、公立小学校19校中18校が一足制を導入しています。その背景には、子どもの人口増加と学校周辺の環境変化があります。
人口増加によるスペース確保
港区の5〜14歳の子どもの人口は、2004年には10,699人でしたが、2024年には23,985人と10年間で約2.2倍に増加しました(港区HP:4月1日年齢別人口より)。この急激な人口増加に伴い、学校施設のスペース確保が課題となっています。下駄箱をなくすことで、限られたスペースを有効活用できるというわけです。
清潔な環境の維持
港区の学校周辺は舗装道路が多く、校庭も人工芝の学校が増えています。そのため、土の汚れが校舎内に持ち込まれにくく、一足制を導入しやすい環境となっています。
 alt港区立芝浜小学校の児童たちは、土足のまま教室で授業を受けている様子。
alt港区立芝浜小学校の児童たちは、土足のまま教室で授業を受けている様子。
一足制のメリット:スムーズな移動と避難
港区立芝浜小学校の宮﨑直人校長先生によると、一足制のメリットは、靴の履き替えがないため、教室への入退室や避難時の移動がスムーズになることです。災害時など、迅速な避難が必要な場面では特に有効でしょう。
上履きのメリット:気持ちの切り替え
一方で、港区で唯一一足制を導入していない青山小学校の可児亜希子校長先生は、上履きには「気持ちを切り替える」効果があると指摘します。上履きへの履き替えを通して、学習モードへの切り替えを促すことができるという考え方です。
専門家の意見
教育心理学者の田中先生(仮名)は、「服装や持ち物を変えることで、人は無意識のうちに心理的な切り替えを行う」と述べています。上履きへの履き替えは、子どもたちにとって学校生活へのスイッチを入れる役割を果たしている可能性があるとのことです。
神戸市での上履き復活:地域差と多様性
興味深いことに、古くから一足制が一般的だった神戸市では、近年上履きを復活させる動きが見られています。これは、各地域の環境や教育方針の違いを反映していると言えるでしょう。
子どもたちの声:意外な反応
一足制を導入している学校の子どもたちからは、「お母さんが昔は学校で土足はダメだったと言っていた」といった声や、下駄箱の存在を知らない子どももいるなど、時代と共に学校生活の風景が変わっていることが伺えます。
まとめ:変化する学校生活
一足制には、スペース確保やスムーズな移動といったメリットがある一方で、気持ちの切り替えという上履きのメリットも無視できません。それぞれの地域や学校の状況に合わせて、最適な方法を選択していくことが重要と言えるでしょう。今後、一足制を取り巻く議論はさらに活発化していくと考えられます。