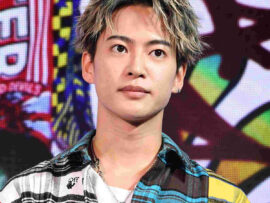1970年代に一世を風靡した傑作マンガ『ベルサイユのばら』が約50年の時を経てスクリーンに蘇った。『ベルサイユのばら』がアニメ化されるのは、これが初めてではない。1979年に東京ムービー新社(現・トムス・エンタテインメント)によって全40話のテレビアニメとして制作されている。長浜忠夫・出崎統といった日本アニメ史に残る人物が監督しており、日本のテレビアニメを語る上でも重要な作品と言える。
昨今、アニメ業界ではリメイク企画が増加しており、リメイクとはどういうもので、それに対してどう向き合えばいいのか、筆者は以前リメイクアニメの創造性についてのコラムを寄せたが、『ベルサイユのばら』は、旧作と新作を比較しがいがあるタイトルだ。どちらのほうが優れているという視点ではなく、アプローチと指向性の違いが明瞭であり、比較することで原作の持つ多面的な魅力に気が付き、「映像作品には単一の正解はない」ということがわかるからだ。
とりわけ、ジェンダー表象とフランス革命を真正面から扱ったという点で『ベルサイユのばら』は先進的と評された作品だったが、この点を踏まえて、新劇場版と旧テレビアニメ版がどのように異なるのかについて、分析してみたい。
旧テレビ版と新劇場版の違い
池田理代子のマンガ『ベルサイユのばら』は全10巻。最終10巻は外伝の位置付けなので、本編は実質全9巻となる。テレビアニメ版は全40話で構成されており、原作にはないエピソードも多数含まれている。新劇場版の上映時間は113分で、原作から多くのエピソードを取捨選択し再構成している。
テレビアニメ版は、シリーズの前半は長浜忠夫氏が監督を務めていたが諸般の事情で降板、数話空けて出崎統氏がその後を引き継いでおり、前半と後半で作風が異なる。テレビアニメ版は制作中にかなりの紆余曲折を経ているものと推察される。
監督が交代していることもありシリーズ全体の指向性を一言でまとめるのは難しいのだが、フランス革命前夜の時代のうねりの描写に重心を置いているとは言える。とくに出崎監督が担当している後半はその傾向が強い。シリーズ後半は、困窮する民衆側の描写が増えていき、革命を目指す市民側に立つキャラクターが活躍するエピソードも増加する。ロべスピエールやベルナール・シャトレ、そして原作では出番が多くないサン・ジュストのエピソードもかなり増やされ、民衆側からの王政に対する突き上げが強くなっていくプロセスが丹念に描かれる。特にサン・ジュストの狂気的な行動は原作にない要素で、革命の暗い部分が原作以上に協調されていると言える。その激動の時代の中で、オスカルも含めた登場人物たちが翻弄される様を群像劇のように描写している。
一方で今回の劇場版は、約2時間の尺に収めないといけないという事情もあってか、革命の描写を大きくそぎ落とし、オスカルという人物の年代記として構成している。革命や貧困にあえぐ市民の描写は存在するが、あくまでオスカルという人物の考えが変化していく様を描くための道具立てとしての描写であり、主眼はそこに置かれていない。黒い騎士の出番はないし、困窮する民衆を代表するロザリーの出番も大幅に少なくなっている。あくまで、オスカルというキャラクターの生き様と、彼女をめぐる愛の交錯と、民衆の自由への意思に触発されていく部分などにスポットを当てて描いている。