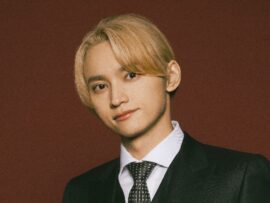私たちは、「性格診断」が好きだ。
星座占いから「MBTI」に至るまで、人びとは多種多様な診断に導かれ、自分をあらわす「キャラクター」たちに魅了されてきた。
無数の「あるある」ネタを楽しみながら、ふと我に返る。
ここに描かれているのは、ほんとうの私だろうか。
違うとすれば、ほんとうの私はどこにいるのだろうか。
そもそも「ほんとうの私」なんて、存在するのだろうか。
現代社会を覆い尽くす、過剰な「キャラ」に違和感を感じるあなたへ。
美学者・難波優輝氏による【連載】「物語批判の哲学」第4回へようこそ。
【連載】「物語批判の哲学」第4回:性格を「つくる」・前篇
>>まだお読みでない方は、第1回・前篇「面接にも広告にも…「人生は物語」に感じる違和感の正体!「ナラティブ」過剰の問題」もぜひお読みください。
「診断」に魅了される人間
人は自分をキャラクタにするのが好きだ。
例えば、いま、また新しい性格診断の流行がある。MBTIと呼ばれる、人の性格を16タイプに分けるものである。だが、これは真の自分の性格を表していると言えるのだろうか。
そもそも16Personalities診断はMBTI学会からも批判されているし、心理学的に言えば、本家のMBTIも構成概念としては甚だ怪しい、と批判されている(Stein et al. 2019)。
しかしそれはそれとして、MBTIのように、何らかのカテゴリ群のなかに自分の性格がマッピングされることの独特の快楽とは何なのだろう(さいきんは「MBTIグミ」も販売されており、人びとは相当にキャラクターとして生きるのが好きなようである)。
あるいは、けんすう『物語思考』(幻冬舎)のように、自分のキャリアを選んだり生き方を考えるために自分を主人公、キャラクターに見立てることを勧める自己啓発本も存在する。
さらには、近年では、ASDやADHDの当事者やそうした認知傾向に共感を覚える人びとが「ASDあるある」や「ADHDあるある」を投稿したりして共感の輪を広げている。
かくのごとく、人びとは、何らかのカテゴリに対してキャラクター化を行っており、これは自己の物語化の重要な一つの実践だと考えられる。
このような物語化の実践は、必ずしも人びとに快楽のみを与えるわけではない。
MBTIの場合は、特定のパーソナリティが(ユーモアであったとしても)揶揄されたり貶められることがあり、さらには、会社でMBTIを選抜で用いたりもするというから、差別の温床になる危険性さえあるだろう。
なぜ人びとはキャラクター化に魅せられるのか。これらの何が悪さをしているのか。
本稿の目的は、キャラクター化がもつ社会的・心理的影響を精査し、その背後にある「自己理解の構造」を浮き彫りにする点にある。
物語はキャラクター化と結びついて個々人の経験を豊かに彩る一方で、ステレオタイプや固定的な役割分担を生み出す力をももつ。MBTIのような性格分類が昨今のSNS文化と結びつき、安易に「ラベル貼り」や「自己の固定化」を誘発している現象は、物語批判の哲学において見過ごせない問題といえる。
本稿では、MBTIのような性格診断を人々が好んで受け入れ、自分自身を「キャラクター化」する傾向に注目し、それがどのような構造をもっているかを明らかにする。
人々は往々にして自分をキャラクターや物語の主人公に見立て、そこから得られる独特の快楽を味わう。この現象を近年の人類学的思考のなかで非常に興味深い議論を行っているテリ・シルヴィオの「アニメーション」という概念を参照しながら検討していきたい。最後に、本連載のまとめとして物語批判の到達点を明確化しよう。