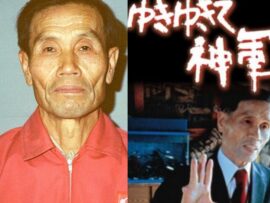近年の地震活動の活発化を受け、南海トラフ巨大地震への懸念がますます高まっている。政府の地震調査委員会も発生確率を80%程度に引き上げ、32万人もの死者が出る可能性があるとされる未曽有の災害への備えが急務となっている。では、巨大地震発生前に現れる「予兆」とは一体何なのか? 過去の事例や最新の研究から、その兆候を読み解いていく。
過去の地震活動から読み解く「予兆」
過去の南海トラフ地震では、発生の約40年前からマグニチュード(M)6クラスの地震が関西地方で10回近く発生していたという。関西大学特別任命教授の河田惠昭氏は、阪神・淡路大震災以降、M6以上の地震が既に7回発生している点を指摘し、あと2回程度の発生で警戒レベルをさらに引き上げる必要があると警鐘を鳴らす。特に、500年以上活動していない奈良の東縁断層と京都の花折断層に注目が集まっている。これらの断層に蓄積されたストレスが、大規模な地震を引き起こす可能性があるためだ。
 地割れ
地割れ
“流体”に着目する新たな視点
東京科学大学理学院教授の中島淳一氏は、地下約100kmにある「流体」に着目している。プレート境界に流体が入ると「潤滑油」のような役割を果たし、プレートがゆっくり滑る「スロースリップ」現象を起こす。東日本大震災や能登半島地震にも、この流体が密接に関わっていたことが明らかになっている。また、松代群発地震では地下水の噴出が確認されており、これは地下の流体が地上に溢れ出たものと考えられる。南海トラフ地震においても、流体の活動が重要な鍵を握っている可能性が高い。
温泉の異変は巨大地震の予兆か?
筑波大学生命環境系教授の山中勤氏は、温泉水の変化から地震の予兆を捉えられる可能性を示唆する。有馬温泉の温泉水はフィリピン海プレート由来の水と水質がほぼ同じであり、阪神・淡路大震災前にラドン濃度の上昇が観測された。和歌山や静岡など、南海トラフ地震の震源域となりうる地域にも、プレート由来の成分を含む温泉が存在する。温泉水の温度上昇、色の変化、感触の変化などは、南海トラフ地震の予兆となる可能性があるという。
備えあれば憂いなし:今できること
南海トラフ地震は、いつ起きてもおかしくない状況にある。巨大地震発生の「予兆」を理解し、日頃から防災意識を高めることが重要だ。家族や地域との連携を強化し、避難経路の確認、非常持ち出し袋の準備など、具体的な対策を進めていく必要がある。
専門家たちの分析を踏まえ、南海トラフ地震への危機感を改めて認識し、万が一の事態に備えよう。