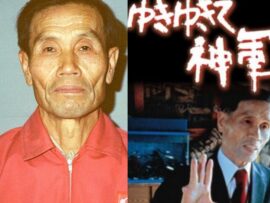日本政治の「ガラスの天井」を破り、女性初の首相となる可能性を秘める高市早苗氏(64)。もし実際に首相に就任した場合、ある疑問が浮上します。それは、大相撲本場所の優勝力士に贈られる内閣総理大臣杯を、高市首相が慣例通り土俵上で授与できるのか、というものです。大相撲では土俵が「女人禁制」とされており、その是非については長年議論が繰り返されてきました。伝統と現代社会の価値観が衝突するこの問題について、日本相撲協会の見解と識者の分析を交えながら、その実情を探ります。
大相撲土俵「女人禁制」の根源と歴史
そもそも、なぜ大相撲の土俵は「女人禁制」なのでしょうか。その理由には諸説ありますが、日本相撲協会は2018年、理事長談話を通じて協会としての公式見解をまとめています。
協会が挙げる主な理由は以下の3点です。第一に相撲がもともと神事を起源としていること、第二に大相撲の伝統文化を守りたいこと、第三に大相撲の土俵は力士らにとって男が上がる神聖な戦いの場、鍛錬の場であることです。「神事」という言葉から、「協会は女性を不浄とみなしていた神道の昔の考え方を女人禁制の根拠としている」と解釈されることがありますが、協会はこの見方を「誤解である」と明確に否定しています。
1978年には、当時の労働省の森山真弓・婦人少年局長(後に女性初の内閣官房長官となる)がこの問題について尋ねた際、伊勢ノ海理事(柏戸)は「けっして女性差別ではありません。土俵は力士にとって神聖な闘いの場、鍛錬の場であり、力士は裸にまわしを締めて土俵に上がる。大相撲の力士には男しかなれず、大相撲の土俵には男しか上がることがなかった。そうした大相撲の伝統を守りたいのです」と説明しました。この説明は、伝統と性別の役割分担に重点を置いていることを示唆しています。
論争を巻き起こした過去の事例
「女人禁制」を巡る社会的な議論は、近年特に活発化しています。2018年4月には、京都府舞鶴市で行われた大相撲の地方巡業「舞鶴場所」で、多々見良三市長(当時)が土俵上で挨拶中にくも膜下出血で昏倒するという痛ましい事故が発生しました。その際、会場に居合わせた女性看護師らが人命救助のために土俵に上がって心臓マッサージなどの救命措置にあたったところ、行司から「女性は土俵から下りてください」というアナウンスが繰り返し流されました。この出来事は「人命としきたりのどちらが大切なのか」と大きな物議を醸し、当時の八角信芳理事長は後に「不適切な対応でした」と謝罪する事態となりました。
同じ2018年4月には、当時兵庫県宝塚市長だった中川智子氏が、地方巡業「宝塚場所」で土俵上での挨拶を希望しました。しかし、協会側はこれを認めず、土俵下に設けた“お立ち台”から挨拶を行うよう求めました。
過去にも、女性が公的な立場で土俵に上がることを試みた例は複数あります。森山真弓氏は首相代理として内閣総理大臣杯の授与を、女性初の大阪府知事となった太田房江氏も大阪府知事賞の授与を、いずれも土俵上で行いたいとの意向を示しましたが、最終的にその願いは実現しませんでした。これらの事例は、「女人禁制」という伝統が、たとえ公的な役割を担う女性であっても、容易に破られることのない強固な壁として存在してきたことを物語っています。
 日本国旗を背景にインタビューに応じる高市早苗氏。女性初の首相として、相撲界の伝統とどう向き合うのか注目される。
日本国旗を背景にインタビューに応じる高市早苗氏。女性初の首相として、相撲界の伝統とどう向き合うのか注目される。
識者の見解:伝統文化と現代社会の調和
長きにわたり続く「女人禁制」の現状について、角界に詳しい識者はどのように見ているのでしょうか。約40年の取材歴を持つ相撲ジャーナリストの横野レイコ氏は、この問題について独自の視点を示しています。
横野氏は、「歌舞伎で女性が舞台に立てないのと同じように、相撲において土俵は『神が宿る聖域』として男たちの手で守られてきました。それは男尊女卑とは別の話です」と語ります。外部の事情によって一方的に歴史と伝統を崩すよう求めることは、「暴力的な感じがする」と指摘し、伝統文化の尊重を訴えています。
もし高市首相が内閣総理大臣杯を手渡したいと意向を示すのであれば、その解決策として、土俵脇に表彰台を設け、優勝力士が歩み寄って受け取る形を提案しています。これは、土俵の神聖さを保ちつつ、女性の公的な役割を尊重する現実的な妥協案と言えるでしょう。伝統文化の価値を認めつつ、現代社会の要請にどのように応えるか、という難しい問いに対する一つの回答を示しています。
「ガラスの天井」と相撲界の未来
高市早苗氏が女性初の首相として「ガラスの天井」を破ることは、日本の政治史における画期的な出来事となるでしょう。しかし、その先に横たわる大相撲の「女人禁制」という伝統は、また別の「ガラスの天井」として立ちはだかります。この問題は、単なる慣習ではなく、日本の精神文化や歴史に深く根ざしたものです。
政治の世界では女性の活躍が推進され、多様性が叫ばれる一方で、大相撲の世界では揺るぎない伝統が守られています。女性宰相の誕生という社会の変化が、相撲界の伝統にどのような影響を与え、どのような対話を促すのか。人命救助の現場でさえ優先された伝統と、現代社会の価値観との間で、今後も模索と議論が続いていくことでしょう。
結論
高市早苗氏がもし女性初の首相に就任した場合、大相撲土俵の「女人禁制」という慣例は、再び社会的な注目を集めることになります。この問題は、相撲が神事を起源とし、男性力士の「聖域」として守られてきた長い歴史と、現代社会が求めるジェンダー平等、多様性の尊重という価値観との間の深い溝を浮き彫りにします。過去の事例や識者の見解が示すように、伝統を守ることの重要性と、時代に応じた柔軟な対応の必要性の間で、日本相撲協会は常に難しいバランスを求められてきました。
女性初の首相が伝統文化の象徴である大相撲にどう向き合うのか、あるいは大相撲が女性宰相という新たな時代の象徴にどう対応するのかは、単なる儀式の問題を超え、日本の伝統と社会の変化、そして多様性を受け入れる文化的な成熟度を問う重要なテーマとなるでしょう。今後の進展が注目されます。
参考文献