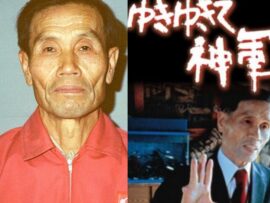先月発足した高市内閣が異例の高支持率を記録し、世論調査では概ね7割前後、中には8割を超えるものもある。その華々しい船出の陰で、かつて「知性的」「改革派」とも評された石破政権がなぜ国民に見放されたのか。その失敗の本質を冷徹に分析する。
国民への姿勢が招いた「だらしなさ」の内実
高市内閣の熱狂的な支持とは対照的に、権力の座から滑り落ちた石破茂前首相、そして彼の政権中枢を担った側近の平将明氏、木原誠二氏の凋落は、単なる権力闘争の帰結ではない。彼らが掲げた政策の表面的な薄さ、国民を欺くような姿勢、そして政治家としての核心的な欠如が招いた必然の結果と言える。
かつて石破内閣発足時に閣僚写真で指摘された「だらし内閣」という揶揄は、単に服装の問題に留まらなかった。それは、思想、政策、そして何よりも国民に対する姿勢そのものに潜む「だらしなさ」であり、それが彼らを決定的な敗北へと導いたのだ。本稿では、石破氏ら三名の政治家がいかにして信頼を失墜させたのか、その本質を詳細に検証する。
 石破茂前首相が国連総会で行った演説会場の様子。聴衆は少なく、退任直前の政権の末期を象徴している。
石破茂前首相が国連総会で行った演説会場の様子。聴衆は少なく、退任直前の政権の末期を象徴している。
「知性」と「政策通」の虚像:石破茂氏の歴史認識の浅さ
石破茂氏は長らく「知性的」「政策通」というイメージを前面に出してきたが、そのメッキは容易く剥がれ落ちた。象徴的な出来事の一つが、戦後80年談話の構想を巡る発言で露呈した、彼の驚くべき歴史認識の浅薄さである。
石破氏は、リベラルな姿勢を演出するかのように政治学者・丸山眞男を引用し、「元老院のおかげで軍事の暴走が止められた」と主張した。しかし、この一見知的な響きを持つ発言は、歴史的事実を致命的に誤解した、空虚な言葉遊びに過ぎなかった。丸山眞男が論じたのは、明治期における元老院の限定的な軍事コントロール機能であり、昭和初期に日本を破滅へと導いた満州事変以降の軍部の暴走は、元老院の衰退が直接の原因ではない。その真の原因は、政党政治の機能不全や統帥権の独立といった、国家システム全体の構造的な欠陥に根差していたのだ。石破氏の発言は、自身のイメージ戦略のために歴史を都合よく解釈しようとする姿勢を浮き彫りにした。
結論
石破政権の失敗は、単なる政治的手腕の不足にとどまらない。それは、国民への真摯な姿勢の欠如、表面的な知性や政策論議に終始し、本質的な深みを伴わない政治の限界を示唆している。高市内閣が国民の期待を集める今、過去の失敗から教訓を得て、日本の政治が真に国民のためのものであるよう、その本質を問い直す時期に来ている。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (2025年11月3日). 失敗の本質はどこに?. https://news.yahoo.co.jp/articles/f45f469b0ecdd2ea07166814ee88be2bc4e0291f